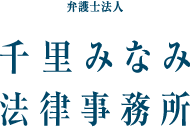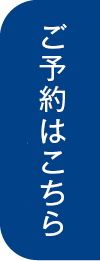【徹底解説・共同親権】最新情報からひも解く共同親権制度の概要
共同親権制度が導入されることが決まり、どのような制度設計になるかということがかなり分かってきました。
そこで、当事務所にて最新の情報に基づいて、多くの方が疑問に思われるであろう点をまとめてみましたので、参考にしていただきたいと思います。
・今後離婚する人は全員共同親権になるのか?
・夫婦の協議で共同親権にするか、単独親権にするか決まらなかった場合はどうする?
・裁判所が共同親権にするか、単独親権にするかを判断する際にどういったことを考慮するか?
→こちらの記事を参照ください。
・裁判所が共同親権にするか、単独親権にするかを判断する際、原則はどちらにするのか?
→こちらの記事を参照ください。
・夫婦(父母)が別居している事案において、裁判所が共同親権と判断するのはどういった場合か?
→こちらの記事を参照ください。
・共同親権とした場合、子どもはどちらの親と暮らすことになるのか?
・子どもと一緒に暮らす親にはどのような権限が与えられるのか?
→こちらの記事を参照ください。
・共同親権であっても単独で親権を行使できるのはどのような場面か?
・共同で親権を行使しなければならない事項について意見が対立したときはどうするのか?
・共同親権と監護権の関係性とは?
→こちらの記事を参照ください。
・現行制度と同様、親権者が決まるまで離婚することはできないのか?
→こちらの記事を参照ください。
・すでに離婚している人は共同親権とすることができるのか?
・すでに離婚している人が共同親権となるのはどのような場合か?
→こちらの記事を参照ください。
・共同親権とした場合、子どもの姓はどうやって決めるのか?
→こちらの記事を参照ください。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。
【大阪の離婚弁護士が教える】将来離婚することやその場合の条件を定めることは有効か
「【大阪の離婚弁護士が教える】将来離婚することやその場合の条件を定めることは有効か」という記事を離婚専門サイトにアップしました。
【大阪の離婚弁護士が教える】婚姻費用・養育費は、当月分を当月払いなのか翌月分を当月払いなのか
「大阪の離婚弁護士が教える】婚姻費用・養育費は、当月分を当月払いなのか翌月分を当月払いなのか」という記事を離婚専門サイトにアップしました。
【大阪の離婚弁護士が教える】再婚する時の子どもの姓(苗字)と養子縁組。子どもの苗字を変えたくない場合はどうする?【全パターン解説】
1.はじめに
再婚する際に、子どもと再婚相手が養子縁組をするかどうか、また、子どもの姓(苗字)をどうするかという問題に頭を悩ませるケースは少なくありません。
以下では、母が子ども(未成年・独身)の親権者となっている状況において、当該母親が再婚し、再婚相手の戸籍に入籍する(母は再婚相手の姓を名乗る)という典型ケースを想定した上で、子どもも再婚相手と同じ姓を名乗る場合と子どもは現在の姓を名乗り続ける場合に分けて、解説していくこととします。
2.子を再婚相手と同じ姓(苗字)にする場合
① 養子縁組をする場合
子どもと再婚相手が養子縁組をする場合、子どもは養親の姓を名乗ることになります(民法810条本文)。
そして、子どもは養親の戸籍に入ります(戸籍法18条3項)。
結果的に、母、子、養父のいずれもが同一の戸籍に入り、同一の姓を名乗る形になります。
② 養子縁組をしない場合
母が再婚相手の戸籍に入籍し、再婚相手の姓を名乗る場合であっても、養子縁組をしないのであれば、自動的に子どもが再婚相手の姓になるわけではありません。
もっとも、養子縁組はしないものの、母と子の姓が違うことは避けたいということで、母と同じ姓にしたいと考える方もおられます。
そのような場合、子どもと再婚相手が養子縁組をすることなく、子どもが再婚相手の姓を名乗ることが可能です。
具体的には、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受けて(※この点については、最後に専門家向けの解説をしています)、役所に入籍届を出すことになります。
これによって、母、子、再婚相手は同一の戸籍に入り、同一の姓を名乗ることが可能になります(ただし、①と異なり養子縁組をしていないため、子と母の再婚相手との間に法律上の親子関係は生じません)。
3.子が姓(苗字)を変えない場合
親が再婚したとしても、子どもは姓を変えたくないという場合もあります。
この場合、以下のような方法をとれば、子どもは現在の姓を名乗り続けることが可能となります。
① 子のみ現在の戸籍に残る場合
再婚する前の戸籍は、母を筆頭者として、その戸籍に子どもが入っているという形になっているはずです。
母が再婚し、母が再婚相手の戸籍に入籍することによって、上記の従前戸籍は、筆頭者である母が除籍になった状態となります。
そして、このままにしておけば、子どもは筆頭者が除籍された戸籍に残り続けるため、子どもの姓は変わらないことになります。
なお、この場合は母親と子どもの姓が異なる形(親子で苗字が違うという状態)になりますので、その点は注意が必要です。
また、このパターンの場合は、子どもと再婚相手は養子縁組をしていませんので、子どもと再婚相手との間に法律上の親子関係はありません。
ちなみに、冒頭に挙げたとおり、ここでの解説は、子どもが未成年のケースを想定していますが、子どもが成人しているケースであれば、子どもだけが残された状態の従前戸籍から、子どもが分籍して、子ども単独の新戸籍を編製することも可能です。
②再婚相手を母の戸籍に入れる場合
ここまでの説明は、母が再婚相手の戸籍に入籍するというケースを想定してきましたが、そうではなくて、再婚相手が母を筆頭者とする戸籍に入籍するという場合であれば、子どもの姓は変わりません(姓が変わるのは再婚相手です)。
子どもの姓を変えたくなく、かつ上記①のように親子(母子)で姓が異なるということを避けたいという場合に、再婚相手の了承が得られるようであれば、このような方法をとることを検討されてもよいと思います。
4.再婚相手と子が養子縁組することなく、再婚相手の戸籍に子を入籍させる際に家庭裁判所の許可が必要か
上記2②のパターンの場合、すなわち、再婚相手と子どもが養子縁組はしないけれども、再婚相手の戸籍に子どもを入籍させる場合に、子の氏の変更手続にあたって家庭裁判所の許可が必要かという点が問題となります。
この点について、「再婚相手と養子縁組をしない子どもの戸籍 離婚により子どもを引き取った母が再婚して、再婚相手の氏を称している場合(民法750条)でも、連れ子の氏は当然には影響を受けません。この場合、子どもの氏と母の氏が異なることになりますから、子どもの氏を母の氏に変更するには、民法791条2項により子の氏の変更手続(入籍の届出、戸籍法98条1項)をしなければなりません。この場合は家庭裁判所の許可は不要です。」とする文献があります(冨永忠祐著『Q&A再婚の法律相談 離婚・死別からのステップ』日本加除出版124-125頁)。
一方で、戸籍実務を取り扱う役所のホームページを見ると、次のような記載があります。
東京都大田区
母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
福井県坂井市
母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには「入籍届」が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
母(父)の再婚相手が、子の父(母)であるときは、許可は必要ありません。
では、いずれが正しいのでしょうか。
民法791条を見てみることにしましょう。
第791条
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
この条文を見ればわかるとおり、原則として、子と母の氏が異なる場合に、子の氏を母の氏と同じにするためには家庭裁判所の許可が必要ということになります(民法791条1項)。
しかし、例外的に、民法791条2項が適用される場合には、家庭裁判所の許可なく入籍届を出すことができるという立て付けになっています。
では、再婚相手と子どもが養子縁組はしないけれども、再婚相手の戸籍に子どもを入籍させるというケースに民法791条2項が適用されるかというと・・・
再婚相手と子どもが養子縁組をしない以上、両者に法律上の親子関係はありませんから、子どもにとって母の再婚相手は「父」ではなく、「他人」です。
したがって、子どもから見れば、「他人と母が婚姻している」という状態にすぎず、民法791条2項にいう「父母の婚姻中に限り」という要件をみたしません。
そのため、上記ケースでは、民法791条2項は適用されず、原則どおり、子の氏の変更手続のためには家庭裁判所の許可が必要ということになります。
これが、たとえば、次のような子どもの両親が復縁したという稀なケースであれば民法791条2項が適用されます。
山田A男と鈴木B子が結婚して、B子の姓は山田になった。
その後、山田C子という子どもが生まれたが、A男とB子は離婚し、B子がC子の親権者となった。
その結果、B子は旧姓である鈴木姓に戻り、C子も鈴木姓になった。
ところが、その後A男とB子が復縁して、再婚してB子は再度山田姓になった。
そこで、C子を山田姓に戻すために、C子をA男の戸籍に入籍させたい。
このようなケースであれば、C子から見ればA男は実の父親ですから、「母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合」であり、かつ「父母の婚姻中」ということになり、民法791条2項が適用され、家庭裁判所の許可は不要となります。
先ほど挙げた福井県坂井市のホームページに「母(父)の再婚相手が、子の父(母)であるときは、許可は必要ありません。」とあるのはこのようなケースを指しているわけです。
その他に、民法791条2項が適用される場面としては、ある男性が子どもを認知した後に、その男性と子どもの母が結婚するような場面などがあります。
以上見てきたとおり、再婚相手と子どもが養子縁組はしないけれども、再婚相手の戸籍に子どもを入籍させる場合には、家庭裁判所の許可が必要と捉えて差し支えないと思われます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の離婚弁護士が教える】別居中に妻が夫名義の車を運転して事故を起こした場合、夫も責任を負うか
1.はじめに
今回は離婚と交通事故という二つの分野にまたがるテーマについて解説してみたいと思います。
実務上、夫婦が別居しており、離婚協議中あるいは離婚調停中という状況下においても、妻が夫名義の車を利用しているということがあります。
この場合、妻が交通事故を起こすと、夫も責任を負うことになるのかということについて見ていきたいと思います。
※以下では、夫名義の車を妻が運転したケースを想定して解説をしていますが、妻名義の車を夫が運転したというケースでは、「夫」と「妻」の表記は入れ替わりますので、その点ご注意ください。
2.夫の運行供用者責任
たとえば、別居後も妻が夫名義の車を使用している状況下で、妻が人身事故を起こしたとします。
この場合、事故の被害者は、通常は、車を運転していた妻に対して損害賠償請求を行うことになりますが、それだけではなく車の所有者である夫に対しても損害賠償請求ができるのでしょうか。
夫からすれば、妻とは離婚を前提に別居をしていることから、妻が起こした事故によって自分が責任を負うことには納得できないという思いを抱いてもおかしくありません。
しかし、夫は運行供用者責任(自賠法3条)を負う可能性があり、そうなると事故の被害者は夫にも損害賠償請求をすることができるということになります。
つまり、妻が起こした事故であっても、車の所有者である夫はその事故の責任を負う可能性があるということになります。
3.夫が責任を回避できる場合はあるか
運行供用者責任が問題となる類型としては、①泥棒運転、②無承諾運転、③詐取的な利用・所有者等の意思に反して借り受け人が返還しない場合、④名義残りの場合などがあるといわれています(以下、参考文献として、藤村和夫ほか編著『実務交通事故訴訟体系 第2巻』41頁~45頁)。
① 泥棒運転
盗難にあった車が、所有者等使用権者の意思に基づかない運行によって人身事故を起こした場合には、一般的には所有者等使用権者は運行供用者責任は負わないとされます。
しかし、実務上は、所有者等使用権者の管理に過失がある場合には、事故発生が盗難直後の比較的短時間内であり、盗難前にあった場所とそれほど離れていない場合には、所有者等使用権者の運行供用者責任が肯定される場合があります(※こちらの記事もご参照ください)。
別居中に妻が夫名義の車を盗難したという事例は想定し難く、仮に夫が妻に車を盗難されたと主張したとしても、両者には夫婦という人的関係があることから、この類型によって運行供用者責任が否定されることは困難といえそうです。
② 無承諾運転
所有者等使用権者と親族関係・雇用関係等の密接な関係がある当事者が、無断で運転した場合には、所有者等使用権者が当該運転行為を承諾していない場合でも、所有者等使用権者の運行供用者責任は肯定される傾向にあります。
したがって、夫の承諾を得ることなく、妻が勝手に運転したという場合であっても、夫に運行供用者責任が認められるということになりそうです。
③ 詐取的な利用・所有者等の意思に反して借受人が返還しない場合
前述した参考文献には次のような記載があります。
すぐ返すからと言って借り出した自動車を、返還請求しても借主が言を左右にして返還しない場合、あるいは、レンタカーを借りた者が返還期限を過ぎてもなかなか返さず、連絡もできない状態になってしまう場合、貸主の運行供用者責任が否定されるのは難しいであろう。しかし、当初は任意に引き渡したものの、所有者等の意思に反して返還しようとしない態度が明白になった状態では、所有権等使用権者の立場は無視され奪われたに等しいから、自分の目的のために使っている状態は消滅したとすべき場合もあると思われる。ただ、このような状態だと評価されるためには、引渡し後ないしは返還期限から相当期間経過していることが必要であろう。また、所有者等使用権者が、当該自動車の返還要求を明確な形で行い、借りた側がその意向を無視していることが明らかな状態になっている必要がある。そこまでの心証がとれない状態の場合は、所有者等使用権者の運行供用者としての立場が消滅しているとはできないと考えるべきである。
この説明を前提にすると、夫が妻に対して、車の返還を明確に求めているにもかかわらず、妻が相当期間返還に応じないというような場合には、夫は運行供用者責任を免れる可能性があるかもしれません。
④ 名義残りの場合
自動車を他の者に譲渡したものの、自動車登録上の所有名義の変更手続をとっていない場合(いわゆる「名義残り」)における形式的所有名義人については、運行供用者ではないとされるのが、判例の傾向であって、代金が未払いのまま曖昧な利用関係が継続しているなど売買当事者間に特別な関係がある場合には例外的に旧所有者の責任が肯定されるといわれています。
そうすると、すでに夫婦間で夫名義の車を妻に譲渡するという合意ができているものの、名義変更の手続きがなされていないにすぎない状態の場合であれば、夫の運行供用者責任が否定される可能性がありそうです。
4.できる限り早めの名義変更を
以上のとおり、夫が運行供用者責任を回避できるケースは限定的であろうと思われます。
実際、全く面識のない者が運転して起こした事故であっても、車の所有者が運行供用者責任を負うとした事例もあり(最判平成20年9月12日判タ1280・110)、運行供用者責任は比較的広く認められています。
仮に離婚協議中・離婚協議中に妻が夫名義の車で事故を起こしたことで、夫も責任を負うとなれば、当事者間の紛争は激化・長期化することにもなりかねません。
そこで、万が一の事故に備えて、もし離婚後も妻が車を使用することで合意ができているのであれば、離婚を待たずに車の名義変更等を行い、車に関しては財産分与を先行して処理してしまうという方法も検討の余地があります。
この場合、自動車保険も夫が契約者となっていることが多いと思われますので、自動車保険の名義変更もあわせて検討してみてください。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の離婚弁護士が教える】モラハラで慰謝料が認められるか
1.離婚の際に必ずしも慰謝料が発生するわけではない
離婚する際には、離婚原因を作った側が慰謝料を払わなければならないと考えている方がおられますが、そのようなことはありません。
慰謝料の支払いなく離婚が成立するケースも多々あります。
慰謝料が問題となる典型ケースは不貞行為があった場合や暴力があった場合です。
では、モラハラ行為があった場合はどうでしょうか。
ネット上では、モラハラがあった場合には慰謝料が発生するかのように読める記事が散見されますが、以下に紹介する裁判例を見ていただくとわかるとおり、訴訟にまで至ったケースではそもそもモラハラを理由とした慰謝料を認めないものが相当数あります。
以下では、モラハラが問題となった裁判例を通じて、モラハラ行為によって慰謝料が発生するかを見ていきたいと思います。
2.モラハラ行為と慰謝料に関する裁判例
① 夫が妻に対して人格否定的な発言をした事例(東京地判令和4年4月26日)
【妻の主張】
被告Y1(注:夫)は、原告(注:妻)の人格を卑しめる以下のような発言を日常的に繰り返し、原告に精神的苦痛を与え続けてきた。
被告Y1は、平素より、家族を蔑視して家族の犠牲の上に自らの金銭的欲望を追求する姿勢を示していた。
被告Y1は、令和2年1月11日当日も、原告の行動を監視しようとしたり、被告Y1の女性関係に口出ししないことを要求したりと、女性を蔑視する傍若無人な発言を繰り返している。原告が被告Y1にDVの損害賠償を求めたものの、同月12日には「おまえ、デリヘルでもやってるのか?www」と不条理に原告の人格を非難した。
被告Y1は、「俺に女として接する努力もしない」、「嫁として機能してない」、「いい歳して、…盛ってるんじゃねーよwww」、「クソ雑魚」など、原告の人格と尊厳を貶める発言を繰り返していた。
【夫の主張】
被告Y1(注:夫)が原告(注:妻)にした発言は認めるが、原告が大学時代の知人男性と外出するために息子を遅い時間まで一時保育に預けていたことが被告Y1に分かったことから、腹立ちまぎれに発したものである。
【裁判所の判断】
被告Y1(注:夫)が、原告(注:妻)に対し、原告が主張するような発言をSNS上でしていたことは認められる(甲11から12)。
しかし、被告Y1の発言が不適当であるとしても、これらが原告に対する不法行為を構成するに至る程度の違法性ある発言かどうかは、原告と被告Y1の従前のやり取り等を踏まえて判断すべきところ、これらの発言のみをもって不法行為であると判断するに足りない。
➢モラハラ発言について慰謝料を認めなかった。
② 夫がSNS上で妻の人格を否定する発言をするなどした事例(福岡家判令和4年1月17日)
【妻の主張】
被告(注:夫)は,面会交流調停の時点から,原告(注:妻)を誘拐犯人呼ばわりするなど,原告を攻撃するような言動を行っていたほか,極めて拡散性が高く,原状回復が困難なSNSというツールを用いて,原告の人格を攻撃する言動を反復継続したことにより,婚姻関係は破綻に至り,原告は極度の精神的苦痛を受けたものである。これを慰謝するに足りる金額は,少なく見積もっても300万円を下回らない。また,被告が裁判外の解決に応じないことから訴訟提起を余儀なくされたものであり,弁護士費用相当額として30万円を加算し,合計330万円の支払を求める。
【夫の主張】
原告(注:妻)の指摘するSNSへの書き込みを行ったことは認めるが,被告(注:夫)は,突然,長女との接触を断たれた父親の悲しみや嘆きを,現状の制度への批判・問題提起,長女を一方的に連れ去った原告に対する意見という形で表明しただけであり,原告との関係を破綻させようとする意図はなかった。被告は,長女の近況の確認,十分な面会交流が実現できれば直ぐにでもアカウントを消去する旨を原告に伝えており,長女とのコミュニケーション(例えばテレビ電話等)の確保を約束してもらえれば,投稿を即時に削除する考えである。
【裁判所の判断】
原告(注:妻)は,被告(注:夫)が,SNSというツールを用いて,原告の人格を攻撃する言動を反復継続したことにより,婚姻関係は破綻に至り,原告は極度の精神的苦痛を受けたなどと主張する。確かに,被告は,不特定多数の者の閲覧が可能なSNSにおいて,原告を実子誘拐,連れ去りを行い,長女を人質に金銭を請求する者として繰り返し批判したほか,原告が被告に送付した長女の写真等を掲載するなどの行為に及んでおり,これらの行為が原告と被告の信頼関係を著しく損なうものであることは否定できない。他方,前記認定のとおり,被告が前記SNSへの書き込みを開始したのは別居から約2年近くが経過した令和2年7月以降であり,同時点において既に原告と被告との間の婚姻関係は破綻していたと認められるから,被告によるSNSへの書き込みが,婚姻関係破綻の原因であると評価することはできず,離婚慰謝料発生を認めるべき事由に当たるとはいえない。
➢SNSへの書き込みについて、慰謝料請求は認めなかった。
③ 夫が妻に対して心ない言葉をぶつけるなどした事例(東京地判令和 3年11月29日)
【妻の主張】
被告(注:夫)は,同居中,原告(注:妻)に生活を支えてもらっていたのに,原告が悪いかのように「お前は(夫婦の間の関係でも)損得ばかり考えている。」「俺の病気が長引いているのはお前が原因だ。」などと言って原告を追い詰めた。また,原告が被告のためを思って言うことにも,「(考え方の)押し付けだ。」などとわめき散らし,原告の心情を踏みにじった。
原告は,被告の上記諸行為により,うつ病を発症し,離婚を余儀なくされ,精神的損害を受けた。そして,不可解な弁解をして慰謝料の支払を拒否する被告の交渉態度により,原告の精神的損害は拡大した。その慰謝料は300万円を下らない。弁護士費用30万円も原告の損害である。
【夫の主張】
原告(注:妻)の言動こそモラルハラスメントと評価され得るものである。すなわち,原告は,ベッドが狭いと言って被告(注:夫)にベッドの下で寝ることを強要し,抑うつ状態のため休業中の被告に家事を強要し,照明の消し忘れ等を被告から注意されても改善せず,被告の両親からの帰省時のもてなしや被告の両親との近居を拒否する態度を示した。
被告と原告は,上記のような原告の言動に苦しんだ被告からの離婚申出に端を発し,双方の話し合いを経て離婚合意に至ったものであるから,離婚に伴う慰謝料が生じる余地はない。
【裁判所の判断】
この点に関する原告(注:妻)及び被告(注:夫)の主張の要旨は前記のとおりであり,お互いに相手の言動をモラルハラスメントと主張し,相手の主張はこれを争うという状況にあるところ,どちらの主張も決め手となる証拠による裏付けを欠くものであって,原告の主張のみを採用することはできない。
➢モラハラ発言を理由とした慰謝料を認めなかった。
④ 夫が妻に対して暴言を吐くなどした事例(東京地判令和2年11月19日)
【妻の主張】
被告(注:夫)は,婚姻後1年も経たないうちに,原告(注:妻)に対し,暴言を吐いたり暴行を加えたり無視するなどのモラルハラスメント行為を日常的に繰り返すようになった。
また,被告は,平成27年4月28日当時,A(以下「A」という。)と不貞関係にあり,同日,原告に対して同事実を認めたが,「不倫されるのはお前が悪いからだ。」などと述べ,反省の態度を見せることはなかった。
被告の上記不法行為により,原告と被告との婚姻関係は破綻した。
(中略)婚姻関係破綻の原因が被告のみにあることに加え,本件離婚が長男出産直後であったことなどを考慮すれば,本件離婚によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は300万円を下らない。
【夫の主張】
被告(注:夫)が原告(注:妻)に対して日常的にモラルハラスメント行為を繰り返し,不仲であったのであれば,長男は誕生していないはずである。また,被告は,原告に対し,Aとの不貞関係を謝罪して許しを得たから,Aとの不貞関係は離婚原因となっていない。原告と被告が離婚に至ったのは,原告から事ある毎に愚痴や不満を述べられ,束縛されることに疲れた被告の方から離婚を申し入れたからである。
【裁判所の判断】
原告(注:妻)は,被告(注:夫)による暴言,暴力等の日常的なモラルハラスメント行為及び不貞行為が離婚原因である旨主張し,原告作成の陳述書(甲17,29)にも同旨の記載がある。
しかしながら,原告は本件と直接の利害関係を有する当事者である上,その陳述書(甲17,29)は反対尋問を経ていないから,その証明力の評価は慎重にされるべきである。当該陳述書には被告による暴言や暴力の内容がある程度具体的に記載されていることは認められるものの(甲17),被告はこれらを否認しており,本件において,当時の会話録音や動画,画像等,被告による暴言や暴力を裏付ける的確な証拠は何ら存在しない。そうすると,上記陳述書の記載のみをもって,婚姻期間中に被告の原告に対する暴言,暴力等の日常的なモラルハラスメント行為があったと認めることは困難である。なお,証拠(甲14)によれば,原告が平成29年2月22日に新宿警察署に対して生活安全相談をした際の生活安全相談処理結果表(以下「相談処理結果表」という。)の「相談の要旨」欄には,「私は元夫と平成20年1月に結婚し,暴力はその1年後くらいから始まりました。」「暴力の頻度は2ヶ月に1回程度」などと記載されていることが認められるものの,これは原告の認識が一方的に記載されたものにすぎないから,上記認定,判断を左右しない。
➢モラハラ行為があったことを認定せず、慰謝料を認めなかった。
⑤ 夫が妻に対して暴言を吐くなどした事例(東京地判令和元年9月10日)
【妻の主張】
被告(注:夫)の原告(注:妻)に対する執拗なモラルハラスメント行為,愛犬〇〇の虐待行為や,夫婦間の信頼関係に重大な影響を及ぼす事実の秘匿・虚偽説明の発覚により,原被告間の婚姻関係は破綻し,原告は離婚を余儀なくされたものであり,これにより原告は著しい精神的苦痛を被った。
本件において,①被告が日常的に「キチガイ」「死ね」「子供をおろせ」等の暴言を吐き,大声で怒鳴るなどし,これらの行為は極めて頻回であって,その内容からも原告の受ける精神的負荷は極めて強度であること,②原告が婚姻以前から大切に飼育してきた〇〇に対する虐待は,原告にとって耐えがたい精神的苦痛を生じさせるものであること,③被告が婚姻中であり,離婚歴3回(当時の妻との離婚を除いても2回),前妻との間に子が1人いるにも関わらず,独身かつ離婚歴1回・子はなしと誤信させて交際を開始し,プロポーズをしたもので,これは配偶者にとって騙されたという甚大な精神的苦痛を生じさせるものであること等の事情が認められる。
さらに,原告は平成30年1月,環境要因すなわち被告の上記行為によって,めまい症,不眠症を発症するに至っている。
これらの事情を総合すれば,離婚により,又は,被告の不法行為により,原告に生じた精神的苦痛を慰謝すべき金額は200万円を下らない。また,同損害の回復に要する弁護士費用は20万円を下らない。
【夫の主張】
被告(注:夫)が日常的に「キチガイ」「死ね」「子供をおろせ」等の暴言を吐いたという事実はない。また,被告の離婚歴や子の存在については,原告(注:妻)も婚姻時には承知していた事実であり,それにもかかわらず知らなかったと虚偽の証言をする行為は非常に悪質である。
めまい症については,今回の件と因果関係はなく,原告の婚姻前からの持病であるメニエール病によるものである。不眠症についても同様に,今回の件と因果関係はない。
したがって,被告が賠償すべき損害はない。
【裁判所の判断】
(2) 婚姻後の被告の言動
ア 原告(注:妻)は,婚姻届出の3日後である平成29年9月21日,静岡に住む妊娠中の友人から遊びに来るよう誘われ,WhatsAppで被告(注:夫)に相談した。被告は,乗換案内情報を調べて原告に送信するなどしたが,妊娠初期に一人で行くべきではないと述べ,それでも行くなら自己責任で好きにすればよいと突き放すような返信をした。
このときのやり取りにつき,原告は,安定期に入ってからという前提で相談したところ,被告が「頭おかしいから」「ついていけないわ」等と返信してきたと主張するが,乙2のメッセージ履歴によれば,原告は,2日後の土曜日に出掛ける話をして被告に反対されたものであり,上記「頭おかしいから」等のコメントは,被告とのやり取りを経て静岡行きを断った原告に対し,その友人が上京してでも原告に会いたいと言ってきたことに対するコメントであり,原告が主張するような文脈で発せられた言葉ではないものと認められる。
イ 被告は,同年10月11日,原告がつわりのため部屋の片付け等の家事ができずにいたところ,原告の自宅には物が多すぎると文句を言い,「別居したい」等と言ったり,「妊娠で辛いときがあるのはわかるけど,辛くないときにやることちゃんとやってもらえないですか」と不満を述べたりした。(乙1・171頁)
また,被告は,同月18日,原告へのWhatsAppメッセージで,原告の勤務先が原告の妊娠に配慮しないことについて,「正直きちがい集団だとしか思えない」「ホントバカなんだろうね そんな人間が校長になれるとか 狂ってる」等と応答し,労働法規等についてインターネットで調べた結果を添えて,「妊婦なのに重い物を職場で持たされるのは完全なマタハラ」「訴えてもいいレベル」等と約3時間にわたって原告へのアドバイスを送信し(乙1・177~179頁),同月30日,原告がフルートの教え子の親からクレームを受けた際には,弁護士に相談に行く,証拠を残せ,等と原告に指示した上,その後に電話での会話を録音しなかった原告に対し,「証拠が大切といってる」「いうこと聞けないならもう助けられない」「バカなんですか?」「何が必要かほんとわかっていない人だね」「勝手にしろよほんと」と立て続けに送信したことがあった(乙1・192~196頁)。
ウ このように,被告は,自分が不満に感じる出来事があると,相手に対して徹底的に攻撃的な態度を示し,WhatsAppのメッセージでさえも,「頭おかしい」「バカ」「きちがい」「狂ってる」等,相手を罵倒する言葉を連発し,また,原告が言うことをきかないと,すぐに「好きにしろ」「勝手にしろ」「別居する」等,突き放すような言葉を発していたことが認められるところ,被告は,原告との日常会話においても,ラーメン店で被告の器に原告が箸をのばして一口食べたことについて「意地汚い」「品がなさすぎる」「バカにどんな話しても通じないから中井(被告が原告との同居前に居住していた被告所有のマンション)に帰る」等と言ったり,原告がDのDVDを買おうかと言ったことに対して「子供が生まれるのにそんなまたモノ増やす事言ってもうXさん死ねばいいと思います」と発言したりし,原告が家計の負担について被告と話し合おうとすると,腹を立て,「そっちが勝手にこんな高い良い家に住んで,こっちは中井を手放さないといけないのに,その上さらに援助してっておかしいでしょ,贅沢にもほどがある,そんなんだったら子供なんか作らなきゃいい」「離婚して犬連れて帰れよ」「もう犬捨ててこいよ」等と言い捨てたりもした。
また,被告は,同年12月11日,原告の教え子の発表会に行き,発表会の終了後,教え子の保護者である著名な女性芸能人に被告を紹介してもらうため観客席で原告を待っていたところ,原告が別の保護者と話していて被告の席に来るのが遅れ,同芸能人が直接被告に挨拶しに来る事態となったことについて,原告に恥をかかされたとして激怒し,「クズ」「死ね」「離婚して子供もおろせ」「何様なんだよ このクズ野郎」「マジで死んでくれないかな」「親の教育が悪すぎる」「こんな最低な女見たことない」等と原告を罵倒した。
エ 被告は,同年12月17日,誰が年賀状を準備するかを巡って原告と言い合い,「嫁に来たからにはY家のやり方を尊重してほしい」という趣旨の話をした。また,被告は,年賀状の準備作業中に,「3回も離婚して,親族の笑いものだ」という趣旨の話をし,原告が3回も離婚したのかと問うと,「いや,1回ですよ」と言い直した。
オ 被告は,原告の飼い犬であるシューの噛み癖を治すと称して,シューを段ボール箱に入れたり,シューの口に指を突っ込んだりする嫌悪刺激を度々加え,シューに噛まれることがあった。
カ 原告は,被告の機嫌がころころ変わり,上機嫌なときには優しく振る舞うものの,不機嫌になると手がつけられないほどに暴言を吐くことに戸惑い,LINEのトークで原告の母に状況を伝えていた。原告の母は,被告のモラルハラスメントないしDVを疑った。
原告は,平成30年1月9日の夕食時,大皿料理を食べる際に取り皿を使うべきかを巡って被告と口論になり,被告との会話を録音した。被告は,原告の発言をさえぎって自己の主張を大声でたたみかけ,原告が口論をやめようと言っても,少なくとも1時間以上にわたり,原告は常識を知らなすぎる等と言って,取り皿を巡る議論をやめなかった。
キ 被告は,同月28日夕方,体調が優れずに寝ていたが,原告が,インフルエンザに感染し胎児に影響が及ぶことを心配して,ホテルで外泊したいと言ったことに激怒し,「僕はインフルじゃない」「問題あるとしたら,あんたの日頃の行いだよ。部屋片付けねーとか,ちゃんときれいにしないとかさ。」等と原告を責めた挙げ句,子どもを堕ろすよう求め,なぜ堕ろさなければいけないのかと原告が問うと,「いらない。当たり前じゃん。やっていけないよ。あんたみたいなくそ人間と。自分のことしか考えてないんだよ。」と言い放った。原告が「子どものためじゃん」と反論すると,被告は,「子どものためじゃないね。俺は大丈夫っつってんだよ。それが信用できないんだったら,おまえ死ねよ,本当に。ふざけんなよ。こっちが大丈夫だっつってんのに,勝手にインフルエンザって決め付けて人を追い出すな。いや,本当に離婚届,明日持ってくるから書いてね。俺は書くから。勝手に1人で産めよ。勝手に1人で育てろよ。だったら。」と言い,原告宅を出て行った。
原告は,被告の物言いに恐怖を感じ,神戸市の父親に事情を話した。原告の父は,即日上京して原告宅に宿泊した。
ク 被告は,翌29日午後7時前にWhatsAppで「今から荷物取りに行く」と連絡した後,午後7時30分頃に帰宅したが,予告なく原告の父がいたことに腹を立て,原告の父に対し,自分は体調が悪いのに原告に無理やり出て行かされた,原告は親離れしていない,「家長」である自分がインフルエンザではないと言っているのに,原告は人の話を聞かない等とまくしたて,確実に離婚すると言い,原告の父が鍵を置いていくよう求めると,「置いていきますよ。荷物,全部送ってくださいよ,うちに。」と言って,原告宅を出て行った。
ケ 原告は,翌30日午前1時過ぎに,被告に対し,被告を大事に思っていないわけではないが,離婚,死ねという言葉がショックであった等と記したメッセージをWhatsAppで送信した。これに対し,被告は,午前2時前後の15分間に「はぁ パブロンは予防だとはっきり言いましたけど」から始まり,原告の対応はありえない,人間としておかしい等と批判するメッセージ8通を返信した。
原告が被告のメッセージに返信せずにいると,被告は,翌31日の午前6時前から9回にわたり,原告に対し,「理不尽」「常識が欠如しすぎ」「最低」「頭が悪すぎる」等と非難するメッセージを送信し,なぜ父親が来ていることを言わなかったのか説明するよう求めた。そして,原告が,荷物を送るようにとのメッセージに対してだけ,「はい」「荷物は送ります。土曜日の18時以降の便着で送ります」と返答すると,父親が来ていたことを言わなかった理由を説明しないことを責め,同日午後7時近くまで,繰り返し「ありえない」「ふざけすぎだろ」等のメッセージをWhatsAppで送り続けた。(甲3)
コ 被告は,同年2月1日,離婚届を原告に送付し,その旨をメール(Gmail)で連絡した。その際,被告は,さらに原告を「クズ」「卑怯者」等と罵倒し,批判する文言を繰り返した。(甲1)
(中略)
上記2(2)のとおり,被告は,原告との婚姻後,次第に,原告の人格を否定して被告の価値観を押し付け,被告に従わなければ徹底的に罵倒するような暴言を吐くようになり,その頻度や内容もエスカレートし,社会的に許容されるべき範囲を逸脱するものとなっていたことが認められるところ,これら一連の暴言がいわゆるモラルハラスメント行為に当たり,原告の人格権を侵害するものであることは明らかというべきである。
これに対し,被告は,暴言を吐いたことを否認し,自己の発言を正当化する主張をするが,これは,被告が自身の言葉が相手を傷付ける暴力的なものであるとの自覚を全く欠いているためであるに過ぎないものと解され,被告の主張は上記判断を左右しない。
(2) また,被告は,原告との交際開始時には,婚姻継続中であったことや前妻との間に子がいることを秘匿し,婚姻後においても,被告の婚姻歴について正確な説明をしていなかったことが認められるところ,これらの事実は,婚姻関係の前提となる相互の信頼関係を損なうものといえるから,上記モラルハラスメント行為ともあいまって,原告と被告との間の婚姻関係を破綻させる要因となったものと認められる。
(中略)
証拠(甲18ないし甲21(枝番を含む。))によれば,原告は,被告の一連のモラルハラスメント行為及び離婚により,強度の不安を感じ,不眠や抑うつ気分等,精神科の治療を要する状態に陥ったことが認められる。
このような原告の精神面の状況や,被告のモラルハラスメント行為自体の悪質性の程度,原告と被告との婚姻期間の長さ,原告が妊娠中の離婚を余儀なくされたこと等,一切の事情に鑑みれば,原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては,200万円と認めることが相当である。
また,同損害の回復に要するものとして相当因果関係が認められる弁護士費用の額は,20万円と認められる。
➢夫による悪質なモラハラ行為があったと認定し、200万円の慰謝料の支払いを命じた。
⑥ 夫が妻に対して乱暴な言動をとるなどした事例(東京地判平成31年3月20日)
【妻の主張】
被告(注:夫)は,原告(注:妻)との婚姻期間中,原告に対し,些細なことで怒り出し,乱暴な言動をしたり,原告の顔にライトを向けて質問したり,原告が繰り返し清掃しても,部屋を汚くし続けたり,人の好意に感謝することがなく,全て自分のおかげという態度をとったり,原告に車から飛び降りるよう求めたり,原告が友人と会うに際して事前及び事後に報告書を提出するよう求めたり,自分本位な夫婦生活を強要したり,大麻を発芽させようとしたり,原告に収入を渡さず,原告の貯金を使わせようとしたりするなど,種々のいわゆるモラルハラスメントを繰り返していた(以下,上記の被告の行為を併せて「本件各行為」という。)。
そのため,原告は,被告との婚姻関係を継続することが困難となり,婚姻関係が破綻するに至った。
【夫の主張】
否認ないし争う。
原告(注:妻)と被告(注:夫)との婚姻関係が破綻するに至ったのは,互いの性格の不一致が原因であり,被告に有責行為はない。
【裁判所の判断】
原告(注:妻)は,前記第2の3(1)アのとおり,被告(注:夫)の本件各行為により原告と被告との婚姻関係が破綻するに至った旨主張する。
そこで検討するに,前記1認定事実によれば,被告には,原告と被告の婚姻期間中における口論等の際,原告に対する不適切な言動が認められる一方で,原告にも,被告の立場について配慮に欠ける発言が認められるところである。そして,前記1認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係が破綻するに至ったのは,双方の性格の不一致や家族観の違いを基礎として,互いに相手の立場や状況に対する配慮に欠ける発言や不適切な言動があったために対立が深まっていたところ,性交渉に関する対立も加わり,別居について解消される見込みが立たない状態になっていたこと及びAと被告との対立が決定的なものとなったこともあいまって婚姻関係が破綻するに至ったのであって,婚姻関係の破綻について被告に有責行為があったとは認められない。
この点,原告は,被告において大麻を発芽させようとしていたことが原告に対するモラルハラスメントに当たる旨主張するが,被告が大麻を発芽させようとしていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。また,原告は,原告が繰り返し清掃しても,被告が部屋を汚い状態にし続けていた旨主張するが,原告と被告の居住していた部屋が汚い状態になったのは,原告及び被告の双方が適切に清掃しなかったのが原因であると認められ(甲6,7,乙1,17,原告本人,被告本人),原告の主張するように,原告が繰り返し清掃しても,被告が部屋を汚い状態にし続けていたためであると認めるに足りる証拠はない。そして,その余の本件各行為についても,前記1認定事実で認定した事実を除き,これらを的確に認めるに足りる証拠はない。
そうすると,婚姻関係の破綻について被告に有責行為があったとは認められない以上,被告の原告に対する不適切な言動があったとしても,被告に離婚慰謝料発生の基礎となるべき有責不法な行為があるということはできない。
したがって,原告の前記主張は採用することができない。
➢妻の主張するモラハラによる慰謝料を認めなかった。
⑦ 夫が妻に対して暴言を吐くなどした事例(東京地判平成29年11月6日)
【妻の主張】
原告(注:妻)と被告(注:夫)が離婚した原因は,被告の有責行為にある。すなわち,被告は,原告との婚姻期間中,原告に対し,心ない言動による精神的暴力及び威嚇行為といったモラルハラスメント(① 体調の悪い原告に対し,食事の用意を強要したり,「寝ていれば治るだろ。」と述べたこと,② いらいらして,突然,「お前ら,全員うるさい!」と怒鳴ったこと,③ 体調が悪いため被告の実家に行けないと述べた原告に対し,「おやじの写真の前に線香の1本もあげられないでどうする!」と怒鳴ったこと,④ 原告が「心臓が痛い。」と言うと,テレビを見たまま,「そうやって否定的な考えばかりしているからどんどん悪くなるんだよ。」と,非難めいた発言をしたこと等)を重ね,それによって原告が精神疾患を抱えるにようになった後も,更に追い打ちをかけてモラルハラスメントを重ねた。そして,被告が,平成23年3月6日,激高してリビングのテーブルにワイングラスを叩き付けて割ったことによって,原告の被告に対する拒否感,恐怖感及び嫌悪感が決定的なものとなり,翌日から別居となったものである。
原告は,被告の上記有責行為によって,被告と離婚するに至り,重度ストレス反応及び適応障害等と診断されるなど,多大な精神的苦痛を被ったものであり,離婚に伴う慰謝料の額は,300万円を下らない。
【夫の主張】
被告(注:夫)は,原告(注:妻)に対してモラルハラスメントをしておらず,平成23年3月6日の出来事も,原告が,飲酒中の被告に対し,それまでの数々の不満を突如として伝えてきたため,衝動的にワイングラスをテーブルに強く置いたところ,意図せず割れてしまったにすぎない。
したがって,原告と被告は,被告の有責行為によって離婚したものではないから,被告は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料支払義務を負わない。
【裁判所の判断】
(1) 原告(注:妻)は,原告と被告(注:夫)が離婚した原因は,被告の有責行為(度重なるモラルハラスメント)にある旨主張し,その旨記載した報告書(甲2)及び陳述書(甲21)を提出し,その旨供述する(原告本人)。
(2) そこで検討すると,原告は,被告と別居した後の平成23年3月30日,精神科医から,「被告との長期間にわたる葛藤があり,精神的なストレス状態となっている。」として,急性抑うつ反応と診断され(甲6),同年9月28日には,別の精神科医から,「被告から受けた長期複数回にわたる精神的暴力と威嚇行為が本疾患の成因である。」として,重度ストレス反応及び適応障害と診断されている(甲7,10)。
しかし,証拠(甲2ないし5,7,16,17,21,乙16,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,① 原告は,被告との婚姻当初,義母から孫を強く要望されることに精神的圧力を感じ,平成8年に妊娠したものの流産となったことで自分を責め,平成9年に精神科を受診したこと,② その後,原告の精神状態は安定したものの,平成16年に原告の母が肺炎の発症を繰り返した際,被告が原告の懇請にもかかわらず,原告の母を自宅に泊めることに同意しなかったことにつき,原告は,憤懣やるかたない気持ちを抱き続けたこと,③ 原告は,平成19年夏頃,体調不良が続いた際,被告が原告の体調を気遣ってくれないと感じて不満を募らせ,同年9月には呼吸困難となり,被告に救急車を呼んでもらったところ,心因性過換気症候群と診断されたこと,④ 原告は,その後も体調不良が続く中,義父の看病,義母への気遣い,経済面における被告への不満などが重なり,思い余って被告や義母に自己の考えを伝えると,かえって被告との間で衝突が生じ,被告に対する拒否感を強く感じるようになっていったこと,⑤ 原告は,平成23年2月,再び精神科を受診するようになり,同年3月6日,耐えられない気持ちから飲酒中の被告に対し,数々の不満を伝えたところ,口論となり,立腹した被告が手にしていたワイングラスをテーブルに強く置いた際,ワイングラスが割れたこと,⑥ 翌朝,原告は,子らを連れて本件マンションを出たことが認められる。
これらの事情を踏まえると,原告は,自身の繊細な性格が原因で,義母や被告の言動を過剰に感受して精神状態が不安定となり,心因性の体調不良を引き起こし,そのことから生ずる被告との衝突が更に原告の精神状態の不安定を招くという悪循環に陥っていたものとみるのが相当である。
原告がモラルハラスメントである旨主張する被告の言動は,原告に対する思いやりが不十分であったというべき部分があるとしても,一般的に婚姻関係の継続を困難にさせる程度のものであるとまではいい難く,本件全証拠によっても,上記診断書に記載されたような「長期複数回にわたる精神的暴力と威嚇行為」があったとまでは認められない。また,原告は,別居の前日である平成23年3月6日の出来事について,被告がワイングラスをテーブルに叩き付けて割った旨主張するが,上記のとおり,意図せず割れてしまったものと認められる。
(3) そうすると,上記経緯で別居状態となり,その後原告が被告との離婚を決意して,婚姻関係の修復が不可能となったことについては,原告の性格とそれに対する被告の対応の双方に原因があるというべきであり,原告が主張するようにその原因が被告の一方的な有責行為にあると認めることはできない。
したがって,被告は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料支払義務を負わない。
➢妻の主張する慰謝料を認めなかった。
⑧ 夫が妻を無視するなどした事例
【妻の主張】
被告(注:夫)は,婚姻当初から,思い通りにならないと,原告(注:妻)や長男を無視し,暴言暴力(物を投げつけるなど)に及んだ。被告は,長男が生まれてすぐに原告に働くことを強要し,自らは家事育児を手伝わないのに,掃除洗濯の方法などを事細かく指示し,原告のやり方が気に入らないと大声で怒鳴りつけるので,原告は,被告に話し合いを求めたが無視された。原告は,精神的に不安定となり,平成20年×月頃には激しいめまいと吐き気で救急搬送されたが,被告が入院を断ったため帰宅を余儀なくされ,体調不良の中家事をさせられた。また,被告は,長男が所在不明になった時にも原告に押しつけて放置した。これら被告の行為(モラルハラスメント)により,原告は,しばしば動悸,めまい,頭痛や吐き気に襲われ,現在,全般性不安障害と診断されている。原告は,被告とは別居しているが,被告は,別件婚費分担審判にもかかわらず婚姻費用を支払わない。以上からすれば,原告と被告との婚姻関係は破綻していて,原告の精神的苦痛を慰謝するには500万円を要する。
【夫の主張】
被告(注:夫)が物を叩いたり,原告(注:妻)と言い合いになったりしたことはあったが,言い過ぎた時などは謝っていたし,暴言や暴力はなく,むしろ原告から激しく怒鳴られたりした。仕事も原告が働きたがっていたので育児ストレスも解消できると賛成したにすぎず,家事の内容を事細かに指示,注意したことも,原告の入院を断ったこともない。また,被告は,揉め事が多い夫婦関係に悩み疲弊していたときに,長男が所在不明になったと聞いて,どうしたら良いか分からなくなっただけで,家族を大切に思っている。婚姻費用については,別居時に預金300万円位を原告が持ち出してしまい,被告には自宅ローンなどの返済もあることから,支払いが遅れている。なお,原告が全般性不安障害に陥ったのは,被告との関係からだけではない。被告は,従前,全般性不安障害についての理解が不足し,原告との接し方を間違えてきたことを深く反省している。今後は,その理解に一層務め,専門家の意見も踏まえながら夫婦共に治療に努力し(夫婦カウンセリングも必要かと思う),子供のためにも,何年もかかるかもしれないが,もう一度家族3人の生活を取り戻したい。本件別居は,被告が,原告の治療に少しでも役立てばと黙認しているにすぎず,原告と被告の婚姻関係は破綻していない。したがって,原告には慰謝料も当然発生しない。
【裁判所の判断】
婚姻の本質は,両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことであるところ,原告は,被告との接触のストレスから全般性不安障害となっていて,被告との同居は無理である旨述べる。しかし,原告が婚姻関係の破綻原因と主張する事実は,上記認定のとおり,その存在自体が認められないか,存在するとしても,いずれも,性格・考え方の違いや感情・言葉の行き違いに端を発するもので,被告のみが責を負うというものではない。そして,そのような隔たりを克服するためには,相互に相手を尊重し,異なる考え方であっても聞き,心情を汲む努力を重ね,相互理解を深めていくことが必要である。しかしながら,原告は,独り決めする傾向が見受けられ,被告が後から何か意見などをすると,自分の判断・行動を責められていると感情的・被害的になって受け入れず,被告に自身の精神状況について深刻に相談をすることもしないまま一方的に別居し,別居後も,頑に離婚を主張している。他方,被告も,独断的な傾向(とにかくやれば良いのだなど)があり,口論の末ではあったかもしれないが原告に大声を出すなど,原告の精神状態に配慮を欠いた相互理解の姿勢に乏しい言動があった。しかし,現在被告は,原告との修復を強く望み,従前の言動を真摯に反省し,全般性不安障害の理解のための努力も重ね,今後も原告の治療を優先に(夫婦カウンセリングも視野に入れている),段階を踏んだ時間をかけての関係改善を考えている。また,原告の,全般性不安障害の原因は,原告の生育歴や思考パターンによる部分も大きいものと考えられる。さらに,被告は,長男誕生時からその養育に関わり,現在も被告と長男の関係が良好に保たれているうえ,原告と被告の同居期間が約10年であるのに対して別居期間は約3年5か月と短い。
以上を総合考慮すると,原告と被告との婚姻関係は,原告の治療を優先に進めながらではあるが,原告と被告が相互理解の努力を真摯に続け,長男も含めた家族のあり方を熟慮することにより,未だ修復の可能性がないとはいえず,婚姻を継続し難い重大な事由があるとまでは認められない(ただし,被告が原告に対し,定められた婚姻費用を支払うべきことはいうまでもない。)。
➢婚姻関係が破綻していないことから、妻の主張する慰謝料を検討するまでもなく、その主張を排斥した。
3.まとめ
以上、8つの近時の裁判例を見てきましたが、そのうち慰謝料が認められたのは、1件(⑤東京地判令和元年9月10日)のみでした。
ここから分かるように、裁判実務においては、相当程度悪質なモラハラ行為を立証することができた場合でなければ慰謝料が認められておらず、モラハラ行為を理由に慰謝料が認められることには相応のハードルがあるといえます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の離婚弁護士が教える】風俗は「不貞行為」に当たるか
1.不貞行為という言葉が用いられる2つの場面
一般に、不貞行為とは、結婚しているにもかかわらず、配偶者以外の異性と肉体関係(性交渉)を持つことを意味すると考えられています。
しかし、性交渉はなくとも、「不貞行為」に当たるというような表現が用いられることがあります。
その一方で、性交渉がない限りは「不貞行為」には当たらないというような表現が用いられることもあり、不貞行為という言葉の用いられ方がやや不透明な側面があるように思われます。
この原因は、後述のとおり、不貞行為の意味を巡って二つの見解があることや、①不貞行為によって慰謝料が発生するか(不貞行為が民法709条にいう不法行為に該当するか)という論点と、②不貞行為が離婚事由に当たるか(民法770条1項1号にいう「不貞行為」の意味は何か)という論点を分けていないことにあります。
この点は、一般の方が誤解しがちな(場合によっては弁護士もあまり意識していない)ポイントですので、以下では、慰謝料の問題と離婚の問題を分けて解説をしていくこととします。
2.風俗店の利用は慰謝料発生事由たる不貞行為(不法行為)に当たるか
たとえば、夫が、妻に内緒で風俗店を利用し、性交渉は伴わないが性的サービスを受けたところ、それが妻にバレたというケースがあったとします。
この場合、妻は夫に対して、夫の風俗通いによって、婚姻関係が破綻したとして慰謝料請求ができるのでしょうか。
不貞行為という言葉を、厳密に性交渉があった場合に限定すると、性交渉を伴わない性的サービスを受けただけであれば、不貞行為には当たらない=慰謝料請求は認められないということになりそうです。
しかし、次のような裁判例があります。
【大津家判令和元年11月15日(判タ1498号45頁)】
原告(注:夫)は,被告(注:妻)から小遣い(原告によれば2か月に1回30万円,被告によれば月30万円)を貰い,ピンサロ,ファッションヘルス,キャバクラ等に行き,知人と女体盛を企画したり,風俗店の女性店員と食事に行く等した。
(中略)
複数の風俗店に通い,女体盛を企画し,風俗店の女性店員と食事に行く等したことが認められ,これが婚姻関係破綻の一因となったものと認められる。原告が支払うべき慰謝料としては100万円と認めるのが相当である。
この裁判例の控訴審は次のように判断しています。
【大阪高判令和 2年 9月 3日(判タ1498号42頁)】
被控訴人(注:夫)は,平成26年頃から,友人とともに複数の風俗店(ピンサロ,ファッションヘルス,キャバクラ等)に通うようになった。友人とのやり取りしているラインの中には女体盛りの企画があった。被控訴人は,風俗店の女性店員と食事に行ったりしていた。
(中略)
被控訴人と控訴人(注:妻)の婚姻関係が破綻した原因は被控訴人によるものが大きいというべきであり,被控訴人の控訴人に対する態度,風俗通いの頻度,未成年の子の存在,婚姻期間の長さ等,本件にあらわれた一切の事情を総合すると,被控訴人が控訴人に支払うべき慰謝料は120万円と認めるのが相当である。
この裁判例で認定されている事実を前提にすると、夫は風俗店に通っていたようですが、性交渉を伴う店ではないと推察されます。
そうすると、性交渉がなくとも風俗通いが婚姻関係破綻の原因になったということであれば、風俗通いが不法行為となって慰謝料請求が認められる可能性があります。
一方で次のように認定して、慰謝料を認めなかった裁判例もあります。
【東京地判令和3年11月29日(令和2年(ワ)26249)】
証拠(中略)によれば,被告(注:夫)が原告(注:妻)との同居中に,自己の財布の中に,風俗ヘルスのポイントカード,高級ソープランドの会員証,ホテルヘルスのスタンプカード及びピンクサロンの未使用の割引券を所持していたほか,居宅において,別の風俗店のメッセージカードをごみ袋に投棄していたこと,さらに,原告との別居後において,上記ピンクサロンの使用済み割引券を被告が居宅内に所持していたことが原告に発覚したことが認められる。この点,被告は,上記ポイントカード等は夫婦関係について相談した友人から冗談半分に渡されたものであり,被告が風俗店を利用したのは上記ピンクサロンの1回のみである旨を主張する。
上記ポイントカード等を所持していた理由についての被告の主張は,客観的な証拠に裏付けられたものではないが,かといって上記ポイントカード等を所持していたことから直ちに被告がこれらの風俗店を利用していたとまでは認めることができず,被告が自認する上記ピンクサロンの1回の利用を除いて,被告が風俗店を利用していたことを認めるに足りる他の証拠は存しない。
また,被告が利用した上記ピンクサロンが性的なサービスを提供する風俗店であることは被告本人も認めるところであるが(被告本人尋問),被告が実際に同ピンクサロンで性的サービスを受けたかどうか,受けたとしてそのサービスの内容がどのようなものであったかについては,これを認めるに足りる的確な証拠がない。
したがって,被告が風俗店を利用した事実は,上記の限度で認められるものの,これをもって被告に不貞行為があったとは認められず,婚姻を継続し難い重大な事由に当たるとも直ちには認めることができない。
これらの裁判例を見ると、夫が風俗店を利用したことがあるというだけで必ずしも慰謝料請求が認められるというわけではないといえそうです。
3.風俗店の利用は離婚事由たる不貞行為に当たるか
次は、風俗通いが原因で離婚が認められるかという問題です。
民法770条1項1号には「配偶者に不貞な行為があったとき」には、離婚の訴えを提起することができると定められています。
つまり、協議段階や調停段階において、一方配偶者が離婚を拒否したとしても、その配偶者に不貞行為があるということが立証できれば、裁判所が離婚を認めてくれるということになります。
では、風俗通いが「不貞行為」に当たるのでしょうか。
この点について、民法770条1項1号にいう「不貞行為」には、①貞操義務違反を疑わせるような性的不謹慎行為の一切を含み、姦通(性交関係)よりも広い概念であるとする見解(広義説)と、②配偶者以外の者と性的関係を結ぶことであるとする見解(狭義説)があります。
裁判実務はどう考えているかというと、判例(最判昭和48・11・15家月26・3・24)は、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうと判示しており、狭義説を採用しているといわれています(松原正明編著『人事訴訟の実務』新日本法規177頁)。
そうだとすれば、性的サービスを提供するものの性交渉は伴わない風俗店の利用は民法770条1項1号にいう「不貞行為」には当たらないといえそうです。
では、実際の裁判例はどうか見ていくこととします。
【横浜家判平成31年 3月27日(平成30年(家ホ)6)】
被告(注:夫)は,平成29年12月21日に1回デリヘルの性的サービスを受けているが,関係証拠(中略)に弁論の全趣旨を総合しても,それ以上に利用したことがあったとは認めるに足りない。
また,仮にあと数回の利用があったとしても,被告は発覚当初から原告(注:妻)に謝罪し(中略),今後利用しない旨約束していること(中略)からすると,この点のみをもって,離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない。
(中略)
以上によれば,原告の離婚請求には理由がなく,そうすると,離婚慰謝料の請求についても同じく理由がないこととなる
あくまで下級審の判断ではありますが、風俗店(デリヘル)で性的サービスを受けたことは、民法770条1項1号にいう不貞行為には当たらないと判断したものがあるということがわかります。
ただし、民法770条1項1号の不貞行為に当たらないとしても、同条項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして離婚が認められる可能性がありますから、その点は誤解のないようにしていただければと思います。
4.まとめ
以上をまとめると、①性的サービスを提供する風俗店を利用することが婚姻関係破綻の原因となったということであれば慰謝料請求が認められる可能性があるが、②離婚理由たる不貞行為(民法770条1項1号)には当たらないと判断される可能性がある(ただし、婚姻を継続し難い重大な事由と判断される可能性はある)ということになります。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の離婚弁護士が教える】完全解説 養育費の時効は何年?
1.はじめに
夫婦が離婚する際に、未成年の子どもがいる場合には養育費の取り決めをするのが一般的です。
しかし、現実的には取り決めの内容どおりに養育費が支払われないということも少なくありません。
こういった場合、養育費の支払を受ける側が何も対応せずに放っておくと、時効によって養育費を請求する権利が消滅していってしまいます。
では、いったい何年で養育費は時効によって消滅するのでしょうか?
この養育費と時効というテーマは、意外とサイトや文献でもきっちりと解説していることが少なく、しかも改正前民法を前提とした解説があったりして混乱しがちなところですので、できるだけわかりやすく解説してみたいと思います。
なお、この解説は基本的には改正民法を前提としていますが、改正民法が施行されたのは2020年4月1日です。
そのため、2020年3月31日までに養育費が決まったという場合には、改正前民法が適用されることになります(附則(平成二九年六月二日法律第四四号)10条1項、4項)ので、ご注意ください。
2.消滅時効の原則
民法には次のような規定があります。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
この民法166条1項1号を見ると、「権利を行使することができることを知った時から5年」で債権は時効消滅するということがわかります。
養育費の請求権も「債権」ですから、請求できることを知った時から5年で消滅してしまうということになります。
たとえば、毎月末日までに養育費を5万円払うという約束で2021年1月に離婚が成立したとします。
1月から5月までは養育費の支払いがありましたが、6月から支払いがストップしてしまいました。
この場合、支払期限である2021年6月30日の翌日である7月1日から時効期間がスタートすることになり、2026年6月末日の経過をもって、2021年6月分の養育費は消滅時効にかかるということになります。
そして、2021年7月分の養育費は2026年7月末日の経過をもって消滅時効にかかり、2021年8月分は2026年8月末日の経過をもって・・・というような形で毎月毎月消滅時効にかかっていくということになります。
ということで、養育費の時効期間は5年ということをまずはしっかりと押さえておきましょう。
3.調停や訴訟で養育費が決まった場合は?
調停や訴訟で養育費を決めれば時効期間が違うというような話を聞いたこともあるかもしれません。
では、実際どうなんでしょうか。
ここでも民法の条文を見てみましょう。
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
この条文には「10年」という時効期間が書かれていますね。
ここでいう「確定判決」というのは、訴訟で判決が出されて養育費が決まった場合と理解していただければと思います。
一方で、「確定判決と同一の効力を有するもの」ってなに?となるかもしれませんが、調停や審判(家事事件手続法268条1項)、訴訟上の和解(民事訴訟法267条)等を指すと考えていただければと思います。
ちなみに、公正証書の場合は、「確定判決と同一の効力を有するものにより確定したる権利には該当しない」とされています(東京高判昭和56年9月29日・東高民時報 32巻9号219頁)。
となると、民法169条1項によって、訴訟、調停、審判で養育費が決まった場合には時効期間は10年となるようにも思えます。
しかし、2項をよく読んでみてください。
「前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。」と書かれていますね。
先ほどの例と同じく、2021年1月に離婚調停が成立し、その調停の中で毎月の養育費を5万円とするという合意をしたとします。
そして、2021年6月分の養育費から支払いがストップしたとすると、養育費が確定した時点である2021年1月の時点では2021年6月分の養育費請求権は「弁済期の到来していない債権」となるわけです。
ということで、結局、訴訟、調停等で養育費が決まったとしても原則どおり5年の時効期間ということになります。
じゃあ169条1項でいう10年という消滅時効はどういう場合に適用されるの?というと、これは過去の未払いの養育費の支払いについて訴訟等で確定的に決められた場合には消滅時効の期間が10年となるということを意味します。
まだわかりにくいですね。
具体例を出しましょう。
先ほどの例で、2021年6月から2022年5月まで支払いがないということで、2022年6月に過去の未払の養育費を支払ってもらうべく訴えを提起したとします。
その結果、「2021年6月から2022年5月までの未払の養育費として、金60万円(5万円×12か月)を支払え」というような判決が出た場合、この60万円の請求権の時効期間は10年となるわけです。
4.定期金債権(民法168条)との関係
ここからは法律家向けの解説になるかもしれません。
さらに民法をしっかりと読むと、ふとした疑問がわいてきます。
第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
ここでいう「定期金の債権」というのは、終身年金のように定期に一定の金銭を給付させることを目的とする権利のことです。
とすると、養育費もまさに定期に一定の金銭を給付してもらうものですので、「定期金の債権」ということになります。
そうであれば民法168条1項1号によって、やっぱり消滅時効期間は10年なんじゃないの?という疑問がわいてきます。
そこで、条文をよく見てみると、①「定期金の債権」という言葉と、②「定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権」という言葉が使い分けられていることがわかります。
つまり、②を行使することができることを知った時から10年間行使しなかったときは、①が時効によって消滅するという条文構造になっています。
①のことを基本権、②のことを支分権と読んだりすることもあります。
ちなみに、改正前民法では②のことを定期給付債権と読んでいました。
養育費に引き付けて考えると、養育費という権利そのものが①(基本権)で、毎月発生する養育費を請求できる権利を②(支分権)と捉えてもいいと思います。
とすると、2021年6月分の養育費を2031年6月末日までほったらかしにしていると、「定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき」に該当し、その結果、養育費そのものが時効で消えてしまうということになるわけです。
先ほどの解説とあわせると、毎月発生する養育費の請求権は5年で時効にかかり、10年間放置しておくと養育費そのものが時効でなくなってしまうということになります。
5.養育費を時効にかからせないためにできることは?
養育費の時効期間は5年ということがわかりましたが、では請求する側は指をくわえて時効にかかるのを待つしか方法はないのでしょうか。
実は時効期間をリセットする方法があります。
これを時効の更新といいます。
具体的には、裁判などの法的手続での請求をしたり(民法147条)、強制執行などの手続をとったり(民法148条)、あるいは債務者に債務)の存在を承認させる(民法152条)といった方法を取る必要があります。
ですから、養育費が時効にかからないようにするためにはこういった手段を検討しなければなりません。
ご自身では対応が難しいケースもありますので、養育費の不払いでお悩みの場合はまずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【大阪の離婚弁護士が教える】成人年齢(18歳)引き下げと養育費の関係
1.はじめに
本日、令和4年4月1日より成人年齢が18歳となりました。
これまで実務的には養育費の支払いは20歳までと定められることが多かったのですが、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで養育費の支払いをいつまでにするのか?という悩みを持たれる方も少なくないと思います。
そこで、今回は成人年齢引き下げと養育費の関係について解説してみようと思います。
2.養育費の支払いは18歳まで?
上記のとおり、実務において、養育費は20歳までと定められることがよくありましたが、成人年齢が18歳になったことで養育費の支払終期も18歳とすべきなのでしょうか。
この点については、司法研修所編「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」に詳しく記載されています。
親は、未成熟子に対し、生活保持義務を負い、養育費はその実現のため支払われるものであるところ、一般的に、未成熟子の意義としては、単に子が現に経済的に自立していないという事実のみでは足りず、監護親及び非監護親の経済状況や子が経済的に自立していない理由等を含む、当該事案の一切の事情の下において、一般的、社会的にみて子が経済的自立を期待されていないこと(経済的に自立しないことを許容されていること)をも要すると解されている。(中略)健康被害の防止や青少年の保護の観点から定められた年齢要件については、年齢要件としての20歳は維持されていることからすれば、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、我が国の法体系において、20歳未満の者については、その未成熟な面を考慮し、保護の対象とすべきとする考え方が維持されていると評価することができよう。(中略)社会情勢をみても、一般的に、18歳となった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、一般的、社会的に18歳となった時点で子に経済的自立を期待すべき実情にもないから、養育費の終期を成年年齢の引き下げと連動させて一律に18歳とすべき事情は認め難い。(「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」54-55頁)
ということで、成人年齢が18歳に引き下げられても、自動的に養育費の支払終期も18歳にするというわけではないということがお分かりいただけたかと思います。
3.すでに養育費の合意をしている場合に影響はある?
では、すでに養育費の合意をしてしまっている場合はどうでしょうか。
たとえば「20歳まで養育費を支払う」というような書き方をしているのであれば問題ありませんが、「成人になるまで養育費を支払う」というような書き方で合意していれば、成人年齢の引き下げの影響を受けるような気もしますね。
具体例を出すと、子どもが10歳のときに「成人になるまで養育費を払う」というような合意して、その後令和4年4月1日時点で子どもが15歳だったとします。
とすると、この子どもの養育費の支払終期は、合意当時の20歳とするのか?それとも現在時点の18歳とするのか?という疑問がわいてくるわけです。
この問題についても上記の書籍に明確に書かれていますので、紹介してみることにします。
協議、家事調停及び和解等において、合意当時、成年年齢は20歳であったのであるから、合意した当事者の意思は、通常、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までとの趣旨であったと解される上、当事者は、予測される子の監護の状況、子に受けさせたい教育の内容、子が経済的に自立すると予測される時期、両親の学歴、両親の経済状況等の個別事情を考慮して、どれだけの期間養育費を支払う必要があるかを定めたと考えられる。そして、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、当事者が養育費の支払期間を合意する前提として考慮した監護の状況や教育内容等が変わるわけではなく、その後に成年年齢が変動したことを理由として養育費を支払う期間を短縮することは、一般に、当事者の意思に合致しないと考えられる。(中略)「成年」の意義は、改正法の成立又は施行後においても、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までと解するのが相当である。(「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」56頁)
したがって、「成人するまで」とか「成年に達するまで」というような合意をしていても、合意当時の成人年齢である20歳を養育費の支払終期と考えてよいということになります。
以上見てきたとおり、基本的には成人年齢が引き下げされたことによって、今後定めることになる養育費についても、これまで定めた養育費についても、何かしらの影響を受けることはないと考えていただいて問題ありません。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【大阪の離婚弁護士が教える】離婚の際に子どもが姓(苗字)を変えることを嫌がったらどうする?
1.はじめに
以前の記事で、離婚する際の子どもの姓と戸籍に関する手続について説明しました。
この際は、子どもと親権者が同じ戸籍に入ること、つまり、子どもと親権者が同じ姓を名乗るためにどうすればいいのかという観点で説明を行いました。
しかし、実際のところ、母親は旧姓に戻したいけど、子どもは今の姓のままがいいというようなケースもあります。
そこで、こういった場合にどうすればいいのかということを今回は解説したいと思います。
2.戸籍制度の概要
まずは戸籍制度の概要を改めて説明しておきます。
夫婦がいざ離婚するとなると、結婚の際に姓を改めた者(多くの場合は女性)は、結婚中の戸籍から除かれることになります。
そして、結婚の際に姓を改めた者は原則として旧姓に戻るけれども、離婚後3か月以内に役所で婚氏続称の手続をすれば、婚姻時の姓を名乗り続けることができるという制度になっています。
この点に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
3.子どもが姓が変わることを嫌がったらどうする?
上記のとおり、結婚の際に姓を改めた者は離婚する際には原則として旧姓に戻ることになります。
1つ例を出して考えてみましょう。
佐藤さんという男性と鈴木さんという女性が結婚して、夫婦ともに佐藤姓になって(夫が戸籍の筆頭者となって)、2人の間には子どもが1人いるというケースがあったとします。
この夫婦が離婚するとなったときに、妻が子どもの親権者となりました。
そして、妻はもはや佐藤姓を名乗りたくなかったので、婚氏続称の手続はしたくないと考えたとします。
ということは、妻は離婚にあたって鈴木姓に戻ることになります。
しかし、このことを子どもに説明したところ、子どもは断固として自分の姓が佐藤から鈴木に変わることを嫌がった場合、どうすればいいでしょうか?
ここで、とりうる選択肢は以下の3つが考えられます。
①子どもに何とか理解してもらうなどして、子どもと母親の姓を同じにする(上記例でいえば、2人とも鈴木姓にする)
②母親が子どもの考えに合わせて婚姻時の姓を名乗り続けることとして、子どもと母親の姓を同じにする(上記例でいえば、2人とも佐藤姓にする)
③子どもと母親の姓を別にする(上記例でいえば、子どもは佐藤姓、母親は鈴木姓にする)
それでは、一つずつ見ていきましょう。
まず、①の方法を取る場合は、裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで、役所で子どもを母親の戸籍に入籍させる手続を行うことになります。
次に、②の方法を取る場合は、役所で母親が婚氏続称の手続をとった後に裁判所で子の氏の変更許可を得て、さらに役所で子どもを母親の戸籍に入籍させる手続を行うことになります。
①②に関しては、詳しくはこちらの記事を参照ください。
今回のテーマは③です。
子どもは姓が変わるのが嫌、母親も婚姻時の姓を名乗るのは嫌ということで、双方の意見が折り合わず、親子で異なる性を名乗るという場合です。
理論的にはこのような方法もあり得ます。
先ほど説明したように、母親は婚氏続称の手続をとらなければ自動的に旧姓に戻ります(先ほどの例でいうと鈴木姓に戻ります)。
一方で、離婚した後に、子の氏の変更許可と子どもを母親の戸籍に入籍させる手続をしなければ、子どもは元の戸籍(父親を筆頭者とする戸籍)に残ったままになります。
そうすると、子どもは親が離婚したとしても姓が変わることはありません(先ほどの例でいうと、佐藤姓のままということです)。
こうすることで、たとえ母親が親権者であっても、母親と子どもが別の姓を名乗るということもあり得るということになります。
ただ、理論的にはこのような方法もあり得るものの、子どもと母親の姓が異なることによるデメリットもあると考えられます。
たとえば、学校や病院などで母親が保護者として書類にサインするなどの対応を求められることがありますが、子どもと母親の姓が違うとなると、子どもが周囲の目を気にしてしまったり、その都度事情の説明を求められたりする可能性があります。
また、子ども自身が、自分と母親の姓が違うということに違和感を覚えるということもあるかもしれません。
このような観点から、子どもと異なる姓を名乗る場合には、そのことによるデメリットやリスクも十分に理解したうえでされた方がよいと思います。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】離婚と公的医療保険(健康保険)にまつわるよくある質問
Q 健康保険とか国民健康保険とか色々あるようですが、違いがよくわかりません。国民健康保険の場合でも扶養するとかしないということはあるのですか?
A 公的医療保険の制度にはいくつか種類がありますが、代表的なものは国民健康保険制度と健康保険制度です。国民健康保険というのは・・・(続きを読む)
Q 離婚を前提に別居中なのですが、別居中に就職することになりました。自分の会社の健康保険に加入するので夫の扶養から外れたいのですが、どうしたらいいですか?ちなみに、夫が国民健康保険の場合はどうなりますか?
A 新たにご自身の会社の健康保険に加入する場合、離婚前であっても夫の扶養から外れることは可能です。この場合、夫には・・・(続きを読む)
Q 上記のケースで、一緒に暮らす子どもを自分(妻)の健康保険に加入させたいのですが、そのようなことはできますか?
A 夫と妻それぞれが健康保険に加入している場合、子どもをどちらの被扶養者とするのかについては基準があり、どのような基準かというと・・・(続きを読む)
Q 別居中に夫の扶養から一方的に外されてしまいました。私(妻)は無職なのですが、こんなことってあるんですか?
A たとえ妻が無職であったとしても、扶養から外れることになるというケースもあります。どのような場合にそのようなことになるかというと・・・(続きを読む)
Q 離婚することになったので、夫の扶養から外れることになりました。新たに健康保険に加入する場合と国民健康保険に加入する場合で何か違いはありますか?
A 健康保険から健康保険に加入する場合と健康保険から国民健康保険に加入する場合で、妻の資格喪失証明書が必要かどうかが変わってきます。具体的には・・・(続きを読む)
Q 離婚することになって、自分(妻)が子どもを引き取ることになりました。夫の扶養から抜けて自分の扶養に入れようと思うのですが、どうすればいいですか?
A 離婚の際に妻が子どもを引き取ることになったからといって自動的に子どもが夫の扶養から外れるわけではありません。妻の扶養に入れるためには・・・(続きを読む)
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】離婚する際の子どもの健康保険をどうするか?
1.はじめに
前回の記事で、離婚する際の妻の公的医療保険がどうなるのかということをご説明しました。
大きく分けると、①健保→健保、②健保→国保、③国保→健保、④国保→国保の4パターンがあります。
今回も、実務的に最も多いパターンである妻が子どもを引き取る場合を前提に、子どもの公的医療保険がどうなるのかということを説明したいと思います。
ここでも妻自身の場合と同様に、4パターンに分けて説明していくことにします。
別居中に子どもの公的医療保険資格を異動させる場合は、こちらをご覧ください。
2.夫の健康保険の扶養に入っていた場合
離婚する前に子どもが夫の健康保険の被扶養者であった場合は、妻が子どもを引き取ったからといって、自動的に子どもが被扶養者の資格を喪失するわけではありません。
ここは妻自身の場合と子どもの場合とで異なる点ですね。
というのも、健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者により生計を維持していることが要件となっていて、同一世帯に属する(住居及び家計を同じくする)ことは必ずしも要件とはならないためです。
もっとも、実務的には離婚にあたって妻が子どもを引き取るケースにおいては、子どもを夫の健康保険の被扶養者から外すケースが多いように思います。
これは、離婚後も子どもが夫の健康保険の被扶養者となると、離婚後も元夫とのやり取りが発生してしまうなどが理由にあるのではないかと思います。
①健康保険から健康保険のパターン
離婚後、子どもを夫の健康保険の被扶養者から外して、妻の健康保険に加入させるためには、妻の健康保険の組合に対して子どもの異動届を提出する必要があります。
この際、夫の被扶養者から外れたということを証明する資格喪失証明書が求められることがあります。
この点は、妻自身が健康保険に加入する場合とは異なります(妻が夫の健康保険から自分の健康保険に加入するパターンの場合には妻の資格喪失証明書は不要)。
これは、前述のとおり、子どもの場合には、父母が離婚したからといって直ちに扶養から抜けるわけではないため、重複加入や加入漏れを防ぐためにも資格を喪失したことを確認しておこうという目的によるもののようです。
子どもが夫の被扶養者から外れたことを証明する資格喪失証明書が必要な場合には、夫にその旨を説明して夫の会社を通じて資格喪失証明書を発行してもらいましょう。
②健康保険から国民健康保険のパターン
離婚後、子どもを夫の健康保険の被扶養者から外して、妻の国民健康保険に加入させる場合、子どもの異動届を役所に提出する必要があります。
この場合には、子どもの資格喪失証明書が必要となりますので、上記①と同様、夫に資格喪失証明書の発行手続きをお願いすることになります。
ちなみに、①、②のいずれの場合においても、夫が資格喪失証明書の発行に協力してくれないなどの場合には、子どもを加入させようと思っている保険の保険者(健康保険組合、市町村役場等)にその旨相談してみてください。
3.夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合
離婚によって、妻が子どもを引取り、子どもが妻の世帯に属するときには、子どもは夫の世帯から外れることになります。
子どもが離婚前に夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者であった場合、夫の世帯から外れることによって、夫を世帯主とする国民健康保険からも外れることになります。
③国民健康保険から健康保険のパターン
この場合は基本的には上記①と同じです。
妻の加入している健康保険に子どもを加入させるために必要な手続を行っていただければと思います。
④国民健康保険から国民健康保険のパターン
離婚後、妻が自分を世帯主とする国民健康保険に加入した場合には、子どもも同一世帯に属するのであれば、同じ国民健康保険の被保険者となります。
説明は以上のとおりですが、必要な書類や細かい手続きの確認や不明点等は、各保険者に詳細を確認していただければと思います。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】離婚する際の妻の健康保険をどうするか?
1.はじめに
これまで別居中の公的医療保険について解説をしてきましたが、実務的には別居中よりもむしろ離婚するタイミングで手続をすることの方が多いということは何度か説明させていただいていたとおりです。
そこで、今回は離婚するタイミングで妻の公的医療保険をどうするのかというテーマで解説をしてみたいと思います。
よくあるケースとして、離婚するまでは夫の扶養に入っていて、離婚するタイミングで扶養から外れるというパターンです。
あるいは、夫が自営業者のケースなどは、離婚するまで夫を世帯主とする国民健康保険に加入していたけど、離婚することになったのでどうしたらいいかわからないというようなケースもあります。
以下では4つのパターンに分けて説明していくことにします。
2.夫の健康保険の扶養に入っていた場合
①健康保険から健康保険のパターン
離婚することで被扶養者の資格を失うことになります(健康保険法3条7項1号)。
健康保険から健康保険のパターンというのは、離婚によって夫を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を喪失して、妻が新たに勤務先の健康保険に加入するという場合です。
これは、別居中の話と同じで、妻が勤務先の健康保険の被保険者資格の要件を満たしさえすれば問題なく新たな健康保険に加入することができるということになります。
この場合、夫の方から資格喪失証明書をもらう必要はありません(ただし、子どもがいる場合は子どもの分の資格喪失証明書が必要になることがあります)。
②健康保険から国民健康保険のパターン
夫の扶養から外れて、国民健康保険に加入するというパターンもあります。
国民健康保険に加入する場合、他の保険に加入していないということが前提になりますので、妻が夫の健康保険の被扶養者の資格を喪失したことを証明する資格喪失証明書が必要となります。
そのため、離婚にあたって、夫に会社で資格喪失証明書の発行の手続をしてもらって、妻に交付してもらうようにお願いしておきましょう。
万が一、夫が資格喪失証明書を渡してくれないという場合には、役所に相談してみるほかないと思います。
これは、国民健康保険に加入するために資格喪失証明書が必要であるかどうかは法律で定められているわけではなく、市町村の取り扱いに委ねられているためです。
3.夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合
③国民健康保険から健康保険のパターン
この場合は上記①と同じです。
妻が勤務先の健康保険の被保険者資格の要件を満たしさえすれば問題なく新たな健康保険に加入することができるということになります。
妻自身の資格喪失証明書が必要ないという点も同様です。
④国民健康保険から国民健康保険のパターン
夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失した後、新たに国民健康保険に加入する場合には、妻自身を世帯主として資格取得の届出を市町村に提出することになります(国民健康保険法9条1項)。
あわせて、役所で保険証の交付のための手続を行うことになります(同法9条2項)。
この場合、国民健康保険間での異動であって資格の喪失が明らかであるため、資格喪失証明書は必要ありません。
続きを読む
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】別居中に扶養から外れる(外される)場合とは?
1.はじめに
前回までの記事では、妻自ら働くようになって、別居中に夫の扶養から外れることになった場合を想定して説明してきました。
つまり、妻側から積極的に扶養から外れる場合の説明でした。
これに対して、一方的に扶養から外されてしまったあるいは扶養から外れざるを得ないというようなケースもないわけではありません。
そこで、今回はどのような場合に別居中に扶養から外れることになるのかということについて考えてみたいと思います。
2.別居中に扶養から外れるのはどのような場合?
これまで何度か書いていますが、離婚時に扶養から外れるというのが実務的には多いパターンだと思います。
これは、離婚することで被扶養者の資格を失うことが明確になる(健康保険法3条7項1号)という理由によるものではないかと考えられます。
つまり、離婚を前提に別居していたとしても、離婚するまでの間は扶養に入り続けているケースが多いということですね。
もっとも、別居中に扶養から外れるパターンもあるということは以前の記事で説明したとおりです。
これは主に妻が別居中に会社勤めをするようになって、自身の会社の健康保険に加入する場面を想定したものでした。
しかし、たとえ妻が無職であったとしても、扶養から外れることになるというケースもあります。
そもそも、被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
そして、被保険者と同一世帯でない場合(別居している場合)の被扶養者の認定基準は以下のとおりです(厚生省通知昭52.4.6保発9号)。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
すなわち、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、別居中であっても被扶養者の資格があるということになります。
反対に言うと、別居中の妻が無職の場合などで年間収入が130万円未満であっても被保険者(夫)からの援助(婚姻費用等の支払)がない、あるいは援助があったとしても妻の年間収入の方が援助額よりも多いというようなケースでは、妻には被扶養者の資格がなくなるということになると考えられます。
たとえば、妻が有責配偶者のケースであれば、妻自身の分の婚姻費用(生活費)の請求は通常認められませんので、夫婦間に未成熟の子どもがいないような場合には、被保険者からの援助(婚姻費用等の支払)が全くないということも十分考えられます。
このような事情によって、被扶養者の資格要件を満たさないという場合には、別居中で離婚する前であっても扶養から外れるということがありえます。
なお、国保組合のように扶養認定という概念のない組合の場合には、別世帯(別居)になった時点で、家族被保険者ではなくなるという取り扱いとなることもあるようですし、組合よっては別居したという事実によって扶養から外れざるを得ないという場合もあるようです。
そのため、ご自身がどのような組合に加入していて、その組合の規定がどのようになっているのかという点は少なくとも確認しておいた方がよいと思います。
3.別居中に扶養から外れることになった場合どうするのか?
上記2で説明したような事情に該当して、別居中に扶養から外れなければならないということになった場合には、①国民健康保険に加入するか、②その時点で会社勤めをしているということで健康保険の加入資格があるのであれば、自身の勤める会社の健康保険組合に加入するという選択肢が考えられます。
少なくとも①の場合は資格喪失証明書を夫からもらう必要がありますが、その他に扶養から外れるにあたって必要な書類や細かい手続きは組合によって異なることもあるようですので、不明点等は、各組合に詳細を確認していただければと思います。
続きを読む
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】別居中の子どもの健康保険はどうなる?
1.はじめに
前回の記事で、別居中の妻の公的医療保険について解説をしました。
今回は、別居中の子どもの公的医療保険について考えてみましょう。
必ずしも別居中に子どもの公的医療保険を異動させなければならないという意味ではありませんので、そこはご注意ください。
2.妻の健康保険に子どもを加入させる場合
前回の記事で説明したとおり、妻が働く会社で健康保険の被保険者資格の要件を満たせば、妻は自身の健康保険に加入することになります。
このような場合に、一緒に暮らす子どもを妻の健康保険に加入させる(妻の扶養に入れる)ことができるのでしょうか?
夫と妻それぞれが健康保険に加入している場合、子どもをどちらの被扶養者とするのかについては次のような基準があります。
1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、
現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同
じ。)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶
養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者
とする。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者
とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)
の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し
支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として
認定しないことはできない。
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。
当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報
酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険
者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑
義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間
及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの
者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出さ
れた日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持す
る者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が
覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない
この基準は昭和60年の基準を廃止して、令和3年8月1日から新たに適用されることになったものです(保保発0430第2号、保国発0430第1号)。
色々と書かれていますが、ポイントとなる部分はというと・・・
➢被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入 、 将来の収入 等 から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
➢夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
基本的には夫婦のうち収入の多い方の扶養に入れるということになるわけですね。
ということで、原則として、妻の方が夫よりも収入が多い場合には、子どもは妻の扶養に入れるということになります。
もっとも、妻の方が収入が少ない場合であっても、長期の別居で世帯を別にするなどの具体的扶養の状況を保険者(健康保険組合など)に話して、子どもを妻の健康保険の被扶養者となれるように交渉してみるという手段もあるとの指摘もあります(『離婚をめぐる相談100問100答〔第二次改訂版〕』256頁)。
実際に当事務所が扱ったケースでも妻の方が夫よりも収入が少なかったものの、別居中に子どもを妻の扶養に入れたというケースがありました。
ちなみに、妻の健康保険に子どもを加入させるにあたって、子どもが夫の健康保険の被扶養者から外れたことを証明する資格喪失証明書を求められることがありますので、具体的な手続きや必要書類については、妻自身の加入する健康保険組合に尋ねてみてください。
3.妻の国民健康保険に子どもを加入させる場合
妻を世帯主とする国民健康保険に子どもを加入させるのは、妻と子どもの世帯が同一であれば可能です。
したがって、妻と子どもの住民票所在地が同一であれば、妻の国民健康保険に子どもを加入させることができます。
ちなみに、もともと子どもが夫の健康保険の被扶養者であった場合には、子どもを妻の国民健康保険に加入させるにあたって、夫の健康保険組合発行の資格喪失証明書が必要となります。
4.夫の協力が得られない場合
上記のとおり、子どもを妻の扶養に入れたり、妻の国民健康保険に加入させるにあたって、子どもの資格喪失証明書が必要になる場合があり、そのようなときには夫側に書類を用意してもらうことになります。
しかし、夫がこれに協力してくれないという場合にどのような取扱いをするのかについては、各保険者(健康保険組合等)の運用に委ねられています。
そのため、夫の協力をどうしても得られないというような場合には、保険者に相談してみるといいと思います。
以上が別居中の子どもの公的医療保険についての説明でした。
前回の記事でも書きましたが、すべてのケースにおいて別居中に妻や子どもの公的医療保険を必ず異動させなければならないというわけではありませんので、その点はご注意ください。
むしろ離婚したタイミングで公的医療保険の異動の手続をするというケースの方が多いと思われますので、そこは誤解のないようにしてください。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】別居中の妻の健康保険はどうなる?
1.はじめに
前回の記事で公的医療保険の概要についてご説明いたしました。
今回は、前回の記事を読んでいただいているということを前提に説明させていただきます。
国民健康保険と健康保険の違いがよく分からないという方は、本記事を読む前に前回の記事をぜひご覧ください。
さて、離婚と公的医療保険の問題ですが、実務的には離婚した後に妻や子どもの公的医療保険の変更などの手続をすることが多いように思います。
もっとも、離婚する前の段階、たとえば別居中の段階で夫の扶養から外れたいというような方もおられます。
そこで、今回は別居中に公的医療保険の手続を行うためにはどうしたらいいのかということを説明してみようと思います。
2.夫が国民健康保険に加入している場合
同居中は夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者だったけど、別居をきっかけに会社勤めを始めるようになったという方もおられます。
こういったケースでは、医療保険はどうしたらいいのでしょうか。
まず、前回の記事で説明したとおり、国民健康保険の場合は、扶養という概念がありませんでしたね。
そして、妻が仕事を始めたからといって、夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者という立場に変更が生じるわけではありません。
妻が働くようになった会社で、健康保険の被保険者資格の要件を満たすということになれば、夫に国民健康保険の被保険者から妻の名前を抹消するための抹消届を出してもらう必要があります。
3.夫の健康保険の扶養に入っている場合
上記2と同じようなケースとして、同居中は妻が夫の健康保険の被扶養者になっていたけど、別居したことをきっかけにバリバリ仕事を初めて扶養から外れたいというケースがあります。
この場合も妻が会社で健康保険の被保険者資格の要件を満たすということが前提になってきます。
そして、妻の被保険者資格が認定されて保険証が作成されれば、夫は自分の健康保険の被扶養者から妻の名前を抹消するための抹消届を出す必要があります。
4.まとめ
以上のとおり、別居中であっても、夫を世帯主とする国民健康保険から抜けて自分自身の健康保険に加入したり、夫の扶養から抜けて自分自身の健康保険に加入したりする場合があります。
ただ、冒頭でも説明しましたが、実際は離婚後に医療保険の変更の手続を行うことが多く、いかなる場合も別居中に手続をしなければならないという意味ではありませんので、その点はご注意ください。
あくまで別居中に医療保険の変更手続きができる場合があるということですね。
次回は、妻自身ではなく子どもの医療保険をどうするのかという問題を考えてみたいと思います。
続きを読む
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】公的医療保険制度の概要
1.はじめに
離婚を考えるときに、自分や子どもの保険証って一体どうなるんだろう?などの疑問を持たれる方はたくさんおられます。
そこで、これから何回かに分けて、離婚に関連する公的医療保険制度のことについて解説してみたいと思います。
今回はまずは医療保険制度の概要から説明してみることにします。
2.医療保険制度の概要
そもそも、すべての国民は公的な医療保険に加入することになっていますので、赤ちゃんから高齢者まで必ず何らかの医療保険に加入しています。
そして、公的な医療保険と一口に言っても、国民健康保険制度や健康保険制度、さらには国家公務員を対象とする医療保険制度や地方公務員を対象とする医療保険制度、後期高齢者医療制度など複数の種類が存在します。
以下では、代表的な国民健康保険と健康保険について、それぞれ説明をしてみることにします。
3.国民健康保険の場合
国民健康保険というのは、他の医療保険制度に加入していない人を対象とする医療保険です。
主に自営業者(個人事業主)の医療保険と考えていただいてもいいかと思います。
この国民健康保険の場合、扶養という概念がないので、被保険者の資格は個人単位で定められています。
つまり、夫、妻、子ども各々が被保険者ということになります。
ただ、「世帯」という概念はあり、各種の届出義務者を世帯主にすること(国民健康保険法9条1項、同法施行規則2条~5条の4)、世帯主が全員の保険証の交付を求めること(国民健康保険法9条2項)、保険料の納付義務者を世帯主にすること(国民健康保険法76条1項)が定められています。
また、国民健康保険の保険料は原則として被保険者が全額負担することになります。
4.健康保険の場合
健康保険というのは、事業主に使用される者を被保険者とし、配偶者(被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの)、子ども等は、被扶養者となります(健康保険法1条、3条)。
主に会社員のための医療保険と考えていただいてもよいと思います。
そして、被扶養者に関する各種の届出は、事業主を通じて被保険者がこれを行うことになります(健康保険法施行規則38条~41条)。
この健康保険の保険料は、事業主と被保険者が折半して負担することになります。
5.一部負担金
病院で治療を受けた場合に患者が窓口で払う医療費の一部負担金の割合は、国民健康保険、健康保険のいずれも、本人・家族(3歳以上)は3割となっています。
3歳未満の患者負担割合は2割で、後期高齢者医療の場合は1割となります(ただし現役並み所得者は3割)。
この点は、国民健康保険と健康保険で特に違いはないということになります。
6.まとめ
このように、公的な医療保険といってもいくつか種類があり、国民健康保険と健康保険も言葉はよく似ていますが、別の制度であるということをお分かりいただけたかと思います。
次回以降では、離婚問題と絡めて医療保険のことについて記事を書いてみたいと思います。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】離婚後の子どもの氏と戸籍に関する手続
1.はじめに
前回の記事で、離婚後の氏のことと戸籍のことについて説明しました。
では、子どもの氏と戸籍はどうなるのでしょうか?
ここでは説明の便宜上、夫が戸籍の筆頭者となっていて、離婚にあたって妻が子の親権者になるという最も一般的なケースを想定して説明することとします。
現状では男性側の氏を名乗る夫婦が多数派ですが、そのような夫婦が離婚した場合、女性側は原則として自動的に旧姓に戻ることになりますが、婚氏続称の手続をとれば結婚時の氏を名乗り続けることができるということは前回の記事で説明しました。
そして、夫側の氏を名乗っている夫婦が離婚する際に、妻が未成年の子の親権者となった場合、妻だけが戸籍から抜ける形になって、子どもは自動的に妻(母親)の戸籍に入るわけではないということも前回の記事のとおりです。
つまり、何も手続をしなければ子どもはそれまでの戸籍に残ったままで、母と子は別々の戸籍になるということです。
これは妻が婚氏続称の手続をとっていたとしても変わりません。
婚氏続称の手続をするということは、妻の氏はそれまでと変わらないということですから、妻(母親)と子どもは同じ氏ということになりますが、戸籍は別々ということですね。
しかも、ちょっとややこしいのですが、母が婚氏続称の手続をしたことで、母の氏と子の氏がたとえ同じであったとしても、あくまで表記上は同じというだけで法律上の氏は母と子で異なっているのです。
この部分については、一応最後に説明を行いますが、興味のない方は読み飛ばしていただいて大丈夫です。
以上のことから、婚氏続称の手続をしているか否かにかかわらず、子を母の戸籍に入籍させるためには以下の手続が必要になってきます。
2.子どもの戸籍を移すための方法
では、子どもの戸籍を妻(母親)の戸籍に移すためにはどうしたらいいのでしょうか?
前回の記事では車のイメージで説明しましたが、母親が乗っている車に子どもを乗せるためにはどうしたらいいのかということですね。
子どもと母親が同じ戸籍に入るためには、子の氏の変更という手続が必要になります(民法791条、戸籍法98条1項)。
子の氏の変更の手続をするための手順は大きく分けて2つです。
①家庭裁判所と②役所で、それぞれ手続が必要となります。
一つずつ説明していきましょう。
まずは家庭裁判所で子の氏の変更許可の審判の申立てを行って、許可を得る必要があります(家事事件手続法160条)。
審判の申立てとか許可が必要と聞くと、なんだか大変そうとか許可がおりなかったらどうしようと思われるかもしれません。
ですが、裁判所のウェブサイトに書かれているとおりに必要書類を揃えて申立てをすれば、基本的にはあっさり許可がおりますので、心配する必要はありません。
何かわからないことがあれば家庭裁判所に聞けば大丈夫です。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可がでたあとは、役所で母の戸籍に入籍する旨の入籍届を出します(戸籍法98条1項)。
こうすることによって、子どもと母親は同一戸籍に入って同じ氏を名乗ることができるということになります。
ちなみに、この入籍届が受理されることで初めて効力が発生しますので、家庭裁判所の許可だけを取って安心して入籍届を忘れてしまっては何の意味もありません。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後はすぐに役所で手続をするということを忘れずにしていただきたいと思います。
3.婚氏続称の手続をしても子どもと氏が違うというのはどういうこと?
先ほど、母が婚氏続称の手続をしたことで、母の氏と子の氏がたとえ同じであったとしても、あくまで表記上は同じというだけで法律上の氏は母と子で異なっていると説明しました。
ここをもう少しだけ詳しく説明しておきます。
たとえば、佐藤さんという男性と鈴木さんという女性が結婚して、この夫婦の姓を佐藤としたとします。
この場合、妻の姓は当然ながら夫の姓である佐藤になります(民法750条)。
そして、この夫婦が離婚することになった場合、妻は旧姓である鈴木姓に戻ることになります(民法767条1項)。
ただし、離婚後3か月以内に婚氏続称の手続をすれば、佐藤姓を名乗り続けることができます(民法767条2項、戸籍法77条の2)。
ここまでは前回の記事でも説明しました。
ただ、婚氏続称の手続をするというのは、あくまで妻が結婚時の姓である佐藤姓を名乗り続けることが「できる」という意味しかなくて、法律上の姓も結婚時の姓のままであり続けるというわけではないんです。
この辺で分からなくなってきたかもしれませんが、民法767条を見てみましょう。
第767条
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
民法767条1項には「離婚によって婚姻前の氏に復する」と書かれていますね。
なお、「協議上の離婚」とありますが、この規定は裁判上の離婚にも準用されています(民法771条)。
そのため、協議離婚であれ裁判所を介した離婚であれ、離婚することによって民法上は問答無用で旧姓に戻るということです。
ただ、第2項に「届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」とあることから、婚氏続称の手続をすれば、呼称上の姓を結婚時の姓とすることができるということになります。
ということで、いくら婚氏続称の手続をしたとしても、あくまで呼称上の姓を結婚時のままとするという意味しかなく、民法上の姓は旧姓に戻るということになります。
先ほどの例で言うと、妻が婚氏続称の手続をした場合、妻の呼称上の姓は「佐藤」ですが、民法上の姓は「鈴木」ということです。
そのため、母と子の民法上の氏が異なるので、婚氏続称の手続をするしないにかかわらず、子どもを自分の戸籍に入れるためには、子の氏の変更の手続が必要になるというわけです。
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】離婚後の戸籍や苗字はどうなる?
1.はじめに
まず簡単に戸籍制度の説明をしておきたいと思います。
日本においては、一つの戸籍に在籍できるのは、①夫婦と②その夫婦と氏を同じくする子どもとされています(戸籍法6条本文)。
つまり、親、自分、子みたいな形で親子三世代が一つの戸籍に在籍することはできません。
まずはこの点を大前提として押さえておきましょう。
結婚をする際、夫婦は夫か妻かいずれかの氏を称することになります(民法750条)。
そして、婚姻届に夫か妻のどちらかの氏を記載して提出します(戸籍法74条1号)。
その結果、この夫婦のための一つの戸籍が作られることになります(戸籍法16条)。
さらに、この夫婦に子ども(嫡出子)ができると、その子は父母の氏を称して(民法790条1項本文)、親と同じ戸籍に入ります。
ここまでの話は、法律の存在や条文の内容は知らなくとも、多くの方が感覚的にわかることだと思います。
たとえば、佐藤さん(男性)と鈴木さん(女性)が結婚して、夫婦ともに佐藤姓になって、その後に生まれた子も佐藤姓になるという、いわば当たり前のことを法律の条文に基づいて説明をしたにすぎません。
本題はここからです。
2.離婚するとどうなるか?~原則~
上記のとおり、結婚するときには、夫か妻のいずれかの氏に決めて戸籍を編製することになるわけですが、いざ離婚するとなると結婚の際に氏を改めた者は、結婚中の戸籍から除かれることになります。
この戸籍の話をするときには、車に一緒に乗っているイメージを持つと分かりやすいかもしれません。
※ここでは夫が筆頭者となっているケースを想定して説明することにします。
夫婦と子どもが一緒の車に乗っていたところ、離婚すると、まず妻だけ車から降ろされてしまうというイメージですね。
車から降ろされてしまった人が次にどの車に乗ればいいのかというと、①結婚前に乗っていた車に乗るか(結婚前の戸籍に入りなおすか)、②新しい車に乗るか(新戸籍を編製するか)の二択ということになります。
この点、原則は、結婚前の戸籍に入りなおすことになります(戸籍法19条1項本文)。
また、苗字については、結婚前の氏に戻ります(民法767条1項)。
先ほどの例で言うと、離婚に伴って、妻の氏は旧姓の鈴木に戻って、妻は結婚前の戸籍に入りなおすというのが原則的な取扱いということですね。
3.新戸籍が編製される場合
離婚した際には、結婚前の戸籍に入り直すのが原則と書きましたが、新たな戸籍を編製するということもよくあり、希望さえすれば新戸籍を編製してもらうことができます(戸籍法19条1項ただし書)。
たとえば、先ほどの例で、夫婦に子どもがいて、離婚の際に妻がその子の親権者になったとします。
この場合、妻が結婚前の戸籍、たとえば自分の両親の戸籍に入り直したうえで、さらに子どももその戸籍に入れたいと考えたとします。
しかし、冒頭で説明したとおり、三世代にわたる戸籍はできませんので、子どもを自分の戸籍に入れようと思うと、新たな戸籍を作る必要があるということになります。
車のイメージで言うと、離婚すると妻だけ車から降ろされてしまうけど、両親・自分(妻)・子どもが一緒の車には乗れないので、子どもを一緒の車に乗せるためには、新しい車でないとダメということですね。
そのため、子どもを自分の戸籍に入れようとするのであれば、新戸籍を編製し、その戸籍に子どもを入れるという形になります。
また、戻るべき戸籍がないような場合も新戸籍が編製されることになります。
たとえば、先ほどの例でいうと、妻の両親がいずれも死亡していて除籍になっているような場合です。
このような場合には、妻が結婚前の戸籍に戻ろうと思っても、戻るべき戸籍がないということになり、新たな戸籍を編製するほかないということです。
このように、離婚する際に、結婚前の戸籍に戻るのではなく、新戸籍を編製することもよくあるというわけです。
4.結婚時の氏を名乗り続ける場合
結婚の際に氏を変更した者は、離婚することで旧姓に戻ると説明しました。
もっとも、離婚後も婚姻中の氏を使用し続けたいという場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることによって、結婚していたときの氏を名乗り続けることができます(民法767条2項、戸籍法77条の2)。
先ほどのケースでいうと、旧姓が鈴木であった妻は離婚後3か月以内に婚氏続称の届出をすれば、離婚後も佐藤姓を名乗り続けることができるということです。
婚氏続称の届出の手続をどこで行うのかというと、届出人の本籍地、または所在地の役所で手続をすることになります。
結婚時の氏を使用したい場合には、離婚後3か月以内に婚氏続称の届出をしなければなりませんので、お忘れないようにご注意ください。
また、この場合、離婚届と同時に婚氏続称の届出を役所に出すことができますので、同時に出してもいいと思います。
続きを読む
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【離婚】年金分割に関するよくある質問
Q 年金分割とはどのような制度ですか?
A 年金分割は、一方が受け取る年金額の2分の1をもらえる制度だと認識しておられる方がおられますが、これは誤解です。どのような制度かというと・・・(続きを読む)
Q 年金分割には合意分割と3号分割という2種類があると聞きました。これはどのような違いがあるのですか?
A 合意分割というのは、夫婦が年金分割を行うことと按分割合を何パーセントにするのかということについて互いに合意をする制度のことをいいます。これに対して、3号分割というのは・・・(続きを読む)
Q 妻から年金分割を求められました。自分は年金分割を拒否したいのですが、争う余地はありますか?
A 夫が年金分割を拒否し続けたとしても、妻が家庭裁判所に年金分割の申立てをすると・・・(続きを読む)
Q 夫は自営業なのですが、年金分割を求めることはできますか?
A 年金というのは、3階建ての構造になっていると言われていて、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金、3階部分が企業年金と位置付けられています。年金分割は、このうち、2階部分の厚生年金を対象とする制度です。自営業者の年金はというと・・・(続きを読む)
Q 財産分与は別居時の財産を対象にすると聞いたことがあります。ということは、年金分割も別居している期間は対象にならないと考えていいですか?
A 財産分与の場合は、基準時(通常は別居時)の財産が対象になりますので、別居後つまり別居期間中に築いた財産は財産分与の対象になりません。これに対して、年金分割の場合は・・・(続きを読む)
Q 離婚した後に年金分割をすることはできますか?また、請求期限はありますか?
A 年金分割は離婚と一緒に取り決めをすることもできますし、離婚後に取り決めをしたり家庭裁判所に申立てをすることも可能です。ただ、年金分割の請求には一定の期限があり・・・(続きを読む)
Q 年金分割をしたいと思うのですが、夫が協力してくれるかわかりません。年金分割をするためにはどのような方法があるのでしょうか?
A 当事者双方が年金事務所に行くという方法を取ることができるのであれば、最も時間とお金をかけずに年金分割の手続をすることができると思います。しかし、現実的には当事者が一緒に年金事務所に行くということは難しいことも多いため、その他の方法はというと・・・(続きを読む)
Q 年金分割をしたらどのくらい得するのかを知りたいのですが、何か方法はありますか?
A 50歳以上の方でしたら、年金事務所で「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という書類を取得することができます。また、統計上の数値ではありますが、年金分割をするかしないかでどの程度の差があるかというと・・・(続きを読む)
Q 離婚後に年金分割をしようと思っていた矢先に、元夫が死亡しました。もう年金分割をすることはできないのでしょうか?
A どのタイミングで元夫が死亡したのかによって結論が変わります。年金分割の合意ができていた場合は・・・(続きを読む)
Q 離婚協議書で「当事者間に債権債務がないことを確認する」という取り決めをしましたが、離婚後にやはり年金分割をしたいと思うようになりました。このような取り決めをしていても年金分割はできますか?
A 年金分割の請求というのは、あくまで厚生労働大臣に対する請求であって、元配偶者に対する請求ではないので・・・(続きを読む)
Q 離婚する際に年金分割をしたいと言いましたが、夫が拒否しました。そこで、やむを得ず年金分割はしないという内容の離婚協議書を作成し離婚しました。しかし、離婚後に冷静になって考えると、やはり年金分割をしたいと思うようになりました。このような場合に、年金分割はできますか?
A 年金分割をしないという内容の離婚協議書の有効性が問題になります。この点が問題になった裁判で、裁判所がどのような判断をしたかというと・・・(続きを読む)
☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話(06-6384-0088)よりご予約いただきますようお願いいたします。