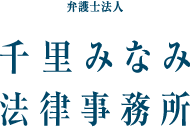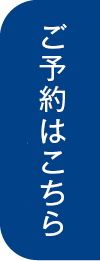【大阪の相続弁護士が教える】相続人が無償で使用している被相続人名義の土地を取得する場合の当該土地の評価額
1.はじめに
前回は、相続人と被相続人との間に土地の賃貸借契約が成立している事案、つまり被相続人名義の土地に賃借権の負担が付いている事案において、当該相続人が土地を取得する場合の土地の評価額について解説しました。
今回は、相続人と被相続人との間に土地の賃貸借契約は成立しておらず、あくまで無償で使用することができる合意つまり使用貸借契約が成立している事案において、当該相続人が土地を取得する場合の土地の評価額について解説してみることとします。
たとえば、被相続人名義の土地に相続人の一人が建物を建て、その建物に無償で居住しているような場合がこれに当たります。
このような場合、土地には使用借権の負担が付いているということになります。
2.使用借権負担付の土地評価の基本的な方法
使用借権は賃借権と異なり、第三者に対抗することはできませんが、使用借権とはいえ、土地の上に土地所有者以外の人の名義の建物が建っている場合、その土地は事実上売却が困難となります。
そのため、その土地の評価額は更地価格よりは1~3割程度減価されるといわれています(『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版256頁)。
具体的には木造などの非堅固な建物が建っている場合は1割減とし、鉄筋コンクリート造など堅固な建物が建っている場合には2割減、事情によっては3割減とすると説明されています((『弁護士のための遺産相続実務のポイント』日本加除出版96-80頁)
したがって、被相続人名義の土地(更地価格5000万円)の上に、相続人名義の木造建物(非堅固な建物)が建っており、その相続人は無償で土地を使用していたという事案であれば、その土地の評価額は4500万円になるということです。
(計算式)
更地価格5000万円-使用借権減価(5000万円×10%)=4500万円
3.使用借権者(建物所有者)が使用借権負担付の土地を取得する場合
上記の例で、建物所有者である相続人が底地を取得する場合、その土地の評価額は4500万円とすることになるのでしょうか。
この点に関しては、前回の記事で解説した借地権負担付の土地の取得の場合と同じように考えます。
すなわち、①その土地の評価額は更地価格とする考え方と②土地の評価額は、使用借権減価をした額としつつ、使用借権評価額相当の利益を無償使用してきた相続人の特別受益の問題とする考え方があります(詳細は前回の記事を参照ください)。
①の考え方による場合は、上記例の土地の評価額は5000万円となるのに対し、②の考え方による場合は、土地の評価額は4500万円としつつ、使用借権評価額相当の500万円は特別受益の問題とすることになります。
家裁実務においては、前回解説したとおり、②が主流になっているといわれています。
②の考え方による場合は、遺産である土地に建物を建て、その土地を無償で使用している相続人は、使用借権の設定を受けたことにより、土地使用借権の生前贈与があったものとして、土地使用借権相当額について特別受益を受けたと考え、あとは被相続人の持戻し免除の意思表示の有無を検討することになります。
上記例であれば、仮に被相続人による持戻し免除の意思表示があったとはいえない場合には、特別受益である500万円は持ち戻されることになるため、結局土地の評価額は更地価格である5000万円と同じ結果となります。
4.建物所有者たる相続人が被相続人を扶養等していた場合はどうか
被相続人所有の土地に、相続人の一人が建物を建て、無償で土地を使用させてもらっている反面、その相続人が被相続人の介護をしたり、扶養をしたりしてきたという場合はどのように考えるのでしょうか。
この点については、次のように考えられています。
被相続人に一緒に住んでくれと言われてその土地上に相続人が建物を建てたが、他方、被相続人を扶養するという負担を負っていた場合には、扶養の負担と土地使用の利益とは実質的に相当の対価関係に立つから、特別受益はないと考えられる。仮に、特別受益に当たるとしても、黙示の持戻し免除があるとして、使用借権減価をするのが相当である。この場合、土地使用の利益と対価関係に立つ扶養については、寄与分の主張はできないものと解される。
(『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版259頁)
したがって、上記例において、建物所有者である相続人が被相続人の扶養をするという負担を負っていた場合には、その相続人が土地を取得するに当たっては、その評価額を4500万円と評価することになります。
つまり、何の負担もなく無償で土地を使用できていた相続人が土地を取得する場合と扶養等の負担を負ってきた相続人が土地を取得する場合とで、土地の評価額に差をつけることで妥当な解決を図ろうというわけです。
【大阪の相続弁護士が教える】相続人所有の建物の底地を当該相続人が取得する場合の土地の評価額
1.借地権負担付の土地評価の基本的な方法
一般的に、借地権の設定されている土地の価格を評価するに当たっては、更地価格から借地権価格を控除する方法がとられます(『三訂版 遺産分割の理論と審理』新日本法規410頁)。
つまり、更地価格1億円の土地があり、その土地の借地権割合が60%という事例であれば、その土地の評価額は4000万円ということになります。
(計算式)
更地価格1億円-借地権価格(1億円×60%)=4000万円
2.借地権者(建物所有者)が借地権負担付の土地を取得する場合
以上を踏まえて、このような例を考えてみたいと思います。
土地(更地価格1億円、借地権割合60%)が被相続人の所有で、建物が相続人の一人の所有となっているケースがあったとします。
このケースにおいて、被相続人と建物所有者との間で賃貸借契約が締結され、建物所有者が相応の地代を支払っている場合などには、被相続人の所有する土地は借地権の負担が付いた土地ということになります。
では、遺産分割において、借地権者(建物の所有者)が被相続人名義の土地を取得するとなった場合、その土地の評価額は前記1のとおり4000万円となるのでしょうか。
この点に関しては、次のような説明をする文献があります。
借地権者が底地を買い取る場合、底地は収益不動産ではなく自用不動産として完全所有権を回復し、底地と借地の併合の利益が生ずるので、併合後は更地価格と等しくなる(中略)。
(『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版212-213頁)
遺産土地の評価は借地権や使用借権により制限された不動産としての評価をすることになるため、遺産土地に対する借地権や使用借権に基づき同土地上に建物を所有する相続人が同土地を遺産分割により単独で取得するときには、その相続人は、更地として評価される土地を取得したのと異ならない計算結果となる。したがって、(中略)更地として評価した上、その価額によって、借地権や使用借権を有する相続人で単独取得させる方法を採用することも、相当であると考えられる。
(『三訂版 遺産分割の理論と審理』新日本法規290頁)
この説明を前提とすると、借地権者(建物の所有者)が被相続人名義の土地を取得する場合、当該土地の評価額は更地価格(前記例であれば1億円)ということになります。
このような考え方は、その土地に負担をかけている相続人が、その土地を取得することで負担がなくなるときは、その負担は考慮しないというもので、「自用地論」といわれています。
一方で、これとは異なる考え方もあります。
1億円の更地価格の土地に対する借地権価格は6000万円となる。そこで、更地価格1億円-借地権価格6000万円で、底地価格は4000万円と評価されることになる。(中略)この価格は、「底地を取得することで完全な所有権を事実上取得できる場合」、例えば、取得者が借地人や借地人の親族の場合、あるいは土地を一体開発するデベロッパーのような場合の「限定価格」である。
(『弁護士のための遺産相続実務のポイント』日本加除出版96-97頁)
この記載からすると、借地権者(建物所有者)が被相続人名義の土地を取得する場合、当該土地の評価額は限定価格(特定の取引環境のもとでのみ成立する不動産価格。前記例であれば4000万円)となります。
そうすると、更地価格で評価する前者の考え方と後者の考え方で大幅に金額に差が出ることになるようにも思えます。
ただ、後者の考え方は、土地の評価額は借地権価格を控除した額としつつ、借地権者である相続人が得た借地権は特別受益の問題とすることで調整を図ることになります。
ここで、一つの文献の記載を見てみたいと思います。
相続人が、被相続人の土地上に建物を建築する際に、被相続人の土地に借地権を設定した場合、「借地権の設定により当該相続人は借地権相当額の利益を得ながらその対価を支払っていない一方、被相続人の財産はその分減少するので、贈与と同視することができ、借地権相当額の特別受益に該当する」が、他方、「借地権取得の対価すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので特別受益に該当しないことになる」(中略)し、持戻免除の意思表示が認められる場合もあると解される。
(『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版252-253頁)
すなわち、この考え方は、上記の例でいうと、土地の評価額は4000万円としつつ、借地権相当額(6000万円)は特別受益の問題とするわけです。
仮に、借地権者(建物所有者)が世間相場の権利金を支払っていない場合には、結局6000万円が持ち戻されることになり、前述の自用地論と同じ金額となります。
ここで、一つの例を出して考えてみたいと思います。
被相続人の遺産は借地権負担付の土地(更地価格1億円、借地権割合60%)と預金5000万円があり、相続人は子であるAとBがいて(法定相続分は各2分の1)、当該土地には相続人A所有の建物が建っているという事案があったとします。なお、Aは被相続人に対して権利金を一切支払っていないとします。
自用地論で考えた場合、遺産総額は1億5000万円となり、Aが土地を取得するのであれば、Bが預金全額(5000万円)を取得し、さらにAがBに対して2500万円を支払うことになります。
一方で、特別受益の問題とする場合、結局、借地権相当額6000万円が持ち戻されるため、みなし相続財産は1億5000万円となります。
その結果、Aの具体的相続分は1500万円(1億5000万円×1/2‐6000万円)、Bの具体的相続分は7500万円(1億5000万円×1/2)となり、結局自用地論と同じく、Bが預金を全額取得し、AがBに対して2500万円を支払うことになります。
したがって、自用地論であっても、特別受益の問題とする考え方であっても、特別受益の持ち戻しがされる事案であれば、基本的には同じ帰結になると考えられます。
一方で、仮にAが世間相場の権利金を支払っている事案であれば、特別受益の問題とする考え方の場合、借地権相当額6000万円の持ち戻しはされないため(借地権は特別受益に当たらないため)、遺産総額は9000万円(土地4000万円+預金5000万円)となります。
そして、A、Bの具体的相続分は各4500万円となり、Aが土地と預金500万円を取得し、Bが預金4500万円を取得するという結論になります。
この事案において、自用地論を貫徹すると、Aが世間相場の権利金を支払っていたとしても、AはBに対して2500万円を支払わなければならなくなると考えられます。
しかし、Aは被相続人に対して世間相場の権利金という対価を支払って、借地権を得ているにもかかわらず、遺産分割において当該土地の評価額を更地価格で評価すると、上記対価(権利金)支払いの事実が一切考慮されず、一律更地価格となり、妥当な結論とならないおそれがあります。
そこで、現在の家裁実務では、具体的事情に応じた柔軟な解決ができることから、おおむね特別受益の問題とする考え方で運営されているといわれています((『弁護士のための遺産相続実務のポイント』日本加除出版87-88頁)。
3.権利金の支払いはないが地代の支払をしていた場合はどうか
前述のとおり、特別受益の問題とする考え方においては、借地権者(建物所有者)が世間相場の権利金を支払っている場合には、借地権相当額は特別受益とならず、持ち戻すことはないと考えられています。
では、権利金は支払っていないものの、地代の支払いは継続していたという事案であれば、どうでしょうか。
この点に関して、遺留分の事件ではありますが、次のような裁判例(東京地判令和3年11月12日)があります。
(借地権の設定に当たって,亡Aと被告との間で権利金等の名目でまとまった金員の授受はされなかったという事案)
亡Aと被告は,本件借地権の設定に際し,賃料を月額16万円と定め,その後,少なくとも平成7年ころまで,亡Aに上記賃料の支払いを行っていたと認められる。これに照らせば,亡Aが無償で被告のために本件借地権を設定したとはいえず,被告が亡Aから本件借地権を贈与されたとは認められない。
原告らは,権利金等の名目での金銭の授受がないことをもって,本件借地権が無償で設定されたなどと主張するが,そうした金銭の授受がないことをもって地代の定めがある借地権について無償で設定されたということはできない。よって,原告らの上記主張は採用できない。
すなわち、この裁判例は、権利金の支払いはないものの、地代の支払いがあることをもって、借地権の贈与(特別受益)があったとはいえないとしています。
一方で、同じく遺留分の事件において次のような裁判例(東京地判平成30年5月10日)があります。
この事案では、被告は、「原告の賃借権の取得が認められたとしても,原告は,その対価として権利金を負担することもなく賃借権の設定を受けたことになるから,特別受益として借地権価額相当の生前贈与を受けたものと同視することができる。」と主張しました。
これに対して原告は、「原告は,亡Aの間で,これに関する賃貸借契約書を取り交わしていないが,亡Aから,上記分筆の際にその地代として,本件土地(1)に係る固定資産税のみならず,亡Aの居住する本件建物及び本件土地(2)に係る固定資産税についても負担をするよう求められたところ,原告においては従前から上記稽古場の利用料として,これらの固定資産税の支払をしていたが,旧建物の解体に伴い,その利用料を支払う必要がなくなったにもかかわらず,亡Aの上記要求により,それ以降は,本件土地(1)の地代として,これらの固定資産税の支払を継続していたのである。(中略)以上によれば,原告と亡Aとの間には,平成6年4月以降,本件土地(1)を目的物として,亡Aの所有する不動産に係る固定資産税相当額を賃料とする賃貸借契約が成立していたということができる。(中略)原告は,平成元年5月にBが死亡して以降,家族と共に,毎日欠かさず食事を亡Aの自宅まで届けていたほか,亡Aの光熱費などの生活費の多くを原告が負担するなどしていたのである。このように原告が長年にわたり亡Aに対する経済的な負担をしてきたことにより,本件土地(1)に係る賃借権設定の対価は支払われていたとみることができるから,特別受益としての生前贈与には当たらないというべきである。」と反論しました。
この点に関する裁判所の判断は次のとおりです。
確かに,原告において亡Aの所有する不動産に係る固定資産税の支払をしていたことが認められる。しかし,これらの支払は,その引き落としがされていた原告名義の預金通帳の記載(甲9)及び領収証等(甲10)によると,当該分割支払の全額が分かる時期でみても,概ね年額15万円ないし20万円程度で推移していたものと認められるところ,かかる負担額は,後記説示に係る本件土地(1)の評価額に照らし,その地代としては著しく低廉なものと認められ,直ちに本件土地(1)の使用の対価としての性質を有するものとは認め難い。実際,前記認定事実によれば,原告においては,原告建物の敷地として本件土地(1)が分筆される以前から,亡Bの書道家の地位を継いで旧建物の稽古場で書道教室を運営していた関係で,亡Bが生前負担をしていたこれらの固定資産税の支払をしていたものであり,旧建物が取り壊された後も,原告は,本件土地(1)上に建築した原告建物に稽古場を設けて引き続き書道教室を運営しながら,これらの支払を継続していたにすぎず,客観的にも,その前後でその支払の額や方法に違いはみられないのである。これらによると,原告において亡Aの所有する不動産に係る固定資産税の支払をしていたのは,亡Aとの親子の情宜に基づき,上記のような態様により本件土地(1)を無償で利用することについての費用負担及び謝礼の範囲内のものとみられるのであり,これらが本件土地(1)の地代の趣旨で支払われたものとは認め難いのである。この点,原告は,その本人尋問において,亡Aから本件土地(1)の地代としてこれらの固定資産税の支払をするよう要請されていた旨の上記主張に沿う供述をするが,他方で,亡Aの相続税の申告の際に,当該賃借権の存在を認識しながら,これを前提とした申告をしなかったことについて曖昧な供述に終始するなど,その供述内容は直ちに採用できるものではない。(中略)
(1) 仮に,本件土地(1)について,原告の賃借権の取得が認められるとしても,後記説示に係る評価額に照らすと,その借地権価額は多額に上るものであり,共同相続人間の実質的衡平の観点から,原告において,その対価として権利金を負担することもなく,当該賃借権の設定を受けたことは,借地権価額相当の生前贈与を受けたのと同視して特別受益に当たるものと解するのが相当である。
(2) これに対し,原告は,平成元年5月に亡Bが死亡して以降,原告の家族と共に,毎日欠かさず食事を亡Aの自宅まで届けていたほか,亡Aの光熱費などの生活費の多くを原告が負担するなどしていたのであり,こうした長年にわたる経済的な負担をもって,本件土地(1)について,借地権価額相当の支払がされていたとみることができるから,原告において賃借権の設定を受けたことは,特別受益としての生前贈与に当たるということはできないのであり,仮にこれに当たるとしても,亡Aが原告を隣地に居住させたのは高齢となった自身の面倒をみてほしいという希望があったからであり,実際に,原告は,亡Aのこうした意向に従って上記のとおり面倒をみてきたのであるから,亡Aにおいて持戻免除の意思表示があったと主張する。
(3) しかし,原告は,その本人尋問において,これに沿う供述をしているが,証拠(乙9~12,被告本人)によれば,実際には,亡Aは,被告と再婚する前から,隔月毎に約30万円の年金を受給しながら,自ら光熱費等の生活費を支出するなど,経済的に自立した生活を送っていたものとうかがわれ,原告の上記供述は額面どおり採用できるものではなく,他に,原告において,亡Aに対して通常の扶養義務の範囲を超えるほどの援助をしたと認めるに足りる確たる証拠もない。これらによると,原告において上記賃借権の設定を受けたことが特別受益に当たることを否定することはできず,本件遺言の内容も踏まえると,亡Aにおいて黙示にも持戻免除の意思表示があったと認めることはできない。
(4) 以上によれば,原告の上記各主張は採用することはできず,仮に,原告が本件土地(1)について賃借権を取得していたとしても,その借地権価額が特別受益として基礎財産に加算されるというべきである。
この裁判例を前提とすると、権利金の支払いがない場合に、地代が支払われていたとしても、その地代が土地の評価額に比して、その地代としては低廉なものと認められるなどの場合には、借地権相当額が特別受益に当たると判断される可能性があるといえそうです。
4.まとめ
以上見てきたとおり、被相続人の所有する土地に借地権の負担が付いている事案において、相続人の一人である借地権者(建物所有者)が当該土地を取得する場合、①その土地の評価額は更地価格とする考え方と②土地の評価額は、更地価格から借地権価格を控除した額としつつ、借地権相当額は特別受益の問題とする考え方があります。
現在の家裁実務では、②が主流とされていますが、借地権相当額が特別受益となるか否か(あるいは持戻免除の意思表示があったと認められるか否か)は、借地権者(建物所有者)が借地権を取得する対価(世間相場の権利金や相応の地代など)を支払っているか否かによると考えられます。
今回は、被相続人名義の土地に借地権の負担がある事案を想定して説明を行いましたが、次回は被相続人名義の土地を相続人が無償で使用している事案(使用貸借の事案)について解説してみたいと思います。
次の記事はこちら
【相続】一部の相続人を除外して遺産分割を行った場合の効果
一部の相続人を除外して遺産分割を行った場合の効果に関する記事を相続専門サイトにアップしました。
【大阪の相続弁護士が教える】遺産分割(相続)において、債務をどのようにして処理するか
1.はじめに
被相続人に債務(借金)がある場合に、まず考えるのは相続放棄かもしれません。
しかし、被相続人が事業をしているようなケースでは、債務がある反面、プラスの財産もあることがあります。
たとえば、被相続人には2000万円の債務があるけれども、3000万円の財産があるというような場合には、通常は相続放棄をするという選択はとらないはずです。
今回は、このようなケースを想定して、遺産分割において債務をどのように処理すればいいのかという点について解説していくこととします。
相続人は、長男Aと二男Bの2名で、被相続人の生前の債務は2000万円、プラスの財産は3000万円、遺言はないというモデルケースを前提とします。
2.大原則
判例は、債務について次のように示しています。
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである
(最判昭和34・6・19民集13・6・757)
したがって、まず大原則として、債務は相続によって、各相続人の相続分に応じて承継されることになるため、遺産分割の対象とはなりません。
つまり、上記のケースであれば、2000万円の債務は、長男Aと二男Bに1000万円ずつ承継されるということになります。
その上で、プラスの財産3000万円をどのようにして分けるかということを協議するということになります。
3.債務を遺産分割協議の対象にすることができるか
上記のとおり、債務は遺産分割の対象となりません。
確かに、プラスの財産3000万円が預金であれば、長男Aと二男Bが1500万円ずつ取得して、そこから各自が承継した債務1000万円を返済してしまうという処理をするという処理が考えられます。
しかし、例えば3000万円の財産が不動産で、これを売ることも難しいというような事情があるケースであればどうでしょうか。
このような場合、長男Aと二男Bが話し合って、長男Aが単独で債務2000万円を引き継ぐ代わりに3000万円の不動産をもらうというような処理をすることも可能です(その上で、長男Aから二男Bに500万円を渡せば、公平な解決となります)。
ただ、注意が必要です。
長男Aが債務を単独で債務を承継するというのはあくまで、当事者間の話し合いの結果にすぎませんから、債権者に対しては、この話合いの効力を及ぼすことができません。
つまり、債権者が、上記2に記載した判例の考え方に基づいて、長男Aと二男Bに対してそれぞれ1000万円を請求した場合に、二男Bが債権者に対して「この債務は全部、長男Aが引き継ぐことになったので、Aに請求してください」と言っても、債権者は「そんな当事者間の話し合いなんて知ったこっちゃない」と言えるということです。
その結果、問答無用で、債権者から二男Bに対する請求が認められるということになります。
したがって、このような処理をする場合には、遺産分割協議を成立させる前に、金融機関などの債権者と交渉をして、長男Aが単独で債務を相続して、二男Bに対する債務は免責してもらうこと(免責的債務引受)ができるかを確認しておく方がよいといえます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の相続弁護士が教える】療養看護型の寄与分における介護報酬額の計算方法
1.はじめに
療養看護行為を行った場合の寄与分の計算方法について、文献等にあまり詳しく載っておらず、どのように主張すればいいのか分からないという方がおられるかもしれません。
今回は、実務的によく参照される文献と思われる『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版)を紐解きながら、具体的な計算方法について検討してみたいと思います。
今回の記事は、主に弁護士などの専門家向けの説明となっていますので、基本事項の説明は省略させていただきます。
2.身体介護報酬基準額の計算方法
前述した『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版)の第4版・341頁には次のような記載があります。
介護保険制度の施行後(平成12年4月以降)は、介護保険における「介護報酬基準」が用いられることが多くなっている。同基準は、介護に要する時間に基づき介護種別(要支援・要介護)を7段階に区分し、それぞれの区分に応じた介護サービスのための報酬額を明示している。
実務においては、要介護者の受けた介護サービスの内容、居住地(級地)等を考慮して介護報酬を算定したものを参考に療養看護の寄与分を算定している。
そのうえで、次のような表が掲載されています。
介護報酬基準額に基づく身体介護報酬額(2021年 1級地(東京23区)の場合)
|
介護種別
|
介護状況
|
要介護認定基準時間
|
身体介護報酬基準額
|
|
裁量割合
|
|
|
なし
|
0.8
|
0.7
|
0.6
|
0.5
|
|
要介護2
|
中等度の介護を要する
|
50分以上70分未満
|
6,578
|
5,262
|
4,604
|
3,947
|
3,289
|
|
要介護3
|
重度の介護を要する
|
70分以上90分未満
|
6,578
|
5,262
|
4,604
|
3,947
|
3,289
|
|
要介護4
|
最重度の介護を要する
|
90分以上110分未満
|
7,524
|
6,019
|
5,267
|
4,514
|
3,762
|
|
要介護5
|
過酷な介護を要する
|
110分以上
|
8,470
|
6,776
|
5,929
|
5,082
|
4,235
|
(注)上表は、訪問介護の場合における介護報酬基準額に基づき、介護報酬単位表と要介護基準時間表を用いてそれぞれの要介護度ごとに療養看護報酬額(日当)を試算したものであるが、要介護度に対応した要介護認定等基準時間には幅があるので、具体的評価の場面では個別に検討する必要がある。
上記の注釈を見る限り、上記の表は、国などが定めた所与のものではなく、著者が計算した結果を記載したものであることがわかります。
ただ、この表に記載されている金額が一体どのようにして計算されているのかが、注釈を何度読んでも今一つよく分かりません・・・。
そこで、以下では、その計算過程を探ってみることにします。
①訪問介護の介護報酬基準額
厚労省が公表している令和元年度介護報酬は、このサイトから見ることができます。
抜粋すると、訪問介護費は、身体介護が中心である場合には、
⑴ 所要時間20分未満の場合は166単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合は249単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合は395単位
⑷ 所要時間1時間以上の場合、577単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数となっています。
そして、1単位の単価は基本10円です。
このことを踏まえて、要介護2~要介護5の各要介護認定基準時間に対応させると次のとおりとなります。
・要介護2:577単位(5,770円)
・要介護3:577単位(5,770円)
・要介護4:660単位(6,600円)
・要介護5:743単位(7,430円)
しかし、これでは上記の表の裁量割合なしの金額と一致しません。
②1単位の単価の修正
先ほど1単位の単価は基本10円と書きましたが、サービスごと、地域ごとに1単位の単価が設定されており、サービスや地域によって微妙に金額が修正されています。
こちらのサイトを見てみてください。
訪問介護の人件費割合は70%で、先ほどの表は1級地(東京23区)の場合を例にしていますから、上乗せ割合は20%となり、結局1単位の単価は11.4円となります。
この単価を前提に、要介護2~要介護5の各単位にかけ合わせてみると、次のような金額が出てきます(小数点以下は四捨五入)。
・要介護2:577単位(6,578円)
・要介護3:577単位(6,578円)
・要介護4:660単位(7,524円)
・要介護5:743単位(8,470円)
これでようやく金額が一致することができました。
ということで、おそらく、『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』は上記のような計算過程で表を作成したものと思われます。
地域ごとの上乗せ割合についても、先ほど挙げたサイトに載っていますので、そちらをご参照いただければ、各地域に応じた金額を出すことも可能となります。
ちなみに、この記事では、上記文献の計算過程を探るべく令和元年度介護報酬を基準に計算しましたが、令和3年度に単位が改定されていますので、上記文献の版が改定される際には記載される金額が変わっているかもしれません。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】使途不明金問題の解決方法~被相続人死亡後の引き出しのケース~
1.はじめに
前回の記事では、被相続人の生前に使途不明な金銭が引き出されたケースを取り上げました。
今回は、被相続人の死後に金銭が引き出されたケースを考えてみることにしましょう。
たとえば、被相続人の相続人は、長男A、二男B、三男Cの3人だったとしましょう。
二男Bが被相続人の預金口座の取引履歴を確認したところ、被相続人の死亡直後に500万円(50万円×10回)が引き出されていることが判明しました。
Bは、亡くなった人間が口座から引き出すことはできないので、間違いなくAかCが引き出したに違いないと考え、AとCに事実関係を確認しました。
すると、Aは自分が引き出したことを認めました。
被相続人の遺産としては、この引き出された500万円のほかに1000万円の預金があったとします。
このような場合、被相続人の死亡後にAが引き出したこの500万円はどのように扱われるのでしょうか?
2.全相続人の同意がある場合
遺産分割の対象となる財産は、①相続時(被相続人の死亡時)に存在し、かつ②遺産分割時にも存在していなければなりません。
そうすると、遺産分割前にお金が引き出されてしまうと、遺産分割時には存在しないということになるので、原則として遺産分割の対象になりません。
したがって、上記のケースの場合、Aが引き出した500万円は遺産分割の対象にならないということになりそうです。
もっとも、全相続人の同意があれば遺産分割の対象とすることができます。
BとCはこの500万円を遺産分割の対象にすることに異論はないとして、Aが遺産分割の対象にすることに同意すれば全相続人の同意によってこの500万円は遺産分割の対象にすることができるということになります。
つまり、500万円を遺産分割の対象にすれば遺産総額は1500万円となり、Aはすでに500万円を受領しているので、残る1000万円をBとCで500万円ずつに分けるということになります。
3.引き出した人が遺産分割の対象にすることに同意しなかった場合
ではAが「この500万円は確かに自分が引き出したけど、被相続人の葬儀費用とか未払いの債務の弁済のために全部使ったんだから、遺産分割の対象にするのはおかしい」と言った場合はどうでしょうか。
仮に上記のとおり遺産分割の対象になるとすれば、Aはすでに500万円を受領しているので、残る1000万円をBとCが500万円ずつ取得することになります。
しかし、Aからすると、引き出した500万円は被相続人のために使ったもので、自分のために使っていない以上、遺産分割の対象にされてしまうと、自分の取り分がなくなってしまうということになりかねません。
そのため、Aは遺産分割の対象とされることに反対しているわけです。
この点、改正民法906条の2には次のような規定が設けられました。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
906条の2第1項は正に全相続人の同意がある場合ですので遺産分割の対象にするということに特に違和感はないと思います。
一方で、第2項に注目してみると、財産を処分した相続人の同意は必要でないということが書かれています。
つまり、本ケースでいうとAの同意がなくとも、Aが引き出した500万円は遺産分割の対象とすることができるということになります。
したがって、いくらAが「引き出した500万円は自分のためではなく被相続人のために使ったんだ!」と強弁しても、BとCがこのAの説明に納得せずに相続財産の対象とするべきだと主張すれば、この500万円も遺産分割の対象となるということです。
となると、Aが真に被相続人のために500万円を使っていた場合には、Aからするととても納得できないということになりそうです。
そこで、Aがこの500万円について争いたいということになれば、AからB・Cに対して訴訟を提起するほかないということになります。
4.Aが引き出し行為を認めていない場合はどうなるか?
上記ケースではA自身が引き出しを認めていますので、民法906条の2を適用して遺産分割の対象にするという処理をすることができます。
しかし、Aが「自分は500万円を引き出していない」と主張した場合にはこの規定を適用することはできません。
したがって、Aが引き出しの事実を認めない場合には、やはり訴訟によって解決するほかないということになります。
5.被相続人の生前の引き出しのケースで民法906条の2は使えないの?
前回の記事を読んでいただいた方からすると、被相続人の生前に引き出したケースでも民法906条の2を適用して遺産分割の対象にすればいいのでは?と思われるかもしれません。
しかし、相続開始前(被相続人の死亡前)に財産が処分された場合には民法906条の2は適用されません(『Q&A改正相続法のポイント』50頁)。
そのため、被相続人の生前の財産の処分が問題となるケースは、前回の記事で説明したような解決の方法を探ることになります。
6.まとめ
以上のとおり、被相続人の死亡後に預金を引き出すなどの財産の処分を行い、良かれと思って葬儀費用等に充ててしまうと、後々になって他の相続人がその財産処分に納得しなかった場合に思わぬ紛争を引き起こしてしまう可能性があります。
そのため、特定の相続人の独断で被相続人の財産から支払等をするのではなく、できる限り全相続人で話し合って進めていった方が後々揉めにくいと考えられます。
☆遺産分割、遺言、遺留分、寄与分、特別受益などでお悩みの方は相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では相続事件に力を入れて取り組んでおり、相続分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
相続に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【相続】使途不明金問題の解決方法~被相続人死亡前の引き出しのケース~
1.はじめに
被相続人が死亡したことをきっかけに、相続人の1人が遺産である預金の残高を確認したところ、死亡の直前に一気に残高が減っていてびっくりしたなんていうことはよくある話です。
このことを知った相続人が「他の相続人が取ったはずだ」と考えることがあります。
このような問題のことを一般に「使途不明金の問題」などといいます。
実務においてはよく問題になる事柄の一つです。
では、この使途不明金の問題はどのようにして解決すればよいのでしょうか。
ここでは被相続人が死亡する前に使途不明の金銭が引き出されているケースについて解説したいと思います。
2. 使途不明金を特定できるかどうか?
ある相続人が、「亡くなった父にはもっと財産があるはずだ!」と主張したとします。
しかし、通帳をいくら見ても使途不明な出金の形跡などがなく、かつ他の相続人も遺産が思ったよりも減っていることについて全く心当たりがないと言っているような場合、この使途不明金問題を遺産分割協議で取り上げることはできません。
これは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てても同じです。
家庭裁判所が積極的に遺産を探す手伝いをしてくれるわけではありません。
どうしてもこの使途不明金の問題について追及したいということであれば、訴訟を検討するほかありません。
では、使途不明金が特定できている場合はどうでしょうか?
具体的に被相続人の亡くなる半年前からまとまったお金が引き出されているなどの形跡があり、そのお金を誰が引き出したのかについて当事者間に争いがないような場合、一応この問題を協議や調停で取り上げることができます。
「一応」と書いたのはなぜかというと、使途不明金の問題は、本来は訴訟で解決すべき問題だからです。
調停や任意の協議で使途不明金の問題を取り上げた結果、実際に特定の相続人が自分が引き出して自分のために使ったことを素直に認めたり、自分が引き出したけれども被相続人のために使ったとの説明を行い他の相続人もそれに納得したような場合には話し合いによる解決ができる可能性があります。
他方で、協議や調停を重ねたけれども、使途不明金の説明がされないとか、説明がされたとしても他の相続人が納得できないということになれば、話し合いでの解決は不可能ということになります。
そうなれば、訴訟での解決を図るほかないということになります。
3.まとめ
以上のとおり、原則として使途不明金の問題は訴訟によって解決すべき問題とされています。
もっとも、使途不明金が具体的に特定されており、話し合いによって解決の余地があるような場合には協議や調停による話合いの土俵に載せることができるということになります。
そして、話し合いをした結果、やはり使途不明金についての協議が整わない場合には訴訟での解決を検討するという流れになります。
ちなみに、ここでいう訴訟は「地方裁判所」で行う訴訟のことを指します。
遺産分割調停は「家庭裁判所」で行いますので、この裁判所の管轄の違いを見ても、使途不明金の問題と遺産分割の問題が性質の異なるものだということがお分かりいただけるかと思います。
続きを読む
☆遺産分割、遺言、遺留分、寄与分、特別受益などでお悩みの方は相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では相続事件に力を入れて取り組んでおり、相続分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
相続に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【相続/離婚】財産分与請求権は相続の対象になるか?
1.はじめに
今回は離婚と相続が絡み合うテーマを取り扱ってみたいと思います。
熟年離婚が増えていると言われていますが、配偶者の死亡と離婚の問題というのは意外と身近なテーマだと思います。
一つ具体例を挙げてみましょう。
夫Aと妻Bの夫婦がいました。
この夫婦は数年前から家庭内別居状態で、互いに離婚を考えていたところ、子Cが社会人になったことを機に、離婚しようということになりました。
妻Bには特に財産はなく、一方で夫Aには財産が2000万円ありました。
そのため、妻Bは夫Aに対して財産分与として1000万円の請求をしようと考え、夫Aにもその旨伝えていました。
そのような矢先、妻Bが亡くなりました。
さて、妻Bが有していたはずの1000万円相当の財産分与請求権は子Cが相続することになるのでしょうか?
2.離婚前に死亡した場合
上記のケース様に、離婚前に一方配偶者が死亡した場合、財産分与請求権が相続されることはありません。
つまり、子Cは、妻Bの夫Aに対する財産分与請求権を相続することはできないということになります。
したがって、夫Aは子Cに対して一切お金をわたす必要はありません。
財産分与請求権という権利は離婚することによってはじめて発生する権利であるため、いまだ離婚していない以上、生前にいくら離婚を前提に財産分与を求めていたとしても、離婚前に死亡した場合には相続の対象にはならないということです。
3.離婚後に死亡した場合
では、上記ケースとは少し事案を変えて、夫Aと妻Bが離婚した後に妻Bが死亡した場合であればどうでしょうか。
この問題については、最高裁判例はありませんが、下級審レベルでは裁判例が存在しています。
【名古屋高裁昭和27年7月3日決定】
当事者の一方が既に相手方に対し財産の分与を請求する意思を表示し又は之を求むる為家事調停或は審判の申立を為して分与請求の意思を表示したが未だ調停又は協議が成立せず若しくは協議に代る裁判所の処分を得ないうちに死亡した場合に於て財産分与請求権が相続され得るか否かに付て按ずるに法が財産分与の制度を設けたのは単に配偶者の扶養の手段を与えようとする理由だけからではなく配偶者に相続権を認めたのに対応し離婚の当事者間の公平なる財産分配の意図も亦之を包蔵するものなることは民法第七百六十八条第三項が当事者双方が其の協力によつて得た財産の額を考慮すべき一切の事情の一として之を掲げているに徴しても明かであつて仮令未だ具体的な債権取得に至らずとするも既に分与請求の意思が表示された後の財産分与請求権は調停又は協議の成立若くは協議に代る裁判所の処分を経て一定の金銭又は財物の給付請求権の取得に至るべきものであるから其の性質は普通の財産権と化しているのであつて一般の金銭債権と同様相続され得べき権利であると解するのを相当とする。
➢被相続人が生前に財産分与の意思表示をしていれば、財産分与請求権が相続の対象となると判断しました。
【大分地裁昭和62年7月14日判決】
所謂清算的財産分与義務に関しては、それが財産的請求権であることに鑑みると、その相続を否定する理由はない(民法八九六条参照)。
➢この裁判例も財産分与請求権が相続の対象となると判断しました。さらに、この事案は被相続人が生前に財産分与についての特段の意思表示をしていませんでしたが、相続の対象となると判断しています。つまり、生前の財産分与請求の意思表示がなくとも相続の対象となるとの判断と解されます。
以上のように、名古屋高裁と大分地裁の二つの裁判例において、生前の意思表示の有無が要件になるかどうかという点は異なるものの、離婚後に死亡したケースでは基本的に財産分与請求権が相続の対象となるとの判断がなされています。
夫Aと妻Bが離婚した後に、妻Bが死亡した場合には、子Cは妻Bの有していた財産分与請求権を相続することができるということになります。
☆遺産分割、遺言、遺留分、寄与分、特別受益などでお悩みの方は相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では相続事件に力を入れて取り組んでおり、相続分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
相続に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【相続】「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)とは何なのか?
1.はじめに
「相続させる」旨の遺言という言葉を聞いたことはありますか?
相続案件を扱う弁護士であれば、当然のように使う言葉ですが、意外と一般の方にはなじみのない言葉かもしれません。
今回は、この「相続させる」旨の遺言について解説したいと思います。
「相続させる」旨の遺言とは、たとえば「長男に不動産を相続させる」というように、特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことをいいます。
改正相続法では、このような遺言を「特定財産承継遺言」という名称になっています(民法1014条2項)。
ここまでの説明で「『相続させる』という内容以外の書き方ってあるの?」という疑問を持たれる方もおられるかもしれません。
「相続させる」という書き方以外の一例として「遺贈する」という書き方があります。
では、「相続させる」と書くか「遺贈する」と書くかで何か違いがあるのでしょうか?
2.「相続させる」と記載する理由・メリット
実務においては、特定の相続人に特定の財産を取得させる場合、「遺贈する」ではなく、「相続させる」と記載するのが一般的です。
これには以下のような理由があります。
①登記手続が簡便になる
所有権移転登記手続において、「遺贈する」とした場合には他の共同相続人と共同で申請をしなければなりません(不動産登記法60条、昭和33年4月28日民事甲779号民事局長通達)。
これに対して、「相続させる」とした場合であれば、受益者(相続人)が単独で申請することが可能になります(不動産登記法63条2項、昭和47年4月17日民事甲1442号民事局長通達)。
したがって、「相続させる」旨の遺言にしておけば、不動産を取得する者にとって登記手続が簡便になるというメリットがあるということになります。
※追記
法改正により令和5年4月1日以降は、相続人への遺贈登記に限り、共同申請ではなく権利者からの単独申請が認められるようになりました。
②賃貸人の承諾が不要
遺産が借地権・賃借権の場合、「遺贈する」とした場合には賃貸人の承諾が必要となります(借地借家法19条、民法612条1項)。
これに対して、「相続させる」とした場合であれば賃貸人の承諾は不要です。
このように、「相続させる」旨の遺言にはメリットがあることから、実務においては「相続させる」旨の遺言が利用されるわけです。
ちなみに、農地法3条の許可が不要という点や登録免許税が安いという点を「相続させる」旨の遺言のメリットとして挙げているサイトがあるようです。
しかし、現在は特定の相続人に対する遺贈の場合であっても農業委員会の許可は不要とされています(農地法3条1項16号、3条の3、農地法施行規則15条5号)。
また、登録免許税についても平成15年4月1日から施行された登録免許税の改正により遺贈の場合も「相続させる」旨の遺言の場合も同一の税率が適用されるようになっています。
そのため、農地法3条の許可の点と登録免許税については、「相続させる」旨の遺言に特にメリットがあるというわけではありません。
3.相続人以外に「相続させる」とすることはできるか?
上記のとおり「相続させる」旨の遺言には、「遺贈する」と記載した場合と比べて一定のメリットがあるといえます。
しかし、当然ながら相続人以外の者は「相続する」わけではないので、相続人以外の者に対して「相続させる」と記載したとしても遺贈と扱われることになります。
たとえば、遺言者の子Aの子B(遺言者の孫)は、Aが存命中は遺言者の相続人ではありませんので、たとえ「Bに相続させる」という遺言を書いたとしても遺贈と解釈されるというです。
4.「相続させる」旨の遺言をどのように解釈するか
ここまで「相続させる」旨の遺言と遺贈を対比しながら説明してきましたが、「相続させる」旨の遺言というのは結局どういうものなのかということがかつて論点になっていました。
下級審においては、「相続させる」旨の遺言も遺贈と同じだと解釈するものや、遺産分割方法の指定であるが、遺言によって確定的には所有権は移転せず遺産分割協議によって確定的に所有権が移転すると解釈するものなどがありました。
この点、最高裁平成3年4月19日判決は次のように判示し、この論点に決着がつけられました。
遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。そして、右の「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法九〇八条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。そしてその場合、遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、右の協議又は審判を経る余地はないものというべきである。
➢ポイント
①遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
②遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される。
このように、最高裁は、原則として(特段の事情がない限り)、①「相続させる」旨の遺言を遺産分割方法の指定としたうえで、②特定相続人が特定財産の所有権を確定的に取得する時期は遺言の効力発生時期(別途遺産分割協議は不要)と解釈しました。
相続や遺言などの問題でお悩みの方は相続問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では相続案件に力を入れて取り組んでおり、多数の解決実績を有しております。
相続に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【相続】相続放棄の熟慮期間の起算点が繰り下げられるのはどんなとき?
1.はじめに
前回の記事で、「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、(中略)相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、(中略)熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と判断した最高裁昭和59年4月27日判決を紹介しました。
では、具体的に相続放棄の熟慮期間が起算点を繰り下げることを認められるのはどのような場合で、反対に認められないのはどのような場合なのかを見ていきたいと思います。
※下線は当事務所によるもの
2.起算点の繰り下げが認められたケース
①仙台高裁平成元年9月1日決定
(1) ところで、相続放棄の申述を受理するかどうかを判断するに当り、家庭裁判所がいかなる程度、範囲まで審理すべきかは、受理審判の法的性質をいかに考えるかによるものであるが、相続放棄は自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることを目的とする意思表示であつて、極めて重要な法律行為であることに鑑み、家庭裁判所をして後見的に関与させ、専ら相続放棄の真意を明確にし、もつて、相続関係の安定を図ろうとするものである。
従つて、受理審判に当つては、法定の形式的要件具備の有無のほか、申述人本人の真意を審査の対象とすべきことは当然であるが、法定単純承認の有無、熟慮期間経過の有無、詐欺その他取消原因の有無等のいわゆる実質的要件の存否の判断については、申述書の内容、申述人の審問の結果あるいは家庭裁判所調査官による調査の結果等から、申述の実質的要件を欠いていることが極めて明白である場合に限り、申述を却下するのが相当であると考える。けだし、相続放棄申述受理審判は非訟手続であるから、これによつて相続関係及びこれに関連する権利義務が最終的に確定するものではないうえ、相続放棄の効力は家庭裁判所の受理審判によつて生じ、それがなければ、相続人には相続放棄をする途が閉されてしまうのであるから、これらの点を総合考慮すると、いわゆる実質的要件については、その不存在が極めて明らかな場合に限り審理の対象とすべきものと解するのが相当だからである。
(2) これを本件についてみるに、前記2で認定した事実によれば、抗告人らは被相続人が生前不動産を所有し、相続財産としてこれらの不動産が存在することは認識していたものの、抗告人らの意識では、これらは農家にあつては、後を継ぐべき長男が取得するもので、抗告人らが相続取得することはないと信じ、被相続人には債務がないものと信じていたものであり、かつ、前記2の被相続人の生活歴、本件債務の発生原因、抗告人らと被相続人及び茂明との交際状態等からして、そのように信じたとしても無理からぬ事情があることが窺われるのである。従つて、民法915条1項の起算日については、前記2の昭和63年11月に農協から請求を受けて債務の存在を知つた時と解する余地がないわけではないと考えられる。
(3) そうであるとすれば、抗告人らの本件相続放棄の各申述は、(1)に従い、受理すべきが相当である。
②福岡高裁平成2年9月25日決定
二 家庭裁判所は、相続放棄の申述に対して、申述人が真の相続人であるかどうか、申述書の署名押印等法定の方式が具備されているかどうかの形式的要件のみならず、申述が本人の真意に基づいているかどうか、三か月の熟慮期間内の申述かどうかの実質的要件もこれを審理できると解するのが相当であるが、相続放棄申述の受理が相続放棄の効果を生ずる不可欠の要件であること、右不受理の効果が大きいこととの対比で、同却下審判に対する救済方法が即時抗告しかないというのは抗告審の審理構造からいって不十分であるといわざるをえないことを考えると、熟慮期間の要件の存否について家庭裁判所が実質的に審理すべきであるにしても、一応の審理で足り、その結果同要件の欠缺が明白である場合にのみ同申述を却下すべきであって、それ以外は同申述を受理するのが相当である。このように解しても、被相続人の債権者は後日訴訟手続で相続放棄申述が無効であるとの主張をすることができるから、相続人と利害の対立する右債権者に不測の損害を生じさせることにはならないし、むしろ、対立当事者による訴訟で十分な主張立証を尽くさせた上で相続放棄申述の有効無効を決する方がより当を得たものといいうる。そして、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から三か月以内に相続放棄の申述をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、右熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(最高裁昭和五九年四月二七日判決・民集三八巻六号六九八頁)。
三 ところで、本件記録によれば、抗告人A(大正一三年一〇月一五日生)はB(大正一五年二月一日生)の妻、同C(昭和二九年七月二二日生)はその子であること、Bは昭和六三年一〇月二八日心不全で死亡したこと、BとDとの間には、「昭和五四年八月四日、DがEに対し、五〇万円を弁済期同年九月三日、利息年一割八分、損害金年三割六分の約で貸し付け、Bほか二名が連帯保証した」旨及び全債務者の執行受諾文言が記載された福岡法務局所属公証人船津敏作成の昭和五四年第一九九七号金銭消費貸借契約公正証書(以下「本件公正証書」という。)が存在すること、抗告人両名は、平成元年一一月二八日に同月二四日付承継執行文の付された本件公正証書謄本の送達を受け、同年一二月一二日ごろにはDから同月一一日付の請求書で抗告人両名の各相続分が六九万三五八八円になるとしてその即時支払を請求されたこと、抗告人両名代理人の〇〇弁護士は、同年一二月二〇日、福岡家庭裁判所小倉支部に対し本件相続放棄の申述をしたことが認められ、抗告人両名は、本件において、要旨、次のとおり陳述する。「Bは、昭和六一年会社を退職して以来年金生活をしていたが、住居は借家であったし、貴金属、預金等の財産と呼べるものは何も残していなかったので、A としてはその後の生活をどうするかで頭がいっぱいであり、相続のことなど頭に浮かびもしなかった。また、Bは無口なたちで、A に外でのことを話すことは余りなかった。それで、A はBの生前、借金のことを聞いたことはなかったし、債権者から家に支払の催促が来たことの記憶もない。A は、平成元年一〇月一日男の人から電話でBの所在を尋ねられ、死亡したことを伝えると、死因等を聞かれた後、同人の借金を払ってもらわないといかんといって、電話をきられた。残金や連絡先など詳しいことは聞かなかった。Aは、同月五日区役所の無料法律相談に行って債務の相談のことを聞き、翌六日福岡在住のCに電話して対策を相談した。そして翌七日両名で弁護士事務所を訪れ、相続放棄制度の教示を受けた。しかし弁護士に委任すれば費用がかかることでもあり、同弁護士からもBに本当に借金があったかどうかもう少し様子をみてみたらどうかと助言を受け、両名で対策を思案していたところ、同年一一月二八日、本件公正証書謄本の送達を受けて初めてその内容を知り、先ごろの電話の主がDであったと推測できた。そこで再度弁護士に相談したところ、利息を加えると元金より多くなっているかもしれないことや今からでも相続放棄の申述が間に合う可能性があると教えられ、同年一二月九日同弁護士に本件相続放棄の申述手続を委任した。Cは昭和四〇年ころ大学生当時にBと別居し、昭和五七年結婚して独立し、以来福岡市内に居住しているので、同人の仕事や生活関係のことは殆ど知らず、借金の話など聞いたことがなかった。
そして、前記認定のとおり、相続債務たるBの債務が保証債務であること、本件記録上、Bが積極財産を残した形跡を認めるに足りる資料はないこと、その他前記認定の事実によれば、平成元年一一月二八日に本件公正証書謄本の送達を受けて初めてBの債務の内容を知ったとの、抗告人Cの前記陳述部分は首肯できるものである。他方、本件記録によれば、Dは本件公正証書に基づいて昭和五五年Bの電話加入権を差押え、抗告人A が昭和六一年これを買い受け、同年一〇月一四日Dは弁済金の交付を受けたことが認められ、この事実に照らすと、抗告人A の同趣旨の陳述部分をそのまま首肯することには疑問がないわけではない。しかしながら、同抗告人が電話加入権を買い受けたのが昭和六一年であったこと、右買受けの具体的経緯を認めるに足りる資料が何もないことを考えれば、同抗告人が昭和六三年一〇月二八日のB死亡時に相続財産が全くないと信じ、かつ、このように信ずるについて相当な理由があった場合に当たらないことが明白であるとまでいうのも躊躇される。なお、本件記録によれば、Bは昭和六二年一一月二八日本件公正証書上の遅延損害金債務の履行としてDに対し二万九五八九円を支払ったことが認められるが、このことも右判断を左右するものではない。
そうすると、抗告人両名の民法九一五条一項本文所定の三か月の熟慮期間は、本件公正証書謄本が送達された平成元年一一月二八日から起算されると認める余地があるから、本件相続放棄の申述はこれを受理するのが相当である。
③名古屋高裁平成19年6月25日決定
1 一件記録によると,抗告人は,被相続人B(以下「被相続人」という。)の二女であること,被相続人は,平成18年3月29に死亡し,抗告人は,同日,被相続人の死亡を知ったこと,被相続人の遺産には,○○市○○×丁目×番×の土地等の不動産が存在し,抗告人は,被相続人の死亡を知った時点において,被相続人に上記不動産の遺産があることを知っていたこと,しかしながら,抗告人は,昭和54年ころから被相続人と別居しており,先に抗告人の父であり被相続人の夫であるC(平成7年×月×日死亡)の遺産である土地を相続取得していたことや被相続人の遺産の1つである○○市△△×丁目×番×号の土地上には被相続人の居宅と共にその長女であるDの居宅が存在したことなどから,被相続人の遺産である不動産はすべてDが相続するものと考えていたこと,また,抗告人は,Dとは日常生活において疎遠であったことなどから,Dと被相続人の遺産分割の話などはしたことがなかったこと,抗告人は被相続人の死後の平成19年3月にDから知らされたことであるが,被相続人は,被相続人の有する一切の財産をDに相続させること等を内容とする遺言公正証書(以下「本件公正証書遺言」という。)を平成18年×月×日○○法務局所属公証人□□□□に嘱託して作成していたこと,ところが,抗告人は,平成19年2月28日,東京地方裁判所平成19年(ワ)第××号譲受債権請求事件(以下「別件訴訟事件」という。)の訴状を受け取ったことにより,被相続人が,株式会社○○銀行に対する連帯保証債務(Dの夫であるEが代表取締役を務める株式会社△△と同銀行との間の消費貸借契約に基づく株式会社△△の同銀行に対する主債務一切を保証する内容の連帯保証債務,以下「本件債務」という。)を負担していたことを初めて知ったこと,そこで,抗告人は,平成19年3月14日に岐阜家庭裁判所に対し本件相続放棄の申述を行ったこと等が認められる。
2 民法915条1項所定の3か月の熟慮期間は,原則として,相続人が,相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが,相続人が,上記各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人においてこのように信じるについて相当な理由があると認められるときには,上記熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁)。
そこで検討するに,抗告人は,被相続人の死亡を知った当時,被相続人の遺産として不動産が存在することは認識していたものの,上記認定の事情の下で,抗告人は,上記不動産は姉であるDが相続して自らは相続取得しないもの,したがって自らには相続すべき被相続人の相続財産はないものと信じていたことが認められ,かつ,抗告人は後になって知ったこととはいえ,被相続人が平成18年×月×日に被相続人の一切の財産をDに相続させる旨の本件公正証書遺言を遺していること等からすれば,抗告人が被相続人の死亡時において,被相続人の遺産をすべてDが相続し自らには相続すべき財産はないと信じたことについて,相当の理由があったものと認めることができる。
また,上記認定の事実によれば,抗告人は,被相続人の遺産に相続債務が存在することを知らず,平成19年2月28日に別件訴訟事件の訴状を受け取って初めて本件債務の存在を知ったことが認められるとともに,本件債務が,Dの夫が代表取締役を務める会社の取引銀行に対する債務を主債務とする連帯保証債務であることや,抗告人,被相続人,D及びその夫の居住関係及び交際状況等に鑑みれば,抗告人が被相続人の上記債務の存在を知り得るような日常生活にはなかったものと推認されることなどからすれば,抗告人が上記の時点まで本件債務の存在を認識しなかったことについても,相当な理由があったものと認めることができる。
そうすると,本件における熟慮期間の起算日は,抗告人が別件訴訟事件の訴状を受け取って本件債務の存在を知った日である平成19年2月28日と解するのが相当である。
3 以上からすれば,平成19年3月14日に行った抗告人の本件相続放棄の申述は,未だ熟慮期間内の申立てであるから,これを受理するのが相当である。
④東京高裁平成19年8月10日決定
抗告人は,平成18年4月20日,その親族が本件相続財産の登記事項全部事項証明書を入手したことにより,同相続財産には,平成11年×月×日,極度額××万円の根抵当権設定の仮登記(権利者株式会社○○○)がなされていることを知った。そこで,抗告人の長男であるDが弁護士Iに依頼し,被相続人の債務を調査したところ,被相続人が債権者・根抵当権権利者を株式会社○○○とする債務につき,連帯保証(主債務者は自己破産)をしている事実が判明した。上記債務の残元本は平成13年時点で1200万円に達しており,超過利息の元本算入をしても,残元本の額は600万円を下回らない。(中略)
2 以上の事実によれば,抗告人は,平成5年×月×日,抗告人の夫Cの死亡に伴い遺産分割協議をし,被相続人が本件相続財産及び現金100万円を取得したことを知っていたもので,平成17年12月17日の被相続人の死亡という相続開始の原因たる事実を知った時点で,自己が相続人となったこと及び被相続人には本件相続財産が存していることを知っていたとみられる。
しかしながら,相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において上記のように信ずるについて相当な理由がある場合には,民法915条1項所定の期間は,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁)。そして,上記判例の趣旨は,本件のように,相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく,一方消極財産について全く存在しないと信じ,かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり,したがって,この場合の民法915条1項所定の期間は,相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。
これを本件についてみるに,抗告人は,平成17年12月17日の相続開始の時点で,被相続人には本件相続財産が存していることを知っていたが,本件相続財産にほとんど財産的価値がなく,一方被相続人に負債はないと信じていたものであり,かつ抗告人の年齢,被相続人と抗告人との交際状況等からみて,抗告人においてそのように信ずるについては相当な理由があり,抗告人が被相続人の相続債務の存在を知ったのは,早くとも平成18年4月20日以降とみられるから,本件の場合,民法915条1項所定の期間は,同日から起算するのが相当である。
そして,抗告人は,平成18年6月20日,本件相続放棄申述をしたものであるところ,上記申述は,上記の同年4月20日から3か月の熟慮期間内に行われたものであるから,適法なものというべきである。
⑤高松高裁平成20年3月5日決定
2 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないとされ(民法915条1項本文),上記3か月の熟慮期間については,相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となったことを覚知した時から起算するのが原則である。
本件においては,前記のとおり,抗告人はかつて被相続人と同居し,別居後も年に数度は被相続人と会っており,被相続人所有の宅地上に建築された被相続人及びDの共有する建物にはC及びDが被相続人とともに居住していたことからすれば,抗告人らは,被相続人の死亡により自己のために相続の開始があったことを知るとともに,被相続人が上記不動産(自宅敷地の所有権及び建物の共有持分権)を含む積極財産を有することを知っていたものと認められるから,熟慮期間の起算点は平成18年6月×日であるところ,抗告人が本件申立てをしたのは平成19年11月×日であって,それまでに既に3か月の期間が経過していることは明らかである。
しかしながら,相続人が,自己のために開始した相続につき単純若しくは限定の承認をするか又は放棄をするかの決定をする際の最も重要な要素である遺産の構成,とりわけ被相続人の消極財産の状態について,熟慮期間内に調査を尽くしたにもかかわらず,被相続人の債権者からの誤った回答により,相続債務が存在しないものと信じたため,限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間を経過するなどしてしまった場合には,相続人において,遺産の構成につき錯誤に陥っており,そのために上記調査終了後更に相続財産の状態につき調査をしてその結果に基づき相続につき限定承認又は放棄をするかどうかの検討をすることを期待することは事実上不可能であったということができるから,熟慮期間が設けられた趣旨に照らし,上記錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときには,相続人において,上記錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の期間内に,錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることができると解するのが相当である。なお,最高裁昭和57年(オ)第82号同59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁は,本件と事案を異にするものであり,前記のように解しても上記判例と抵触するものではない。
これを本件についてみると,前記のとおり,Dは,被相続人死亡後間もない時期に本件農協○○支所を訪れて被相続人の本件農協に対する債務の存否を尋ね,同債務は存在しない旨の回答を得,そこで,抗告人らは本件農協における被相続人名義の普通貯金の解約や出資証券の払戻しの手続を執るなどしたものであるが,それは,抗告人らにおいて同債務が存在しないものと信じたことによるものであり,それゆえに,抗告人らは被相続人死亡時から3か月以内に限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることもなかったものと認められる。
こうした事情に照らせば,抗告人らは本来の熟慮期間内に被相続人の本件農協に対する債務の有無及び内容につき調査を尽くしたにもかかわらず,本件農協の誤った回答により同債務が存在しないと信じたものであって,後に本件農協からの通知により判明した被相続人の本件農協に対する保証債務の額が残元金7500万円余という巨額なものであることからすれば,上記のような抗告人らの被相続人の遺産の構成に関する錯誤は要素の錯誤に当たるというべきである。
そうすると,抗告人は,錯誤を理由として上記財産処分及び熟慮期間経過による法定単純承認の効果を否定して改めて相続放棄の申述受理の申立てをすることができるというべきであって,抗告人が平成19年9月×日ころに本件農協からの通知を受けて被相続人の債務の存在を知った時から起算して3か月の熟慮期間内にされた本件の相続放棄の申述受理の申立ては適法なものとしてこれを受理するのが相当である。
3.起算点の繰り下げが認められなかったケース
①仙台高裁平成4年6月8日決定
抗告の理由2は要するに、抗告人らの熟慮期間の起算日は、抗告人らがその主張する交通事故に基づく損害賠償請求の訴状の送達を受けた日、すなわち平成三年九月一九日である、というのである。
しかしながら、熟慮期間は、抗告人らも引用する最高裁判所判決(民集三八巻六号六九八頁)の判示のとおり、原則として、相続人が、相続開始の原因となった事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきであるが、例外的に、相続人が上記事実を知った場合であっても、上記事実を知った時から三箇月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産(積極及び消極財産)が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があるときには、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべきものと解するのが相当であり、相続人が相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知った時既に積極であれ消極であれ相続財産の一部の存在でも認識し又は通常であれば認識しうべかりし場合は、熟慮期間の起算点を繰り下げる余地は生じないのである。
記録によれば、原審判が認定する本件の事実関係は、優にこれを認めることができ、この事実関係の下においては、本件の熟慮期間の起算日は、抗告人らにおいて被相続人小野新作が死亡したことを知った平成三年二月二一日であるというべきであり、本件相続放棄の申述が受付けられたのは平成三年一〇月二九日であること記録上明らかであるから、本件相続放棄の申述は民法九一五条一項に定められた期間を経過した後になされたことが明らかである(原審判が、損害賠償債務について説示する部分は、付加的理由として説示していることが明らかである。)。
②高松高裁平成13年1月10日決定
抗告人は、平成12年11月20日まで被相続人に高額の相続債務が存在することを知らず、そのことに相当な理由があるから、民法915条1項所定の熟慮期間は同日から起算すべきである旨主張する。
しかし、民法915条1項所定の熟慮期間は、遅くとも相続人が相続すべき積極及び消極財産(相続財産)の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭和59年4月27日・民集38巻6号698頁)。
そして、前示1引用の原審判理由説示及び一件記録によると、抗告人は、被相続人の死亡をその当日に知り、それ以前に被相続人の相続財産として、宅地約68.83平方メートル、建物約56.30平方メートル、預金15万円があることを知っていたといえるから、抗告人は被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえる。
そうすると、民法915条1項所定の熟慮期間は、被相続人の死亡の日である平成9年3月6日から3か月であるといえるから、同期間経過後になされた本件相続放棄の申述は不適法である。
③東京高裁平成14年1月16日決定
(1) 抗告人らは、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において相続債務が存在しないか、あるいは、相続放棄の手続をとる必要をみない程度に少額にすぎないと誤信したためであって、かつ、そのように信ずるにつき相当の理由がある場合には、相続債務のほぼ全容を認識したとき又は通常これを認識すべきときから起算すべきものと解するのが相当であるとして、本件の場合の民法915条所定の熟慮期間の起算点は、被相続人の債権者である株式会社A 銀行から抗告人らが訴えにより初めて請求を受けた日である平成13年8月24日(抗告人X2については同月25日)とすべきであると主張する。
(2) しかしながら、相続の承認又は放棄に係る3か月の熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであり、相続人が上記各事実を知った場合であっても、その時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった原因が、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において自己が相続すべき遺産がないと信じたためであり、かつ、そのように信じるについて相当な理由があると認められるときには、当該熟慮期間は相続人が自己が相続すべき財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。
これを本件についてみるに、抗告人らは、被相続人が死亡した直後である平成10年1月9日ころ、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議し、これを長男である抗告人X3に単独取得させる旨を合意し、同抗告人を除く他の抗告人らは、各相続分不存在証明書に署名押印しているのであるから、抗告人らは、遅くとも同日ころまでには、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、抗告人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。
抗告人らは、要するに、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて、相続の開始を知ったといえる旨を主張するものと解されるが、独自の見解であり、採用することはできない。
(3) そうすると、本件において、抗告人らは、遅くとも、遺産分割協議をした平成10年1月9日ころまでには、被相続人の遺産の存在を認識し、自己のために相続の開始があったことを知ったといわざるを得ないから、民法915条所定の3か月の熟慮期間は、同日の翌日を起算日として計算すべきであり、抗告人らがした平成13年10月24日付けの本件各相続放棄の申述は、明らかに熟慮期間を経過した後にされたものである。
4.まとめ
以上のとおり、裁判例を概観すると、相続人が相続財産の一部の存在を知っていたようなケースにおいては相続放棄を認めるか否かについて、結論が分かれており、実務上の見解が固まっているわけではないという見方もできるところです。
そのため、相続人としては、相続開始の事実を知り、かつ、自分が相続人になったことを知った以上は、相続財産が存在しないだろうと安易に決めつけずに、3か月以内に十分な相続財産の調査を行うことが重要といえるでしょう。
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【相続】相続放棄の熟慮期間の起算点~あとから借金が判明したような場合にどうすればいいか?~
1.はじめに
前回の記事で、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければならないということを説明しました。
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは具体的にいつなのでしょうか?
2.原則論
判例(大審院大正15年8月3日決定)は、「相続の開始を知った時」を次のように解釈しました。
①相続開始の原因事実の発生を知り
かつ
②このため自己が相続人となったことを覚知した時
①相続開始の原因事実の発生を知った時とは、被相続人の死亡または失踪宣告を知った時を指します。
また、②このため自己が相続人となったことを覚知した時については、相続人たる法定順位にある者が相続開始の原因事実の発生を知ったときは、原則として、自己が相続人になったことを覚知したものと認定するのが相当とされています(大審院大正15年8月3日決定)。
つまり、被相続人が死亡したことを知ったときには原則として自分が相続人になったことを知ったと認定されるということです。
原則として、①の時期(死亡の事実を知った時)=②の時期(自分が相続人になったことを知った時)ということになります。
そして、この解釈が原則論としてその後の実務において定着しました。
3.原則論に潜む問題(原則論修正の必要性)
上記のとおり、①相続開始の原因事実の発生を知り、かつ②このため自己が相続人となったことを覚知した時が相続放棄の熟慮期間の起算点の原則です。
しかし、この原則論を貫くと、相続開始の事実と自分が相続人になった事実を知った時から3か月が経過した後に、被相続人に多額の借金が発覚したというような場合に相続放棄ができないということになります。
これでは、相続人は予期せぬ借金を背負い込むことになりかねません。
実際、貸金業者の中にはあえて被相続人の死亡後3か月以上が経ってから相続人に請求を行う業者もあったようです。
そこで、裁判所は相続放棄の熟慮期間の起算点を繰り下げるという形で救済を図ることとなりました。
最高裁判所は次のように判示し、この問題について解釈を確立させました。
最高裁昭和59年4月27日判決
※下線は当事務所によるもの
【事案の概要】
相続人が、被相続人の死亡から約1年後に同人に保証債務が存在することを知り、裁判所に対して相続放棄の申述をしました。
【判旨】
民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(以下「熱慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、原審が適法に確定した事実及び本件記録上明らかな事実は、次のとおりである。
1 第一審被告亡大西増治郎(以下「亡増治郎」という。)は、昭和五二年七月二五日、上告人との間で、浅野さくの上告人に対する一〇〇〇万円の準消費貸借契約上の債務につき、本件連帯保証契約を締結した。
2 本件の第一審裁判所は、昭和五五年二月二二日、上告人が亡増治郎に対して本件連帯保証債務の履行を求める本訴請求を全部認容する旨の判決を言い渡したが、亡増治郎が右判決正本の送達前の同年三月五日に死亡したため、本件訴訟手続は中断した。そこで、上告代理人が同年七月二八日に受継の申立をしたが、第一審裁判所は、昭和五六年二月九日亡増治郎の相続人である被上告人らにつき本件訴訟手続の受継決定をしたうえ、被上告人大西収に対して同年二月一二日に、被上告人大西操子に対して同月一三日に、被上告人大西茂子に対して同年三月二日に、それぞれ右受継申立書及び受継決定正本とともに第一審判決正本を送達した。もつとも、被上告人大西茂子は、同年二月一四日に被上告人大西操子から右送達の事実を知らされていた。
3 ところで、亡増治郎の一家は、同人が定職に就かずにギャンブルに熱中し家庭内のいさかいが絶えなかつたため、昭和四一年春に被上告人大西収が家出し、昭和四二年秋には亡増治郎の妻が被上告人大西操子、同大西茂子を連れて家出して、以後は被上告人らと亡増治郎との間に親子間の交渉が全く途絶え、約一〇年間も経過したのちに本件連帯保証契約が締結された。その後、亡増治郎は、生活保護を受けながら独身で生活していたが、本件訴訟が第一審に係属中の昭和五四年夏、医療扶助を受けて病院に入院し、昭和五五年三月五日病院で死亡した。被上告人大西収は、同人の死に立ち会い、また、被上告人大西操子、同大西茂子も右同日あるいはその翌日に亡増治郎の死亡を知らされた。しかし、被上告人大西収は、民生委員から亡増治郎の入院を知らされ、三回ほど亡増治郎を見舞つたが、その際、同人からその資産や負債について説明を受けたことがなく、本件訴訟が係属していることも知らされないでいた。当時、亡増治郎には相続すべき積極財産が全くなく、亡増治郎の葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられた事情にあり、被上告人らは、亡増治郎が本件連帯保証債務を負担していることを知らなかつたため、相続に関しなんらかの手続をとる必要があることなど全く念頭になかった。ところが、被上告人らは、その後約一年を経過したのちに、前記のとおり、第一審判決正本の送達を受けて初めて本件連帯保証債務の存在を知つた。
4 そこで、被上告人らは、第一審判決に対して控訴の申立をする一方、昭和五六年二月二六日大阪家庭裁判所に相続放棄の申述をし、同年四月一七日同裁判所はこれを受理した。
右事実関係のもとにおいては、被上告人らは、亡増治郎の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつた事実を知つた当時、亡増治郎の相続財産が全く存在しないと信じ、そのために右各事実を知つた時から起算して三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、民法九一五条一項本文の熟慮期間は、被上告人らが本件連帯保証債務の存在を認識した昭和五六年二月一二日ないし同月一四日から起算されるものと解すべきであり、したがつて、被上告人らが同月二六日にした本件相続放棄の申述は熟慮期間内に適法にされたものであつて、これに基づく申述受理もまた適法なものというべきである。それゆえ、被上告人らは、本件連帯保証債務を承継していないことに帰するから、上告人の本訴請求は理由がないといわなければならない。
最高裁判所は、相続人が相続開始の原因事実の発生を知り、このために自己が相続人になったことを覚知していても、相続財産に含まれる債務の存在を知らなかった場合には、熟慮期間の起算点を繰り下げる余地があるとの判断を示しました。
この最高裁の判断によって、相続人に落ち度がなく相続財産を調査しきれなかった時には、その相続財産(債務)の存在を知った段階で初めて「自己のために相続の開始があったことを知った」ということになりうるという解釈が確立されることとなりました。
4.上記最高裁判例を読み解く際の注意点
上記のとおり、最高裁は「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、(中略)相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、(中略)熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」としています。
つまり、この判例を厳格に適用すれば、被相続人に相続財産が少しでも存在することを知っていた場合や、相続財産の調査を相続人に期待することが著しく困難だったとまではいえないような場合には、熟慮期間の起算点の繰り下げは認められないということになります。
現に、最高裁判所判例解説においても「一律に、相続財産についての認識がない以上熟慮期間は進行しないという考え方によるべきものとすると、著しく法的安定性を害するおそれがあるし、また、相続財産の調査を怠って相続財産がないものと軽信し、漫然と3か月の期間を徒過した者まで救済の対象となってしまうので、右の考え方を何らの限定もつけずに採用することは妥当ではない」とされているところです(最判解説昭和59年度188頁)。
そのため、安易に相続放棄の熟慮期間の起算点が繰り下げられると考えるべきではないといえるでしょう。
次回以降では、実際に起算点の繰り下げが認められたケースと認められなかったケースを紹介したいと思います。
続きを読む
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【大阪の相続弁護士が教える】徹底解説・相続放棄の熟慮期間~期間満了日が休日の場合はどうする?~
1.相続放棄の熟慮期間とは?
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければならないとされています(民法915条1号)。
この3か月という期間のことを「熟慮期間」といいます。
上記のとおり、民法においては「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と規定されていることから、相続人が、亡くなった方(被相続人)の死亡の事実を知らなかったときや、自分が相続人であることさえ知らなかったときなどは、熟慮期間は進行しません。
つまり、被相続人の死亡した日から3か月以上経過していても相続放棄ができる場合もあるということになります。
たとえば、1月1日に被相続人が死亡し、相続人であるAさんは2月15日に被相続人が死亡したことを知り自分が相続人であることを認識しました。現在は4月15日というケースがあったとします。
この場合、被相続人の死亡日からはすでに3か月以上が経っていますが、Aさんが相続開始の事実を知ってからはまだ3か月が経過していませんので、相続放棄できるということになります。
2.熟慮期間の具体例~いつからいつまで?~
具体例を挙げてもう少し細かく説明してみたいと思います。
たとえば、1月1日に被相続人が死亡したとして、被相続人の実子であるBさんはこの日に被相続人を見取りました。つまり、1月1日にBさんは相続開始の事実を知ったということになります。
この場合、3か月の熟慮期間は一体いつからいつまでなんでしょうか?
熟慮期間の満了日は4月30日なのか5月1日なのか?それとも5月2日なのでしょうか??
この点について、民法には次のような規定があります。
民法140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
民法141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法140条によって初日は算入しないので、上記ケースの熟慮期間の起算日は1月2日ということになります(ただし、1月1日午前0時に死亡し、その時にBさんが相続開始の事実を知ったという場合であれば、民法140条ただし書の規定によって、熟慮期間の起算日は1月1日ということになります)。
そして、期間の末日の終了をもって満了となるので(民法141条)、熟慮期間の満了は1月2日から3か月後の4月1日午後12時(4月2日午前0時)になります。
よって、Bさんは1月2日から4月1日までの間に相続放棄の手続をしなければなりません。
3.期間満了日が休日の場合
では、期間満了日である4月1日が休日の場合はどうでしょうか?
このような場合についても民法に次のような規定があります。
民法142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
この規定だけを見てもよくわからないかもしれませんが、
原則:休日であっても期間は満了する
例外:休日に取引をしない慣習があれば、休日の翌日に満了する
ということだと理解していただければ問題ありません。
ただ、例外といっても、この例外にあたるケースが実際には多いと思います。
相続放棄に話を戻すと、まさにこの例外にあたる規定が家事事件手続法と民事訴訟法に存在します。
家事事件手続法34条
1 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
2 家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4 民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。
民事訴訟法95条
1 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
要するに、家事事件手続法34条4項が準用する民事訴訟法95条3項の規定によって、家事事件の一つである相続放棄事件においては、期間満了日が休日の場合には翌日が満了日になるということです。
先ほどのケースでいうと、4月1日が休日の場合には、その翌日である4月2日が休日でなければこの日(4月2日午後12時)が熟慮期間の満了日ということになります。
4.応当する日がない場合の注意点
もう少しだけ細かい話をしてみましょう。
たとえば、ある相続人が11月29日に相続開始の事実を知ったという場合、熟慮期間の起算点は11月30日となります。
11月30日から3か月を数えるとして、、、
2月には30日がないのでどうすればいいでしょうか?
2月28日を満了日とすればいいのか、それとも30日まであると仮定して、3月2日を満了日とするのでしょうか。
この点については、以下のような規定が存在します。
民法143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
この条文に照らすと、「起算日に応当する日」は2月30日ということになります。
しかし、2月30日は存在しませんので、ただし書が適用されることになり、2月末日つまり2月28日が満了日になるというわけです。
このように、相続放棄をするにあたっては3か月の熟慮期間がありますので、時間には余裕をもって手続を行いたいところです。
もっとも、相続放棄の手続に必要な戸籍謄本などの書類の収集に意外と時間がかかってしまうこともあります。
できる限りスピーディに手続を進めるためには弁護士などの専門家に依頼するのも一つの方法だと思います。
続きを読む
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【遺言・相続】当事務所の勝訴判決が新聞に掲載されました
当事務所が原告代理人を務めた事件で勝訴判決を得ることができ、神戸新聞に掲載されました。
☆ネットニュースはこちら
内容を簡単にご説明すると、公正証書遺言と自筆で書かれた遺言の2つがあり、その効力等が問題になった事件です。
遺言や相続の事件については、多数の解決実績がございますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】公正証書遺言のすすめ
遺言書には大きく分けて、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があるということを以前説明しました。
最も簡単な方法は、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言であれば、コストもほとんどかかりません。
ですが、自筆証書遺言には、厳格な要件が定まっており、それを一つでも欠けば無効な遺言になってしまいます。
また、自筆の場合、相続人間で、この遺言は偽造されたものだとか、相続人の一人に無理やり書かされたものだなどと争いになることもあります。
つまり、後々紛争になるリスクがあるということです。
さらに、紛失してしまうというリスクもあります。
この点、公正証書遺言であれば、公証役場で作成しますので要件を満たしていないということは通常ありえません。
偽造ということも普通はありえません。
また、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成しますので、基本的には遺言者の真意が反映されているといえるでしょう。
もちろん、公正証書遺言であっても後々紛争になるケースはありますが、自筆証書遺言に比べれば争いの種は少ないと思います。
ですから、せっかく遺言書を作るのであれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
ちなみに、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、偽造や破棄のおそれがあることから、実務的にはほぼ利用されていないというのが実際のところです。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】遺言の撤回の方法
遺言を作ってみたものの、後から内容をなかったことにしたいとか内容を変更したいというお気持ちになることもあると思います。
今回は、その方法についてご説明します。
民法では、遺言はいつでも撤回することができるとされています。
まず、撤回の方法の一つ目としては、新たに遺言を作成するというものです。
遺言を作り直すということですね。
たとえば、当初の遺言で、預金を相続人の1人であるAさんに相続させるとしていたとします。
その後、遺言を撤回したいと思い、後の遺言で、預金のすべてを他の相続人であるBさんに相続させるとしました。
これによって、当初の遺言でAさんに相続させると記載された部分は撤回されたものとみなされます。
ちなみに、抵触部分についてのみ撤回されたものとみなされますので、当初の遺言のうち、後の遺言と抵触していない部分は、効力を有することになります。
たとえば、当初の遺言で不動産はCさんに相続させると記載されていて、後の遺言に不動産のことは何も記載されていなければ、依然、その部分については当初の遺言が効力を持つということです。
遺言の撤回の方法の二つ目としては、遺言の内容と抵触する法律行為を行うというものです。
たとえば、遺言で不動産をAさんに相続させるとしていたけど、その後に不動産を売ってしまったと言うような場合は、不動産をAさんに相続させるという部分は撤回されたものとみなされるということです。
自筆証書遺言の場合、自分で書いた遺言を破棄してしまうというのも、撤回の方法の一つです。
これに対して、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、手元にある公正証書遺言の謄本を破いて捨てたとしても撤回にはなりません。
また、公証役場では本人であっても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
以上、遺言を撤回する方法についての説明でした。
当事務所では、以前作った遺言を見直したいというご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談にお越しください。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】養子の子どもに相続権はあるか?
こんなケースを考えてみましょう。
Aさん(70歳)には、妻B(67歳)と養子C(40歳)がいます。
養子Cには子どもD(10歳)がいます。
Aさんはふと疑問に思いました。
自分が亡くなったときの相続人は誰なんだろう?
これは、単純な問題です。
Aさんが亡くなったとき、相続人になるのは妻Bと養子Cということになります。
ですが、Aさんはさらに不安になりました。
自分が亡くなる前に、万が一養子Cが亡くなっていた場合、Cの子であるDが相続人になるんだろうか?
このように、相続人となることが予定されていた者が死亡したことによって、その者の子どもが相続人となることを代襲相続といいます。
つまり、DはAの代襲相続人になれるのか?という問題ということになります。
この問題については、場合分けが必要です。
Aさんと養子Cが養子縁組をした時期とDの出生の時期によって、結論が変わります。
まず、養子縁組をする前にDが出生していた場合、たとえば、Dが平成21年に生まれて、AとCの養子縁組は平成25年に行ったというような場合、Dに代襲相続権は発生しません。
これに対して、養子縁組後にDが出生していた場合には、出生時においてすでにAとCの血族関係が生じており、DはAの直系の孫ということになるので、代襲相続権が発生するということになります。
このように、養子縁組をした時期と養子の子の出生の時期によって、結論が全く異なりますので、注意が必要ですね。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】配偶者居住権とは何か?
配偶者の一方が死亡した場合、他方の配偶者は、自宅に引き続き居住したいと考えるのが一般的です。
特に高齢者である場合には、居住建物を変更するは精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となりかねません。
しかし、現行の民法では配偶者の居住権を保護する制度はありませんでした。
そこで、このたび民法が改正されることにより、配偶者にこれまで住んでいた自宅の使用を認めることを内容とする権利が与えられることになりました。
この権利を「配偶者居住権」といいます。
具体的には、①配偶者の居住権を保護するため、相続開始後も短期的・暫定的にこれまで居住していた被相続人の相続財産に属する自宅を使用できる権利(配偶者短期居住権)と、②当該自宅の帰属が決定した後も長期的・終身的に同建物を使用・収益できる権利(配偶者居住権)の2つの権利に分けられています。
①配偶者短期居住権と②配偶者居住権は、言葉はよく似ていますが、内容は異なります。
①配偶者短期居住権というのは、配偶者が、居住建物を取得した者に対して、相続発生後も引き続き暫定的に(少なくとも相続開始時から最低6か月は)居住建物を無償で使用することができる権利のことをいいます。
さらに、居住建物の遺産分割がまだまとまっていないのであれば、遺産分割が完了するまで居住建物を使用することができます。
②配偶者居住権とは、配偶者が、相続開始時に被相続人の相続財産に属する建物に居住していた場合に、当該配偶者を保護するため、当該建物の帰属が決定した後も長期的な(原則として終身の間)使用及び収益権を与えるという権利のことをいいます。
配偶者居住権は、被相続人の遺産分割後における、配偶者の終身的・長期的な居住権を明文化したものですので、配偶者保護に資する権利といえるでしょう。
ただし、配偶者居住権は、配偶者が遺産分割において取得すべき財産の額(具体的相続分額)に算入されることになりますので、具体的に配偶者居住権がいくらの金額と計算されるのかということが問題となります。
その計算の仕方は中々に複雑ですのでここでは割愛しますが、建物の賃料相当額が問題になりますので、これを正式に計算しようと思うと鑑定手続を経なければ算定困難となります。
そういった点から、配偶者居住権が使用されないのではないか懸念されているようです。
今後、この制度が定着するかは実務の推移を見る必要があると思います。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】嫡出子と非嫡出子は相続分が異なるか?
嫡出子というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。
一方で、非嫡出子というのは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
たとえば、Aという人が、正妻との間にBという子をもうけ、愛人との間にCという子をもうけたとします。
この場合、Bが嫡出子、Cが非嫡出子ということになります。
では、BとCの相続分は異なるのでしょうか?
実は、以前は民法の規定で、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とすると決められていました。
しかし、平成25年9月4日の最高裁決定でこの民法の規定が憲法に反するとの判断がされました。
これによって、嫡出子と非嫡出子の相続分に差はなくなり、上記の民法の規定も改正されることとなりました。
したがって、先ほどの例でいうと、BとCとの相続分は異ならないという結論になります。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】養子は実子と同じ相続分なのか?
自分は養子なんだけど、他の実子相続分の半分しか受け取れないのでしょうか?
という質問を受けることがあります。
この方の認識は正しいのでしょうか?
ある家族を例に考えてみましょう。
お亡くなりになった方(A)には妻B、実子C、養子Dがおり、遺言はのこされていませんでした。
Aの遺産としては、預金が2000万円ありました。
ここで、妻Bの相続分が2分の1ですので、Bは1000万円を相続することになります。
では、実子Cと養子Dの相続分はどうでしょうか?
実は、養子と実子には相続分に差はありません。
養子であっても、子どもであることには変わりありませんので、相続分には違いが出ることはないんです。
ですから、先ほどの例でいうと、実子Cと養子Dはそれぞれ4分の1の相続分があり、500万円ずつ相続するということになります。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【相続】誰が相続人になるか?
人が亡くなった場合、相続が発生します。
その結果、亡くなった人のことを被相続人、法律上相続する権利のある人のことを相続人といいます。
では、この相続人には誰がなるのでしょうか?
①配偶者(亡くなった者の妻又は夫)
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
②子(第1順位の相続人)
次に、被相続人の子は第1順位の相続人になります。
被相続人が亡くなったときにはまだ生まれていない胎児も含まれ、母体から産まれたときに相続人となる地位をえることになります。
子どもが相続開始前に亡くなっていた場合は、そのまた子ども(被相続人から見たら孫)が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
③直系尊属(第2順位の相続人)
直系尊属というのは、被相続人の父母、祖父母など、被相続人より上の世代のことを指します。
子や孫、ひ孫などで相続人なる者が1人もいないときに相続人になる者が1人もいないときに直系尊属が相続人になります。
④兄弟姉妹(第3順位の相続人)
第1順位、第2順位に該当する相続人が1人もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
このように、誰が相続人になるかということは、民法で明確に決められています。
相続が発生したときには、まず相続人を確定させなければなりませんが、相続人が多かったりすると、誰が相続人になるのかを探すだけでも大変な作業になることがあります。
誰が相続人になるのがが、よく分からないときは弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。