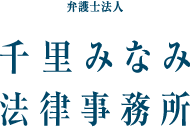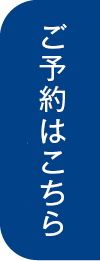【交通事故】平均余命の2分の1の端数は四捨五入?切り捨て?【逸失利益】
逸失利益の計算において、症状固定時の年齢が67歳を越える場合には、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
では、平均余命の2分の1に小数点以下の端数が生じた場合、これは四捨五入なのでしょうか、それとも切り捨てなのでしょうか。
例えば、令和4年版簡易生命表によると、70歳男性の平均余命は15.56年となっていますが、これを2分の1すると、7.78という数字が出てきます。
では、労働能力喪失期間は四捨五入して8年なのか、それとも端数を切り捨てて7年なのか、いずれが妥当なのでしょうか。
近時の裁判例をいくつか見てみることにしたいと思います。
【大阪地判令和5年4月18日】
(平均余命は18.78年という事案)
Aは死亡時66歳であったから、就労可能年数については平均余命の2分の1である9年とすべきであり、9年間に相当するライプニッツ係数は7.108(小数点第4位は四捨五入)となる。
⇒18.78年の2分の1は9.39であるところ、小数点以下を切り捨てた。
【名古屋地判令和4年5月27日】
(平均余命は5年という事案)
ウ 労働能力喪失期間
平均余命の2分の1に当たる2.5年(ライプニッツ係数2.291。計算式:1.859+(2.723-1.859)×1/2≒2.291)
⇒5年の2分の1は2.5であるところ、そのまま2.5という数字を採用した。
【鹿児島地鹿屋支判令和4年2月7日】
(平均余命は19.46年という事案)
前記のとおり,亡Aは本件事故による後遺障害によって就労することができなくなったと認められるところ,亡Aは症状固定時65歳であり,その逸失利益は,労働能力喪失期間を平均余命の2分の1として,平成27年の簡易生命表〈男〉を参照し,10年間(ライプニッツ係数7.7217)として算出するのが相当である。
⇒19.46年の2分の1は9.73年であるところ、小数点以下を四捨五入して10年とした。
【東京地判令和 3年7月8日】
(平均余命は20.35年という事案)
前記認定の原告の後遺障害の内容及び程度に照らすと,労働能力喪失率は14%,労働能力喪失期間は平均余命期間の2分の1である10年(対応するライプニッツ係数は7.7217)と認めるのが相当である。
⇒20.35年の2分の1は10.175年であるところ、小数点以下は切り捨てた。
【東京地判令和2年7月10日】
(平均余命は25.33年という事案)
原告X1は症状固定時の平均余命の2分の1(平成29年の簡易生命表【女】64歳の平均余命は25.33年)である12年間(対応ライプニッツ係数8.8633)の労働能力を喪失したと認める。
⇒25.33年の2分の1は12.665年であるが、小数点以下を切り捨てた(原告は13年と主張していた)。
【京都地判令和2年2月19日】
(平均余命は21.73年という事案)
Bの年齢における平均余命は21.73年とされているから(平成28年簡易生命表),家事労働者としての就労可能年数はその約2分の1に当たる11年間と認める(対応するライプニッツ係数は8.3064)。
⇒21.73年の2分の1は10.865年であるところ、小数点以下を四捨五入した。
【東京地判令和元年11月6日】
(平均余命は26.23年という事案)
亡Bの基礎収入は家事労働を前提に平成29年の60歳から64歳の女性の平均賃金325万0800円とし,平均余命26.23年の2分の1である13年(端数切捨て)にわたり就労可能であり(これに対応するライプニッツ係数は9.3936),生活費控除率は0.3とするのが相当である。
⇒26.23年の2分の1は13.115年であるところ、小数点以下を切り捨てた。
【名古屋地判令和元年9月25日】
(平均余命は14.19年という事案)
本件事故当時,亡Cは,72歳であったから,平成28年当時の平均余命は14年であった。したがって,逸失利益の喪失期間は,年金関係につき14年間,介護関係につき7年間と認めるのが相当である。
⇒14.19年の2分の1は7.095年であるところ、小数点以下を切り捨てた。
【大阪地判平成31年3月19日】
(平均余命は28.83年という事案)
家事労働に従事していたAの基礎収入を上記(3)の313万8400円とし,就労可能期間を平均余命の2分の1である14年(ライプニッツ係数9.8986)とし,生活費控除率は,女性の年齢別平均賃金を基礎収入としていること等に鑑み,30パーセントとするのが相当である。
⇒28.83年の2分の1は14.415年であるところ、小数点以下を切り捨てた。
【神戸地判平成31年1月16日】
(平均余命は35.72年という事案)
労働能力喪失期間は,症状固定時,原告が52歳であったことから,平均余命である35.72年(平成24年女性簡易生命表)の2分の1である17年(小数点以下切り捨て。対応するライプニッツ係数は11.2741)と認めるのが相当である。
⇒35.72年の2分の1は17.86年であるが、小数点以下を切り捨てた(原告は18年と主張していた)。
【京都地判平成30年9月14日】
(平均余命は26.51年という事案)
本件事故による死亡時から平均余命までの約26.51年間(平成24年簡易生命表)の約2分の1である13年間(75歳まで。対応するライプニッツ係数は9.3936である。)は就労する蓋然性があった。
⇒26.51年の2分の1は13.255年であるところ、小数点以下を切り捨てた。
【福島地判平成30年9月11日】
(平均余命は13.21年という事案)
平均余命が13.21年であること(平成26年簡易生命表・女・78歳)から,労働能力喪失期間としては平均余命の2分の1である6年とする。
⇒13.21年の2分の1は6.605年であるが、小数点以下を切り捨てた(ただし、原告自身、7年ではなく6年と主張したいたようである)。
【東京地判平成30年7月5日】
(平均余命は11.79年という事案)
亡Cは家事従事者であり,家事労働分の逸失利益については,平成28年賃金センサス学歴計・女・70歳以上の平均年収301万4800円を基礎収入とし,生活費控除率を4割として,平均余命11年の約2分の1に相当する5年(対応するライプニッツ係数は4.3294である。)にわたり就労可能であったものとして算定するのが相当である。
⇒11.79年の2分の1は5.895年であるが、小数点以下を切り捨てた(原告は6年と主張していた)。
以上、複数の裁判例を見てきましたが、四捨五入している事例もあれば、四捨五入すれば切り上げるはずであるところ、そうはせずに切り捨てている事例もあることが分かります(一方で、四捨五入すれば切り捨てるはずであるところを切り上げている事例は、上記裁判例の中にはありませんでした)。
【大阪の交通事故弁護士が教える】被害者に後遺障害が残った場合に、近親者にも慰謝料が認められるか?慰謝料額はどのくらい?
1.はじめに
交通事故によって後遺障害を負った場合、その被害者には後遺障害慰謝料が認められます。
後遺障害等級に応じた慰謝料の基準額は以下のとおりです(赤い本基準)。
・1級:2800万円
・2級:2370万円
・3級:1990万円
・4級:1670万円
・5級:1400万円
・6級:1180万円
・7級:1000万円
・8級:830万円
・9級:690万円
・10級:550万円
・11級:420万円
・12級:290万円
・13級:180万円
・14級:110万円
このように、後遺障害を負った被害者本人に対して慰謝料が認められるのは、いわば当然ともいえますが、被害者が後遺障害を負ったことで、その家族(近親者)も精神的苦痛を受けることが少なくありません。
では、被害者の家族は、その精神的苦痛を慰謝料という形で加害者に請求することはできるのでしょうか。
2.近親者の慰謝料請求が認められる場合
近親者の慰謝料請求については、民法711条に規定があります。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
この規定によれば、被害者が死亡した場合に限り、近親者の慰謝料請求が認められるように思われます。
しかし、最高裁は、次のとおり、被害者が死亡した場合でなくとも、近親者の慰謝料請求が認められる余地があることを示しました。
死亡の場合でなくとも、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求が認められる。
(最判昭和33年8月5日民集12巻12号1901頁)
このように、被害者が死亡した場合に並ぶほどの精神的苦痛を近親者が受けたときは、近親者自身の慰謝料が認められることになりますが、一般に被害者に重度の後遺障害が残った場合に近親者にも別途慰謝料請求権が認められると考えられています(2024年版・赤い本(上巻)234頁)。
具体的には、後遺障害等級1級~3級の事案であれば、基本的に近親者の慰謝料請求が認められ、後遺障害等級4級以下の事案については「当該行為障害により近親者がいかなる苦痛(特に介護の負担や生活の変化)を受けるかにより個別に判断されている。」と説明する文献があります(『交通賠償のチェックポイント』弘文堂146頁)。
その他の文献では、「実務では、被害者の後遺障害等級が高いものについては認められる傾向にあり、1級又は2級の場合は通常肯定、3級事案でも工程が多くみられ、4級以下では事案に応じて肯定事例、否定事例が存在しています。」と説明するものもあります(『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規234頁)。
3.近親者の慰謝料の額はどのくらいになるか?
近親者自身の慰謝料が認められるとして、その額はどの程度になるのでしょうか。
この点に関しては、一定の目安はなく、裁判官の個別判断に任されているものの、後遺障害等級1級の事案においては、被害者本人の後遺障害慰謝料額の5~20%程度が多く、30%以上はなかなか認定されないと説明されています(2016年版赤い本(下巻)102-104頁)。
後遺障害等級1級の後遺障害慰謝料の基準額は、前述のとおり2800万円ですから、その5%であれば140万円、20%であれば560万円ということになります。
また、後遺障害等級2級の事案については、「1級の事案ほど近親者固有分が当然のように認定されているわけではないが、認定される場合には、200万円~300万円、あるいはその水準を超える慰謝料額の積み上げがなされているという印象である」とされています(同上104頁)。
4.慰謝料請求が認められる「近親者」とはどのような人を指すのか?
ここまで「近親者」の慰謝料請求という言葉を使ってきましたが、この「近親者」というのは、被害者とどのような関係のある人を指すのでしょうか。
この点、前述した民法711条には「被害者の父母、配偶者及び子」と規定されていますが、最高裁は次のように判示して、必ずしもこれらの者に限定しないことを明らかにしました。
不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法七一一条が明文をもつて認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。
(最判昭和49年12月17日民集28巻10号2040頁)
つまり、被害者の父母、配偶者及び子と実質的に同視し得る身分関係があり、甚大な精神的苦痛を受けた者については、固有の慰謝料請求が認められるということになります。
実際の裁判例に目を向けると、以下のとおり、「被害者の父母、配偶者及び子」以外の身分関係のある人についても、固有の慰謝料が認められているものがあることがわかります。
・胸髄損傷による両下肢麻痺等(後遺障害1級)の会社員男性が被害者となった事案において、法律上の母ではないが、将来にわたって介護にあたることとなる事実上の母に、250万円の慰謝料を認めた事例(仙台地判平成23年9月9日自保ジ1870号11頁)
・遷延性意識障害(後遺障害等級1級)の中学生が被害者となった事案において、被害者の姉と兄に各200万円の慰謝料を認めた事例(神戸地伊丹支判平成30年11月27日自保ジ2039号1頁)
・被害者である中学生が死亡した事案において、被害者と同居していた、被害者の父母、祖父母、姉2人、妹にそれぞれ固有の慰謝料を認めた事例(宇都宮地判平成23年3月30日判時2115号83頁)。※認容額は父母が各250万円(計500万円)、祖父母、姉2人、妹が各120万円(合計600万円)であった。
・被害者が頚髄損傷等(後遺障害等級1級)を負った事案において、将来被害者の介護にあたる予定の弟に300万円の固有の慰謝料を認めた事例(名古屋地判平成24年10月26日交民45巻5号1314頁)
5.まとめ
以上のとおり、被害者が死亡した事案だけでなく、被害者が後遺障害(特に重度の後遺障害)を負った事案においても、近親者に固有の慰謝料が認められることがあります。
そして、固有の慰謝料が認容される場合、その額は決して小さいものとはいえません。
したがって、被害者が重度の後遺障害を負ったような場合には、この近親者固有の慰謝料請求を請求対象から漏らすことのないように注意が必要です。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【大阪の離婚弁護士が教える】別居中に妻が夫名義の車を運転して事故を起こした場合、夫も責任を負うか
1.はじめに
今回は離婚と交通事故という二つの分野にまたがるテーマについて解説してみたいと思います。
実務上、夫婦が別居しており、離婚協議中あるいは離婚調停中という状況下においても、妻が夫名義の車を利用しているということがあります。
この場合、妻が交通事故を起こすと、夫も責任を負うことになるのかということについて見ていきたいと思います。
※以下では、夫名義の車を妻が運転したケースを想定して解説をしていますが、妻名義の車を夫が運転したというケースでは、「夫」と「妻」の表記は入れ替わりますので、その点ご注意ください。
2.夫の運行供用者責任
たとえば、別居後も妻が夫名義の車を使用している状況下で、妻が人身事故を起こしたとします。
この場合、事故の被害者は、通常は、車を運転していた妻に対して損害賠償請求を行うことになりますが、それだけではなく車の所有者である夫に対しても損害賠償請求ができるのでしょうか。
夫からすれば、妻とは離婚を前提に別居をしていることから、妻が起こした事故によって自分が責任を負うことには納得できないという思いを抱いてもおかしくありません。
しかし、夫は運行供用者責任(自賠法3条)を負う可能性があり、そうなると事故の被害者は夫にも損害賠償請求をすることができるということになります。
つまり、妻が起こした事故であっても、車の所有者である夫はその事故の責任を負う可能性があるということになります。
3.夫が責任を回避できる場合はあるか
運行供用者責任が問題となる類型としては、①泥棒運転、②無承諾運転、③詐取的な利用・所有者等の意思に反して借り受け人が返還しない場合、④名義残りの場合などがあるといわれています(以下、参考文献として、藤村和夫ほか編著『実務交通事故訴訟体系 第2巻』41頁~45頁)。
① 泥棒運転
盗難にあった車が、所有者等使用権者の意思に基づかない運行によって人身事故を起こした場合には、一般的には所有者等使用権者は運行供用者責任は負わないとされます。
しかし、実務上は、所有者等使用権者の管理に過失がある場合には、事故発生が盗難直後の比較的短時間内であり、盗難前にあった場所とそれほど離れていない場合には、所有者等使用権者の運行供用者責任が肯定される場合があります(※こちらの記事もご参照ください)。
別居中に妻が夫名義の車を盗難したという事例は想定し難く、仮に夫が妻に車を盗難されたと主張したとしても、両者には夫婦という人的関係があることから、この類型によって運行供用者責任が否定されることは困難といえそうです。
② 無承諾運転
所有者等使用権者と親族関係・雇用関係等の密接な関係がある当事者が、無断で運転した場合には、所有者等使用権者が当該運転行為を承諾していない場合でも、所有者等使用権者の運行供用者責任は肯定される傾向にあります。
したがって、夫の承諾を得ることなく、妻が勝手に運転したという場合であっても、夫に運行供用者責任が認められるということになりそうです。
③ 詐取的な利用・所有者等の意思に反して借受人が返還しない場合
前述した参考文献には次のような記載があります。
すぐ返すからと言って借り出した自動車を、返還請求しても借主が言を左右にして返還しない場合、あるいは、レンタカーを借りた者が返還期限を過ぎてもなかなか返さず、連絡もできない状態になってしまう場合、貸主の運行供用者責任が否定されるのは難しいであろう。しかし、当初は任意に引き渡したものの、所有者等の意思に反して返還しようとしない態度が明白になった状態では、所有権等使用権者の立場は無視され奪われたに等しいから、自分の目的のために使っている状態は消滅したとすべき場合もあると思われる。ただ、このような状態だと評価されるためには、引渡し後ないしは返還期限から相当期間経過していることが必要であろう。また、所有者等使用権者が、当該自動車の返還要求を明確な形で行い、借りた側がその意向を無視していることが明らかな状態になっている必要がある。そこまでの心証がとれない状態の場合は、所有者等使用権者の運行供用者としての立場が消滅しているとはできないと考えるべきである。
この説明を前提にすると、夫が妻に対して、車の返還を明確に求めているにもかかわらず、妻が相当期間返還に応じないというような場合には、夫は運行供用者責任を免れる可能性があるかもしれません。
④ 名義残りの場合
自動車を他の者に譲渡したものの、自動車登録上の所有名義の変更手続をとっていない場合(いわゆる「名義残り」)における形式的所有名義人については、運行供用者ではないとされるのが、判例の傾向であって、代金が未払いのまま曖昧な利用関係が継続しているなど売買当事者間に特別な関係がある場合には例外的に旧所有者の責任が肯定されるといわれています。
そうすると、すでに夫婦間で夫名義の車を妻に譲渡するという合意ができているものの、名義変更の手続きがなされていないにすぎない状態の場合であれば、夫の運行供用者責任が否定される可能性がありそうです。
4.できる限り早めの名義変更を
以上のとおり、夫が運行供用者責任を回避できるケースは限定的であろうと思われます。
実際、全く面識のない者が運転して起こした事故であっても、車の所有者が運行供用者責任を負うとした事例もあり(最判平成20年9月12日判タ1280・110)、運行供用者責任は比較的広く認められています。
仮に離婚協議中・離婚協議中に妻が夫名義の車で事故を起こしたことで、夫も責任を負うとなれば、当事者間の紛争は激化・長期化することにもなりかねません。
そこで、万が一の事故に備えて、もし離婚後も妻が車を使用することで合意ができているのであれば、離婚を待たずに車の名義変更等を行い、車に関しては財産分与を先行して処理してしまうという方法も検討の余地があります。
この場合、自動車保険も夫が契約者となっていることが多いと思われますので、自動車保険の名義変更もあわせて検討してみてください。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の交通事故弁護士が教える】人身傷害保険を利用した場合の過失相殺と損益相殺(既払金)の順序
1.はじめに
人身傷害保険とは、保険加入自身や同乗者の治療費、休業損害等を負担してくれる保険のことをいいます。
つまり、自分が加入している保険を利用して、自分が受けた損害の補償を受けることができる保険というわけです。
人身傷害保険に加入している場合、事故の相手方が加入している任意保険と自分自身が加入している人身傷害保険の両方を利用するというケースがよくあります。
今回は、人身傷害保険を利用した場合に問題となる、過失相殺と損益相殺の順序について解説したいと思います。
2.解説
Aさんが自動車を運転していた際に、Bさんの運転する車と衝突し、Aさんは怪我をしました。
過失割合はAさん:Bさん=30:70で、Aさんの損害の総額は500万円でした。
つまり、Aさんの過失割合部分は150万円(500万円×30%)で、Bさんの加入する保険会社(以下「B保険会社」といいます。)に対して請求できるのは350万円(500万円×70%)ということになります。
①人身傷害保険の利用がない場合
すでにAさんはB保険会社から既払金180万円を受けていたとします。
すると、人身傷害保険の利用がない、いわば通常の事例の場合は、今後AさんがB保険会社から受け取る金額は、以下の計算式のとおり、170万円ということになります。
(計算式)
500万円×70%(過失相殺)-既払金180万円(損益相殺)=170万円
つまり、通常の事例の場合は過失相殺をした後に損益相殺を行うという計算をするというわけです。
そして、トータルでAさんはB保険会社から350万円(既払金180万円+その後にB保険会社から支払われた170万円)の支払いを受けたということになります。
②人身傷害保険が利用できる場合
では、人身傷害保険が利用できる場合はどうでしょうか。
上記と同様の事例で、人身傷害保険の保険会社(以下「A保険会社」といいます。)から治療費180万円がすでに支払われていたとします。
仮に、上記①と同じ計算方法をとるとすれば、AさんがB保険会社から受け取ることができる金額は170万円ということになりそうです。
しかし、それではAさんが受け取ることができた総額は結局350万円(人身傷害保険から180万円+B保険会社から170万円)ということになるので、人身傷害保険に加入しているか否かにかかわらず、受け取ることができる総額に違いがないということになり、人身傷害保険に加入しているメリットがないようにも思います。
この点については、かつては実務上の見解の争いがありましたが、最高裁判例(平成24年2月20日)が出されたことで、現在においては人身傷害保険からの既払金がある場合には、まず優先的に当事者の過失割合部分に充当さるという処理がなされるということで見解が統一されることとなりました(この見解のことを「訴訟基準差額説」といいます)。
上記の例でいうと、まずA保険会社の人身傷害保険からの既払金180万円は、Aさんの過失割合部分150万円に充当され、残り30万円はB保険会社に対して本来請求すべき350万円に充当されることになります。
そして、Aさんは残る320万円(350万円-30万円)をB保険会社に請求すれば、最終的には損害額500万円全額を受領することができるという形になります。
このように、人身傷害保険を利用できる場合には、利用できない場合に比べてより多くの賠償額を得ることができることがあるというわけです。
3.最高裁判例をどう読み解いたらいいの?
ここからは弁護士向けの解説です。
上記では、「人身傷害保険からの既払金がある場合には、まず優先的に当事者の過失割合部分に充当さるという処理がなされる」とさらっと書きましたが、最高裁平成24年2月20日判決は人身傷害保険に基づき保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲等が争われた事案です。
そうすると、上記最高裁判決の判示内容からどういうロジックで「人身傷害保険からの既払金がある場合には、まず優先的に当事者の過失割合部分に充当さるという処理がなされる」という帰結が導かれるのかという点が気になるところです。
そこで、判示内容を見てみることにしましょう。
ポイントになる判示は以下の部分です。
上記保険金を支払った訴外保険会社は,保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように,上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。
これだけを読んでも何を言っているのかよくわからないので、これを先ほどの例にあてはめて読んでみましょう。
A保険会社は,Aさんに裁判基準損害額に相当する額が確保されるように,上記保険金の額(180万円)とAさんのBさんに対する過失相殺後の損害賠償請求権の額(350万円)との合計額(530万円)が裁判基準損害額(500万円)を上回る場合に限り,その上回る部分(30万円)に相当する額の範囲でAさんのBさんに対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。
これでだいぶ読みやすくなったのではないでしょうか。
つまり、この判例は、人身傷害保険の保険会社より支払われた保険金は、損害額のうち、被害者の過失割合に相当する部分にまず充当され、残額が加害者の過失割合に相当する部分に充当されると考えているという風に読み取れるというわけです。
ここで、より理解を深めるべく、原審の取った見解も見てみることにしましょう。
原審は絶対説と呼ばれる見解、すなわち、人身傷害保険の保険会社は支払った人身傷害保険金額全額に相当する損害賠償請求権を代位取得するという見解をとっていました。
つまり、原審の考え方を前提にすると、A保険会社は180万円全額についてAさんの持っていた損害賠償請求権を代位取得するということになるわけです。
「代位取得」と言う以上、もともとAさんがB(B保険会社)に対して持っていた損害賠償請求権を代わりに取得にするということですね。
つまり、絶対説は、AさんがB(B保険会社)に対して持っていた350万円の損害賠償請求権のうち180万円が代位取得の対象になると考えているということになります。
そして、結局180万円はA保険会社がAさんに代位してB(B保険会社)に請求(回収)するわけなので、人身傷害保険によって賄われたというよりは、B保険会社が支払ったのと変わらない結果となるわけです。
したがって、絶対説によると、結局Aさんは人身傷害保険を利用したものの、最終的に受け取ることができる金額は、上記①の人身傷害保険を利用しない場合と同様の350万円(A保険会社から180万円+B保険会社から170万円)ということになります(そして、A保険会社は180万円をB(B保険会社)に対して代位請求するという格好になります)。
これに対して最高裁のとった訴訟基準差額説は、A保険会社がAさんの損害賠償請求権を代位取得するのは30万円だけとされるので、反対に言うとAさんの過失割合部分150万円は、人身傷害保険によって全額賄われるという形になるのです。
つまり、最高裁の結論の方がより被害者に有利な考え方ということがいえますね。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【大阪の交通事故弁護士が教える】会社役員の休業損害が認められるのはどのような場合?
1.はじめに
休業損害とは、被害者が事故を原因とした受傷により、治療又は療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、本来得られるはずの収入を得ることができなかったことによる損害のことをいいます。
つまり、休業損害が認められるためには、基本的には、現に休業し、減収が生じていることが必要とされており、損害額は休業期間中の現実の収入減をもって認定されることになります。
この点、会社役員の場合、会社との委任契約に基づいて報酬が支払われるところ、給与とは異なって休業したからといって直ちに全額を減額されるものではありません。
そういった特殊性があることから「会社役員の休業損害」という論点が問題となるわけです。
しかし、この問題に関する議論や解説を読んでいても、労務対価性がどうとか、利益配当部分がどうとか、企業損害が・・・など、とにかく分かりにくいというのが正直なところです。
まるで会社役員の場合であっても、無条件で休業損害が認められて当然というような書き方をしているサイトなどがあることも混乱の原因かもしれません。
そこで、今回はできる限り文献のウラをとっていきながら、分かりやすく説明をしてみようと思います。
2.原則、休業損害は認められない
前述のとおり、休業損害が認められるためには、基本的には、現に休業し、減収が生じていることが必要であるところ、会社役員の場合、事故による休業中も報酬が支給されるのが通常であるため、減収が存在せず、原則として休業損害は認められません。
ここで、とある文献に分かりやすい記載があるので紹介してみたいと思います。
Xは、会社から事故前と同額の報酬を支給されており、自己による傷害の療養のために現実に得られなかった収入(減収)が生じていない。したがって、Xの立場(個人企業の代表者、同族会社の取締役、長年雇用されてきた会社で部長職に昇進して取締役になった者)いかんにかかわらず、原則としてXの休業損害は認められない。
もっとも、例外的に、Xが、取締役部長など使用人兼務取締役として給与を支給されており、療養のために年次有給休暇を使用したような場合には、当該給与支給分については減収が生じていなくとも、取得した有給休暇の日数を休業日数として損害額を算定し、その賠償を請求することができる。
(『裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 交通損害賠償編』271頁)
重要なのは前段部分ですね。
この「減収がない以上、立場にかかわらず、原則として休業損害は認められない」という部分はしっかりと押さえておくべきだと思います。
この原則をすっ飛ばして労務対価の議論などをしているサイトなどがありますが、ややミスリードな気がします。
3.では労務対価性の議論ってどういう場面で出てくるの?
減収がなければ、休業損害も認められないとなると、多くのサイト等で紹介されている労務対価性云々という議論は、一体どういった場面で問題になるのかという疑問がわいてきます。
ここでも先ほど挙げた文献の記載を紹介してみたいと思います。
休業損害や逸失利益の請求ができる場合には、Xの役員報酬のうち労務対価部分をもとに基礎収入を定めて、損害額を算定することになる。(中略)現実には報酬中の労務対価部分の区別は明確でないことも多く、前記のような類型的な考察だけでは足りず、諸般の事情をきめ細かく考慮して判断を行う必要がある場合も少なくない。
(『裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 交通損害賠償編』272頁)
「休業損害が請求できる場合には(中略)労務対価部分をもとに・・・」ということは、裏返すと、休業損害が請求できないときには労務対価部分の議論をする必要はないというように読めますね。
別の文献の記載も見てみましょう。
受傷に起因して減額ないし不支給となった場合、労務対価部分(労務提供の対価と評価される部分)は休業損害として認められるが、利益配当部分(資本の対価ないし利益配当としての実質をもつ部分)については認められない。
(『交通賠償のチェックポイント』95頁)
ここでも「減額ないし不支給となった場合、労務対価部分は休業損害として認められるが・・・」とあり、反対に言うと減額や不支給がなければ労務対価部分の議論にはならないと考えられそうです。
以上をまとめると、減収があって初めて労務対価性の議論をすると考えて差し支えないと思います。
ちなみに、労務対価部分の判断においては、次の要素等を検討することになります。
①会社の規模(および同族会社か否か等)・利益状況
②当該役員の地位・職務内容、年齢
③役員報酬の額
④他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)
⑤事故後の当該役員および他の役員の報酬額の推移
⑥類似法人の役員報酬の支給状況等
これらの各要素の詳細は赤い本2005年版下巻に解説されていますので、説明はそちらに譲りたいと思います。
4.減収がない場合には諦めるしかないのか?
これまで見てきたように、減収がなければ休業損害が認められないというのが原則です。
しかし、休業に起因する減額も不支給もない場合でも、当然にではないものの、企業の従業員等の場合と同様、肩代わり損害ないし反射損害が認められることもあります(『交通賠償のチェックポイント』95頁)。
とはいえ、簡単にこのような法律構成が認められるものではないということは同書の次の記載からもわかります。
理論上は会社の肩代わり損害・反射損害が認められることになるが、実務上は簡単ではない。まず、役員報酬を減額(不支給)していないときは、休業による(会社としての)損失がないからだと反論されることが考えられる。そのため、当該役員が休業したからこれだけ会社の売上が減少したという主張・立証をする必要があるが、この相当因果関係の立証は一般に容易ではない。(『交通賠償のチェックポイント』95頁)
ということで、理論上は企業の損害という構成も考えられますが、現実的にはハードルは高いと考えておいた方がよいと思います。
5.交通事故の翌年度(翌期)の報酬が減少した場合はどうか?
上記のとおり、事故後に減収がない場合には休業損害が認められないのが通常です。もっとも、事故による休業を原因として、事故があった年度の翌年度などの報酬改定のタイミングで報酬が減少したという場合に休業損害が認められないのでしょうか?
ここでは、事故の翌年度(翌期)に役員報酬が減少した事案において休業損害が認められた裁判例を概観してみることにします。
⑴ 東京地裁平成11年10月20日判決
事故当時1200万円であった役員報酬が、本件事故による負傷のため、翌年度以降、1000万円→150万円→260万円と減少した事案(後遺障害等級14級)。
→裁判所は、「役員報酬減少分をそのまま休業損害と認めるのは相当でない。」としつつも、「原告の労務の対価に相当する額と、症状固定時までの治療期間中に労働能力が制限された割合を前提に休業損害を算定するのが相当である。」として、役員報酬(1200万円)の7割である年間840万円を労務の対価分と認定し、同額を休業損害の基礎収入とした。
⑵ 名古屋地裁平成16年4月23日判決
事故当時810万円の役員報酬を得ており、期中の減額はされなかったが、事故により約5か月間休業したことを理由に次年度の株主総会において、原告の前年度の報酬のうち休業期間5月間分に相当する330円を減額する決議がされた事案(後遺障害等級9級)。
→裁判所は、「原告は、訴外会社の取締役とされ、取締役としての報酬を受けているが、実質は、取締役就任以前と同様に訴外会社の従業員として勤務していたと解され、原告に支給されていた報酬は、全て労働の対価であったと解するのが相当である。」として、330万円を休業損害と認定した。
⑶ 東京地裁平成28年11月17日判決
会社は原告(役員)の一人会社であるところ、事故当時1080万円(月額90万円)の役員報酬を得ていたが、本件事故により230日間業務に従事し得ず、本件事故の次年度より720万円(月額60万円)に減額された事案(後遺障害等級7級)。
→裁判所は、原告単独で印刷機器の販売等を行っていたことが認められることから、役員報酬は全て労務提供の対価というべきであるとしたうえで、役員報酬が月額90万円から60万円に減額された事実に照らし、30万円(90万円-60万円)を休業損害算定の基礎とした。
⑷ 上記裁判例の分析
以上のとおり、事故の翌年度以降に報酬の減少が生じた事案において休業損害が認められている事案があるのは事実です。
もっとも、事故の翌年度に報酬が減少したことが、事故による休業が原因であるということが大前提であり、当然のことながら事故以外の理由で報酬が減少したとしても休業損害にはあたりません。
また、一人会社などの小規模会社の場合には代表者自身の判断で減収させることが可能な側面があるため、翌年度以降に減収が生じたからといって直ちにその減少分が休業損害に繋がるとは考えられていません。
現に家族経営の会社の取締役の報酬不支給が問題となった裁判例(名古屋地裁平成12年5月12日判決)において「取締役報酬の不支給が原告の労働能力について本件損害賠償請求の存在を離れて適切に評価されたものか否か強い疑義を抱かざるを得ない」との評価を下したものがあります。
このような観点からすると、事故の翌年度以降に減収が生じたというようなケースにおいては、少なくとも事故による休業が原因で、事故があった翌年度以降に不支給や減収があり、かつ相応の休業状態が生じたことが立証できなければ、役員の休業損害が認定されるということは困難といえるかもしれません。
6.まとめ
以上をまとめると、会社役員の休業損害が問題となるケースにおいては、次のようなフローで検討してみるといいのではないかと思います。
・事故が原因で休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたか
↓ ↓
YES NO→休業ない以上、休業損害なし
↓
・当該休業により減収が生じたか否か
↓ ↓
YES NO→原則、休業損害認められない
※企業損害や事故翌年度以降の減収の検討
↓
・役員報酬の中にどれだけ労務対価部分があるか
→会社の規模、当該役員の地位等を考慮して判断
↓
・労務対価性を有する部分について休業損害請求
以上の説明で少しは整理できたでしょうか。
今回の記事が、会社役員の休業損害の議論に悩んでいる方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【交通事故】過失割合の修正要素の立証責任はどちらにある?
1.はじめに
今回は主に専門家(弁護士)向けの記事です。
交通事故の過失割合を検討する際に、おそらく多くの弁護士がまず初めに見るのは『別冊 判例タイムズ38号』(以下「別冊判タ」といいます。)だと思います。
この本には多数の事故類型が掲載されていますので、自分が扱っている交通事故事件がどの類型と一致するかあるいは近いかという観点で調査をしていくというのが一般的です。
たとえば、歩行者と四輪車の横断歩道上の事故で、歩行者が黄色信号で横断を開始した(四輪車は赤信号で進入した)というケースであれば、別冊判タの【2】の図が該当することになります。
そして、この図を見れば、歩行者の過失割合は10%がベースとなることがわかります。
2.過失割合が争点になる場合
上記の例で、歩行者と四輪車のいずれもが、事故類型について別冊判タ【2】の図を使うこと及び歩行者の過失割合を10%とすることに異存がなければ特に過失割合は争点にならないでしょう。
しかし、歩行者が、「四輪車が脇見運転をしていた」とか「四輪車には時速15㎞以上30㎞未満の速度違反があった」などとして、過失割合の修正を主張し、一方で四輪車側がそのような事情を否定したとすると、事故態様の認識に大きな開きがあるということになり、過失割合が争点になってきます。
仮に上記の歩行者の主張が認められれば、四輪車には著しい過失があるということになり、歩行者の過失割合は5%減少することになります。
そのため、いずれの主張が認められるかで損害額が変わるため、過失割合の立証責任の所在がどちらにあるのかということは重要になってくるわけです。
3.過失相殺の立証責任
判例によると、「民法四一八条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者に過失があつた事実は、債務者において立証責任を負うものと解すべきである。」としています(最高裁昭和43年12月24日判決)。
そして、不法行為における過失相殺についても、被害者の過失の立証責任が原則的に加害者側(被告)にあることに異論はないとされています(『交通関係訴訟の実務』306頁)。
そこで、被害者にも過失があるとして、過失相殺の主張立証自体を行うのは加害者側(被告)ということになります。
なお、過失相殺に弁論主義の適用があるのかという論点についてはここでは立ち入らないことにします。
4.過失割合の修正要素の立証責任
では、過失割合の修正要素の立証責任についてはどのように考えればいいのでしょうか。
先ほどの例でいうと、四輪車に著しい過失があったということについて、著しい過失が「あった」ことを基礎づける事実を歩行者側が立証しなければならないのか、著しい過失が「なかった」ことを基礎づける事実を四輪車側が立証しなければならないのかという議論ということになります。
過失相殺自体を基礎づける事実自体は被告側が主張立証しないといけないとしても、修正要素、中でも被告に不利な修正要素となると、果たして被告に主張立証責任があるといえるのか?などと疑問が出てくるところです。
この点について、ある文献を見てみると「修正要素とは、公平性の観点から、基本過失相殺率・過失割合の値を修正すべき個別具体的な事情のことをいいます。例えば、歩行者と四輪車・単車との事故については、被害者(歩行者)が幼児・児童・高齢者である場合や加害者に居眠り運転・無免許運転等の重過失が認められる場合には、過失相殺率は減算修正されます。(中略)そこで、修正要素を基礎づける事情について具体的に主張・立証する必要があります。」との記載がありますが(『事例にみる交通事故損害主張のポイント』294頁)、残念ながら具体的に被害者側と加害者側のどちらに立証責任があるのかが明示されていません。
そこで、別の文献に目を通すと、「通常、加算修正事由については加害者側、減算修正事由については被害者側が主張・立証責任を負うものとして取り扱われる。」との記載があります(『交通賠償のチェックポイント』229頁)。
また、その他の文献も見てみると「特段の事情の立証がない限り、事故類型に対応する基本の過失相殺率を適用し、これを修正すべき諸事情は、それぞれが自己に有利に働く当事者において立証の必要性を負担するような様相を示す。」との記載があります(『交通関係訴訟の実務』307-308頁)。
ということで、過失割合の修正要素は、その修正要素によって有利になる側が、基本的には主張立証責任を負うという理解で差し支えないといえるでしょう。
そのため、冒頭の例でいうと、「四輪車が脇見運転をしていた」とか「四輪車には時速15㎞以上30㎞未満の速度違反があった」というような事情(四輪車の著しい過失を基礎づける事情)は、歩行者側が主張立証しなければならないということになります。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故分野に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他様々な地域にお住まいの方々からご利用いただいております。
【大阪の交通事故弁護士が教える】レッドブックで見るべきは下取価格?卸売価格?小売価格?
1.はじめに
交通事故で車両に損害が発生したときに、修理が客観的に不可能な場合(物理的全損の場合)や修理は可能であるけれども修理費相当額が車両時価と買替諸費用の合計額を上回るような場合(経済的全損の場合)には、車両に関する損害賠償の上限額は車両の時価額となります。
では、この車両の「時価」はどのように算出するのでしょうか?
今回は、車両の時価の意味を説明したうえで、時価を算出する際によく使われる、「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)の見方を紹介したいと思います。
2.車両の時価とは?
そもそも、車両の時価とは何を指すのでしょうか?
最高裁昭和49年4月15日判決を見てみましょう。
※下線は当事務所によるもの
いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。
この判例のいう「中古車市場において取得しうるに要する価額」というのは、「小売価格」すなわち業者が顧客に対して販売するときの価格を指します。
つまり、業者に対して売却するときの「下取価格」でも、業者間で売買をするときの「卸売価格」でもないということです。
3.レッドブックの見方
車両の時価を算出するのによく利用されるのが「レッドブック」です。
レッドブックというのは通称で、正式名称は「オートガイド自動車価格月報」といいます。
このレッドブックには、中古車に関する「下取価格」、「卸売価格」「小売価格(販売価格)」、「新車販売価格」が、各車種、型式ごとに掲載されています。
先に見た通り、車両の時価は、原則として同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるのに要する「小売価格」を意味しますので、レッドブックの「小売価格」の額を見ればよいということになります(レッドブックの小売価格を参考に車両時価を算定した裁判例として、東京地裁令和2年10月6日判決、東京地裁平成30年10月9日判決など)。
くれぐれも「下取価格」や「卸売価格」ではありませんので、間違えないようにしてください。
ちなみに、レッドブックに掲載されている価格は、年間走行距離は平均走行距離、ボディー・外装・内装の損傷が少ないこと、タイヤの残り山は5分山(新品の半分)程度、エンジン・足回り等機能部分が正常であること、小売価格については、機能・内装・美観の点で車検整備済(12か月分の車検残存期間)又はそれと同程度の状態にある保証付き車両であることを前提とした「車両本体価格」(消費税相当額を除く)を意味するとされています。
そのため、事故の対象となった車両の走行距離や車検残存期間の長短等が、レッドブックの前提条件と異なる場合には、レッドブック記載の加算減算表を参考に「時価」を算出していくことになります。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【大阪の交通事故弁護士が教える】また貸しの場合に自動車の所有者は事故の責任を負うか?
1.はじめに
以前の記事で、盗難車で交通事故が起きたときの所有者の責任について解説をしました。
では、盗難車ではなく、また貸しのケースであればどうでしょうか?
たとえば、車の所有者であるAさんがBさんに車を貸したところ、BさんがAさんに無断でその車をCさんに貸してしまい、Cさんが事故を起こしたとします。
このようなケースで車の所有者(Aさん)は責任を負うのでしょうか?
2.運行供用者ってなに?
以前の記事でも解説しましたが、自動車損害賠償保障法3条を見てみましょう。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
この条文から分かるように、車の所有者が損害賠償義務を負担することになるのは、当該所有者が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に該当する場合です。
運行供用者とはどのような人を指すのかという点については、いろいろな学説があるのですが、近時の判例では、①自動車の使用について支配権(運行支配)を持っているか、②自動車の使用により享受する利益(運行利益)が帰属するかという点に着目して比較的緩やかに運行供用者性を認める傾向にあるといわれています。
そして、運行供用者であるとなった場合には、自賠法3条ただし書に記載されているⅰ自己及び運転者に過失がなかったこと、ⅱ被害者又は第三者に過失があること、ⅲ自動車の構造上の欠陥・機能障害がないことという3要件(免責3要件)を立証しない限りは、損害賠償責任を免れないことになります。
3.また貸し事故の場合は所有者に運行供用者性があるのか?
車がまた貸しされたケースにおける所有者の運行供用者性が問題となった判例として、最高裁平成20年9月19日判決があります。
事案の概要は次のようなものでした。
車の所有者は父Bで、子Xに車を貸すことがそれまでにもありました。
XとAは、AがXの勤務していたキャバクラに客として訪れたのを機に知り合い、その後、Xは、Aの勤務するホストクラブに客として通うようになり、互いに携帯電話の番号を教え合う仲になりました。
Aが自動車の運転免許を有していないことは、Xも知っていました。
ちなみに、父BとAは面識がなく、Aという人物が存在することすら認識していませんでした。
当日、XはBの車を運転して飲食店に行って、無免許のA(運転する能力はあった)と一緒に飲酒していたところ、酔いつぶれてしまいました。
そこで、AがXを助手席に乗せて運転して、家路につこうしたところ、その道中で交通事故を起こしてしまい、Xはこの事故によって顔面を怪我しました。
そこで、Xは、本件自動車を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社に対し、Bが自動車損害賠償保障法2条3項所定の保有者として法3条の規定による損害賠償責任を負担すると主張して、法16条に基づき損害賠償額の支払を求めました。
この場合に、車の所有者である父Bには運行供用者責任が認められるのでしょうか。
最高裁は次のように判示しました。
※上告人というのは、子Xを指します。
前記事実関係によれば、本件自動車は上告人の父親であるBの所有するものであるが、上告人は実家に戻っているときにはBの会社の手伝いなどのために本件自動車を運転することをBから認められていたこと、上告人は、親しい関係にあったAから誘われて、午後10時ころ、実家から本件自動車を運転して同人を迎えに行き、電車やバスの運行が終了する翌日午前0時ころにそれぞれの自宅から離れた名古屋市内のバーに到着したこと、上告人は、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて、Aと共にカウンター席で飲酒を始め、そのうちに泥酔して寝込んでしまったこと、Aは、午前4時ころ、上告人を起こして帰宅しようとしたが、上告人が目を覚まさないため、本件自動車に上告人を運び込み、上記キーを使用して自宅に向けて本件自動車を運転したこと(以下、このAによる本件自動車の運行を「本件運行」という。)、以上の事実が明らかである。そして、上告人による上記運行がBの意思に反するものであったというような事情は何らうかがわれない。
これらの事実によれば、上告人は、Bから本件自動車を運転することを認められていたところ、深夜、その実家から名古屋市内のバーまで本件自動車を運転したものであるから、その運行はBの容認するところであったと解することができ、また、上告人による上記運行の後、飲酒した上告人が友人等に本件自動車の運転をゆだねることも、その容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきである。そして、上告人は、電車やバスが運行されていない時間帯に、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて泥酔したというのであるから、Aが帰宅するために、あるいは上告人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して本件自動車を運転することについて、上告人の容認があったというべきである。そうすると、BはAと面識がなく、Aという人物の存在すら認識していなかったとしても、本件運行は、Bの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきであり、Bは、客観的外形的に見て、本件運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である。
この最高裁判例によると、自動車の所有者とその自動車をまた借りした者との間に全く面識がなく、また貸しについて所有者が明示的に承諾していなかったとしても、また借り人の運転が所有者の容認の範囲内にあると評価できるような事情があれば、所有者について運行供用者性を肯定し、損害賠償責任が認められるということになります。
4.まとめ
以上見てきたとおり、自動車の所有者は、原則として運行支配・運行利益を有する者として運行供用者性を肯定されることが多いといえます。
もっとも、また借り人の自動車運転を所有者が容認していないと評価される場合や、また借り人の自動車使用状態が所有者の容認の範囲を超えていて、その状態を所有者が回復する現実的手段がないような場合には、運行供用者性が否定される可能性もあると考えられます。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【交通事故】交通事故に関する基準時まとめ/事故前年?事故の年?症状固定の年?
1.はじめに
交通事故事件において、損害額を算出するときに、いつの時点の収入が基準になるんだろう?とか、いつの時点の年齢を基準に考えるんだろう?という疑問をもたれる方もおられると思います。
弁護士でも時には「事故前年?事故の年?いや症状固定時?」などと混乱することもありえるところです。
交通事故に関して基準時を考えないといけない項目がいくつかあるので、今回はこのテーマについて解説してみたいと思います。
2.休業損害における基礎収入の基準時
休業損害を計算するうえで、当然のことながら計算の基礎となる収入額を決める必要があります。
では、この収入はいつの時点の収入を基準とするのでしょうか?
この点について、以下にまとめてみることにします。
ただし、いずれもあくまで原則的な考え方や実務的に多い考え方であって、絶対的なものではありませんので、その点はご容赦ください。
| ①給与所得者 |
事故前3か月の平均給与 |
| ②事業所得者(個人事業主) |
事故前年の申告所得額 |
| ③家事従事者(専業主婦) |
事故時の賃金センサス(※注1 参照) |
| ④未就労年少者 |
原則として休業損害は認められない。 |
※注1
実務書において「家事専業者については、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を採用する。」とあります(『交通損害関係訴訟【補訂版】』142頁)。
また、他の文献でも「平均賃金も変動するものであり、いつの賃金センサスを用いるべきかが争われることもあるところ、休業期間が複数年に及ぶ事案(現実の休業日の属する年の賃金センサスを用いる方が、より正確ないし蓋然性の高い数額を算定する観点には適う)においても、理屈はともかく、通常、事故時のものが用いられている。」と記載されているものもあります(『交通賠償のチェックポイント』96頁)。
ただし、賠償請求の時点で事故の年の賃金センサスがいまだ公表されていないような場合には事故前年の賃金センサスによるほかないと考えられます(通常、金額に大きな差はありません)。
3.後遺障害の逸失利益算定における基礎収入の基準時
後遺障害の逸失利益算定においても、休業損害と同様に基礎収入を決める必要があります。
基本的な考え方は休業損害と同じですが、こちらも以下にまとめてみることにします。
| ①給与所得者 |
事故前年の収入(※注2 参照) |
| ②事業所得者(個人事業主) |
事故前年の申告所得額 |
| ③家事従事者(専業主婦) |
症状固定の年の賃金センサス(※注3 参照) |
| ④未就労年少者 |
症状固定の年の賃金センサス(※注4 参照) |
※注2
事故時おおむね30歳未満の若年者で将来的に生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合において、事故前の現実収入の金額が全年齢平均賃金よりも低額のケースは、諸要素を考慮したうえで、全年齢平均の賃金センサスをもって基礎収入とするとされています。
この場合には、原則として症状固定の年の賃金センサスが用いられるとされています(判例タイムズ第1014号61頁(三庁共同提言))
※注3
上記※注2と同様に、三庁共同提言において、原則として、症状固定の年の賃金センサスを用いるとされています。
「通常、休業損害については事故時、逸失利益については症状固定時・死亡時の年の数値が用いられます。」と指摘する文献もあるところです(『事例にみる交通事故損害主張のポイント』113頁)。
※注4
上記※注2と同様に、三庁共同提言において、原則として、症状固定の年の賃金センサスを用いるとされています。
なお、「症状固定時のものを用いる裁判例が多いが、事故時のものや最新(事実審口頭弁論終結時)のものを用いた例もある。」と指摘する文献もあります(『交通賠償のチェックポイント』115頁)。
4.後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間の始期
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とされ、未就労者の場合には原則18歳(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)とされています(〔補訂版〕交通事故事件処理マニュアル117頁)。
「事故日」ではありませんのでくれぐれも間違えないようにしたいところです。
5.まとめ
以上見てきたとおり、①事故前年、②事故時、③症状固定時の3つの基準時が存在することが分かります。
基礎収入の算定にあたっては、基本的には事故前を基準として、賃金センサスが問題となるときだけ事故時or症状固定時を基準とすると認識しておけばよいのではないかと思います。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【交通事故】事故の後どのタイミングで病院に行くべきか?
1.はじめに
前回の記事で、軽いけがだと思っても、自己判断をせずに速やかに医師の診察を受けておきましょうという説明を行いました。
では、具体的にいつ病院に行ったらいいの?という疑問を持たれたかもしれません。
回答としては、「可能な限りすぐに」ということになります。
稀に、仕事が忙しい等の理由で、痛みがあるのに我慢をして最初の診察が事故から数週間経ってからになってしまったという方がおられます。
しかし、弁護士としては最初の診察は事故後すぐに行っていただきたいと思います。
その理由を以下でご説明いたします。
2.初診が遅れることのリスク
上記のように、仕事などを理由に初診が事故から数週間経ってからということになってしまうと、怪我と事故との因果関係が否定されるリスクがあります。
要するに、事故からこんなに期間が開いてから初めて病院に行ってるけど、本当に今回の事故でこの怪我をしたの?という疑問を持たれてしまうということです。
万が一、怪我と事故との因果関係が否定されてしまうと、治療費などが支払われないということにもなりかねません。
こうなってしまうと、適切な賠償を受けることができなくなってしまいます。
このようなリスクがあるので、事故後すぐに診察を受けてほしいということになります。
3.初診時に医師に伝えるべきこと
初診時には、医師にすべての症状を正確に伝える必要があります。
最も痛い箇所だけをとりあえず伝えて、その他の部分は後で言おうという方がおられますが、最初の時点ですべての部位に対する自覚症状を伝えておいていただきたいと思います。
たとえば、初診時には最も痛みの強い腰の症状だけを伝えて、腰の症状が落ち着いてきた1か月後にようやく実は首も痛かったんだよねということで、首の症状を医師に伝えて治療を受けたとします。
しかし、この場合も上記の初診が遅れてしまったときと同様、首の治療費を保険会社から出してもらえないというリスクが発生してしまいます。
ですから、たとえ軽微な症状であったとしても、初診時にすべての部位について自覚症状を正確に医師に伝えておいてほしいのです。
たとえば、右足首と腰は常時強い痛みがあって、首はしびれがあってというような内容です。
また、事故の状況も医師に伝えておく必要があります。
いつ、どこで、どのような事故があって、どのような怪我をしたのかということを説明しておくようにしましょう。
以上のとおり、まずは交通事故に遭われたら、できるだけ早いタイミングで病院に行くということをしていただければと思います。
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【交通事故】事故直後にすべきこと・してはいけないこと
1.はじめに
人生で交通事故に遭うことは1回あるかないかという方がほとんどだと思います。
そのため、交通事故に遭った際に何をすべきなのか、何をしてはいけないのかということがよくわからないということもあると思います。
今回は、弁護士の立場で交通事故直後にすべきこととしてはいけないことを解説してみたいと思います。
2.事故の届出
交通事故が発生した場合、事故があったということを警察に届け出をしなければなりません。
道路交通法72条には次のような規定があります。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
上記の道交法72条1項を読めば何をしなければならないかということが分かります。
①直ちに車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること
②警察に当該交通事故に関する情報を報告すること
が必要です。
この届出は物損事故や自損事故であっても必要です。
3.加害者から届出をしないでほしいとお願いされたときはどうする?
加害者側から警察への届出をしないでほしいと言われることもあるようです。
しかし、このお願いには応じるべきではありません。
というのも、警察への届出は運転者に課せられた道交法上の義務であるからです。
また、仮に届出をしないでおくと、交通事故証明書が作成されないこととなり、後々の示談交渉や後遺障害の認定の場面などにおいて被害者側に不利益が生じてしまうおそれがあります。
したがって、交通事故に遭った場合は、いくら加害者からお願いされたとしても警察への届出をしておくべきということになります。
4.事故の相手方に関する情報を得ておく
交通事故の直後には気が動転してしまうことがありますが、だからと言って、相手方の情報を全く得ておかないと、後から示談交渉をしようとしても手掛かりがないということになりかねません。
そのため、事故の相手方の情報をきちんと確認しておく必要があります。
いくつか具体例を挙げておきます。
①運転免許証を確認して氏名、住所を把握する。
②車のナンバーを確認しておく。
③車検証を確認して、所有者、使用者を把握する。
➢所有者と使用者が異なる場合には、双方の情報を記録しておきましょう。
④自賠責保険、任意保険の会社名を確認しておく。
➢今後の示談交渉先を知るとても重要な情報です。
⑤名刺などから勤務先を把握しておく。
➢場合によっては雇主に対して損害賠償請求をすることもできる可能性もあるためです。
5.相手方とのやり取りを録音しておく
事故直後の相手方の言い分を録音しておくと後々証拠として使える可能性があります。
たとえば、事故直後に言っていた話と示談交渉段階で言っている話が違うというようなことがありますが、そのような場合に相手方から「事故直後にそんなことは言っていない」と主張されたときに録音が役に立つかもしれません。
6.事故現場の状況を撮影しておく
自身の車の状況や相手方の車の状況などをスマホのカメラで撮影しておきましょう。
あとから事故直後の状況を再現することは困難ですので、事故直後の状況を残しておくと、これも後々に揉めたときに証拠として使える可能性があります。
7.目撃者がいれば証言を得ておく
交通事故の目撃者がいる場合、もし協力してくれるようであれば、その目撃者から事故状況がどのようなものだったのかについて証言をしてもらい、メモや録音に残しておくとよいと思います。
できればその目撃者の氏名や連絡先も聞いておきたいところです。
ただし、無理強いをすることはできませんので、あくまで任意に協力してくれればという前提ではあります。
8.自分の加入している任意保険会社への連絡
ご自身の加入している任意保険会社に対しても事故が起きたことを報告しておきましょう。
9.医師の診察を受ける
軽いけがだと思っても、自己判断をせずに速やかに医師の診察を受けておきましょう。
10.弁護士に相談する
事故直後でなくても構いませんが、ある程度落ち着かれたタイミングで弁護士ご相談されるとよいと思います。
今後の示談交渉のこと等を見据えて法律家の視点でアドバイスさせていただきます。
11.まとめ
以上のとおり、交通事故の直後にすべきことは結構あるということがお分かりいただけたかと思います。
しかし、当然ですが、すべてを完璧にこなすことはできない場合もあると思います。
事故による被害が重大で救急搬送されたような場合には、ここに書いたことの多くのことができないということもあるでしょう。
そのため、できることをやっておく、事故直後にできなかったとしても後からできることはやっておくというスタンスで、できる限りのことをしていただければと思います。
続きを読む
☆交通事故、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、治療費の打ち切りなどでお悩みの方は交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の得意とする分野の一つです。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
【交通事故】盗難車で起きた事故~車の所有者は責任を負うか?~
1.はじめに
あなたの車が盗まれて、盗んだ人間がその車で歩行者をはねるという交通事故を起こしたとします。
この場合、あなたは責任を負うことになるのでしょうか?
反対に言うと、事故の被害者である歩行者は、車の所有者であるあなたに対して責任追及をすることができるのでしょうか?
今回はこの問題について解説したいと思います。
自動車損害賠償保障法には次のような規定があります。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
この条文から分かるように、車の所有者が損害賠償義務を負担することになるのは、当該所有者が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に該当する場合です。
車が盗まれた場合、車を盗んだ人間が車の所有者のために運転するということは普通ありませんので、所有者が「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当するということはないとも思えます。
では、裁判所はどのような判断をしたのかを見ていきたいと思います。
2. 運行供用者性が否定された(所有者の責任を否定した)ケース
【大阪高裁昭和46年11月18日判決】
本件事故を発生させた訴外Aは、第一審被告との間になんら人的関係のない第三者であつたのであり(人的関係の不存在)、Aは事故車を勝手にタクシー営業行為に使用し、第一審被告の利益に反して、自己の利益を得たうえ(運転利益の帰属の不存在)、乗り捨てる意図のもとに事故車を盗み出したもので、従つて自身で第一審被告に返還する意思はなく(返還予定の不存在、車体に「サンキュー」と大書されているため、乗り捨てたあと第一審被告になんらかの方法で回収される蓋然性が存在することは、容易に考えられるところであるが、Aがその責任において返還を予定していたとは認められない)、その運転につき事後的に第一審被告の許容を期待しうるような関係には全くなかつた(許容の予測可能性の不存在)のであるし、また、事故車の保管状況からみても、ドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだままであつた(事故車の保管方法の杜撰なことが、第一審被告の担当従業員の第一審被告に対する債務不履行責任上の過失とはなつても、本件事故との間に因果関係の存在を認め難いことは、のちに認定する)とはいえ、一般人の通行の用に供される道路上に、あたかも一般通行人の運転を許容するかのように、一般通行人が極めて容易に運転できる状況のもとに放置していたというわけのものではなく、周囲をブロック塀で囲まれた第一審被告の営業所内に保管していたのに、Aは、扉が開いていたとはいえ、深夜裏口からタクシー車を盗み出すつもりで侵入し、事故車を窃取したものであつて、これらの事情を総合すると、事故車に対する第一審被告の支配は、Aが事故車を盗み出したときに排除せられ、本件事故のときには右Aのみが事故車の運行を支配し、運行利益も同人に帰属していたものというべく、本件事故につき第一審被告に運行供用者としての責任があるとすることはできない。(中略)結局自動車についてはそれが道路上に、あたかも、運転資格を問うことなく、一般通行人の運転を許容するかのように、一般通行人の誰でもが極めて容易に運転できる状況に自動車を放置したため、運転無資格者や泥酔者が運転し、所有者がこれらの者に運転を許容したのと同視できるような故意に近い重過失のある特殊な場合はさておき、少くとも本件のように、周囲をブロック塀で囲んだ営業所の構内に保管されていた自動車が盗み出された場合には、保管上の手落ち自体をとらえて、運転自体の過失から生じた事故との相当因果関係を肯定し、これを以て、保管上の過失による事故としての不法行為とすることはできない。
➢①所有者と窃盗犯との間に何らの人的関係がないこと(所有者と窃盗犯の人的関係)、②所有者が運転の利益を得ていないこと(運転利益の帰属の有無)、③窃盗犯が車を返還する予定がなかったこと(窃盗犯による返還予定の有無)④所有者が窃盗犯が運転することを許容していたと評価できないこと(許容の予測可能性の有無)、⑤所有者が車をブロック塀で囲まれた営業所内に保管していたこと(所有者の車両管理状況)、⑥窃盗犯が営業所内に侵入したうえで車を盗み出したこと(窃盗犯の乗り出し態様)などから、所有者の責任を否定しました。
【最高裁昭和48年12月20日判決(上記大阪高裁判決の上告審)】
本件事故の原因となつた本件自動車の運行は、訴外川口が支配していたものであり、被上告人はなんらその運行を指示制御すべき立場になく、また、その運行利益も被上告人に帰属していたといえないことが明らかであるから、本件事故につき被上告人が自動車損害賠償保障法三条所定の運行供用者責任を負うものでないとした原審の判断は、正当として是認することができる。(中略)おもうに、自動車の所有者が駐車場に自動車を駐車させる場合、右駐車場が、客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造、管理状況にあると認めうるときには、たとえ当該自動車にエンジンキーを差し込んだままの状態で駐車させても、このことのために、通常、右自動車が第三者によつて窃取され、かつ、この第三者によつて交通事故が惹起されるものとはいえないから、自動車にエンジンキーを差し込んだまま駐車させたことと当該自動車を窃取した第三者が惹起した交通事故による損害との間には、相当因果関係があると認めることはできない。
前示のように、本件自動車は、原判示の状況にある被上告人の車庫に駐車されていたものであり、右車庫は、客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造、管理状況にあつたものと認められるから、被上告人が本件自動車にエンジンキーを差し込んだまま駐車させていたことと上告人が本件交通事故によつて被つた損害との間に、相当因果関係があるものということはできない。そして、この判断は、本件において、次のような事実、すなわち、被上告人は、本件自動車が窃取された約二〇日前である昭和四二年八月一日午前二時頃にも、エンジンキーを差し込んだまま本件自動車の駐車地点とほぼ同じ場所に駐車しておいたままタクシー車が窃取されたうえ乗り捨てられたという事実があつたが、盗難防止のための具体的対策を講じなかつたこと、被上告人の営業課長浅倉秀雄は、本件自動車が窃取される前、すでに、エンジンキーが差し込まれたままの状態にあつたことを知つていたが、そのまま放置していたこと、また、被上告人の当直者のだれもが本件自動車が窃取されたことに気付かなかつたこと等の事実が存し、被上告人の本件自動車の管理にはいささか適切さを欠く点のあつたことが認められることを考慮しても、左右されるものとはいえない。
したがつて、被上告人が本件事故につき民法七一五条の不法行為責任を負うものではないとした原審の判断は,正当として是認することができる。
➢最高裁も所有者の責任を認めず、原審(大阪高裁昭和46年11月18日判決)の判断を正当なものであると結論づけました。
【東京地裁平成7年8月30日】
以上の事実によれば、いかに夜間で、人通りの決して多くない道路とはいえ被告Aは、被告車を、エンジンキーを着け、エンジンもかけたまま、ドアも施錠しない状態で公道上に放置した結果、被告車を窃取されたのであり、被告車の管理に過失があつたことは明かである。
しかしながら、被告Aは、被告車を停車させた場所は、被告Aが買い物に出かけたコンビニエンスストアーと隣接した路上であり、被告Aと被告車との距離は、数メートルと極めて短距離であること、被告Aは、コンビニエンスストアーでジユース等を買い物をするために被告車から約五分間と短時間、一時的に離れたに過ぎず、被告Aには、被告車を長時間放置する意図はもとよりなかつたこと、被告Aが被告車を離れた直後に、これを待ち受けていた訴外畑が被告車を窃取していること、被告Aは、被告車を窃取されたことに気づき、直ちに、被告車を窃取された旨警察に連絡し、同日午後一一時には被害届が作成されており、訴外畑ら第三者の運転を排除するための措置を取つていること、本件事故は、窃取後、約七時間半を経過した後に事故を起こしたのであり、窃取後、短時間後の事故とはいえないこと、訴外畑らは、被告車を窃取してから本件事故を惹起するまでの間、途中、仮眠を挟むなどした上、被告車を約三〇キロメートル走行させていること、被告車が窃取された前記「サークルK」前路上から本件事故現場までは、直線で約七、八キロメートルあり、距離的にも離れていること、訴外畑らには、被告車を返還する意思は認められないこと、被告Aと訴外畑らとの間には、親族関係はもちろん、何らの人的関係もないことが認められる。
これらの事実を総合考慮すると、被告Aは、被告車を第三者の自由使用に委ねたと評価できず、また、被告車の運行支配も運行利益も失つていると認められるので、自賠法三条の責任を認められない。
また、前記のとおり、被告Aに、被告車の管理上の過失があつたことは認められるが、本件事故は、直接的には訴外畑の過失によつて発生したものであり、右のとおりの窃取からの本件事故までの経過から見て、被告車は、既に被告Aの管理の影響を脱出していると認められるので、被告車の管理上の過失と本件事故との間に因果関係が認められず、被告Aには、民法七〇九条の責任も認められない。
3.運行供用者性が肯定された(所有者の責任を肯定した)ケース
【大阪地裁昭和61年3月27日判決】
前記認定事実によれば、被告会社は捜査機関に対し、加害車が被告会社と何ら関係のない第三者によつて窃取されたものであるとの被害届を提出しないため、捜査機関においてもこれを窃盗被疑事件として捜査せず、原告小坂を被害者とする業務上過失傷害被疑事件としてのみ捜査を継続しているものの、事故現場に犯人と結びつく物的証拠も残されていなかつたことからいまだ犯人を特定するに至つていないこと、〇〇警備(株)の事件当夜の警備員は、その警備報告書に、昭和五九年三月一九日午後八時三〇分の本件駐車場点検時にはトラツク七台が駐車されていたと記載し、その後の巡回において車両の増減がなかつたために右報告書には特別の記載がなされていないことから、加害車が本件駐車場を出発する時刻においても、なおトラツク七台が駐車されていたものと推認されるのに、事故後に駐車されていた車両も七台であつたというのであるから、右事実によると、被告会社関係者が、本件駐車場において、加害車に乗り換えたものとする余地も全くありえないものでもないこと、事件当夜に、本件駐車場にはエンジンキーが差し込まれたまま、ドアーに施錠もせずに駐車されていた車両が三台も存在したのに、本件駐車場中央西側に向け駐車されていたとする加害車が運行され(なお、警備員は加害車の発進音のみを聞いており、発進時に衝突があつたとする証拠はない。)、旧国道一七〇号線に面して駐車されていた加害車と同様にエンジンキーが差し込まれたままドアーに施錠もされていなかつた四屯車両及び本件駐車場南西に西に向け駐車されていた、本社事務所からの見通しのきかない同二屯車両が、その運行が容易であつたのに、これらは運行されなかつたこと及び加害車発進時刻から判断すると、照明燈から我が身を隠すというよりも、むしろ、加害車運転者は、特に、加害車を運行手段にすることを目的としていたものとも推認されること、加害車運転者は事故当時飲酒しており、蛇行運転して被害車と正面衝突したというのであるから、その運転者は、被告会社主張の如く、転売目的ないし乗り捨て目的のため常習として車両を窃取していた者とはいえず、事故を発生させたこと及び飲酒運転の発覚をおそれ、また、被告会社の許可なくこれを使用したことが発覚することをおそれたために現場を逃走したものとも考えられ、犯人が逃走している事実をもつて、運転手が窃盗犯人でなければならないものともいえないことが認められ、右事実のみでも、事故時の加害車運転手が加害車を窃取した犯人であり、被告会社は加害車の運行支配を離脱していたとする被告会社の主張はとうてい認めることができないうえ、全証拠によるも、加害車運転手が、被告会社の加害車に対する運行支配を離脱させるべく、乗り捨て目的でこれを運行していたものであると認めることもできない。
のみならず、仮りに、事故時の加害車運転手が加害車を窃取した犯人であるもしても、加害車が駐車されていたとされる本件駐車場は、前記認定のとおり、旧国道一七〇号線に東側を面した間口が三〇メートルあり、四囲を囲む施設、設備などの工作物が建造されたこともなく、その南側三分の一は被告会社以外の第三者が駐車場として使用し、被告会社使用部分も、下請及び被告会社従業員並びに顧客などが自由に駐車できる駐車場であつて、客観的に第三者の自由に立入ることのできる駐車場であつたことが認められ、かつ、本件駐車場と本件事故現場とが場所的に、約二キロメートル弱の距離にあつて近接し、警備員川口が加害車の発進音を聞いた時刻と事故発生時刻とが近接しているうえ、飲酒した状態で加害車を蛇行運転し、長距離運転する状況になかつたことを考え合せると加害車の発進と事故発生とが時間的にきわめて近接していることが認められる本件では、被告会社の加害車に対する運行支配が、本件事故発生時において、既にその支配から離脱していたものとはいえない。
【東京地裁平成22年11月30日判決】
証拠(乙3、4)及び弁論の全趣旨によれば、被告車両が駐車されていた場所は、被告の八王子支店敷地内の駐車場であり、公道との間に外壁はなく、第三者が自由に出入りできたこと、被告車両は施錠されず、鍵は運転席サンバイザーに挟まれていたことが認められる。そうすると、第三者が無断で被告支店駐車場に侵入し、施錠されていない被告車両を窃取することは容易に予想することができ、被告は第三者が運転することを容認していたと同視されると評価されてもやむを得ない。被告車両が窃取されてから本件事故の発生まで長くても5時間半程度しか経過していないし、本件事故現場は窃取された場所から遠隔地でもない。被告が被告車両を窃取された後、本件事故が発生するまでの間に、被告車両が運転されないようにする措置を取った事実は認められない。
そうすると、本件事故発生当時、被告は被告車両について運行供用者としての地位を失っていなかったというべきであり、被告は本件事故によって生じた原告の人身損害を賠償すべき責任がある。
3.まとめ
以上のとおり、盗難車による事故が問題となったケースにおいては、所有者の責任を否定する裁判例と肯定する裁判例のいずれもが存在しています。
これらの裁判例を分析すると、所有者の責任が認められるか否かは、①所有者と窃盗犯の人的関係、②所有者が運転の利益を得ているか否か、③窃盗犯が車を返還する予定があったか否か、④所有者が窃盗犯が運転することを許容していたと評価できるか否か、⑤所有者の車両管理状況がどのようなものだったのか、⑥窃盗犯がどのような態様で乗り出しを開始したのか、⑦車の窃盗と交通事故とが時間的・場所的にどの程度離れていたのかなどの諸要素を考慮して決定されるものと考えられます。
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【交通事故】整骨院等の施術費が認められる場合と認められない場合
1.はじめに
前回の記事で、整骨院などで受けた施術費の全額が必ずしも加害者の賠償すべき治療費として認められるとは限らないということを説明しました。
今回は、いくつかの裁判例を紹介しながら、どのようなケースで施術費が認められたのか、あるいは認められなかったのかということを見ていきたいと思います。
※下線は当事務所によるもの
2.施術費が認められたケース(一部認められたものも含む)
①神戸地裁平成18年12月22日判決
原告本人尋問の結果によれば、原告は、A病院を退院した後、A病院の医師と話し合った上、リハビリテーションを受けるために坂口接骨院に通院することにし、B接骨院で運動療法及び電気治療などを受けており、B接骨院で施術を受けたときには原告の症状が軽減したこと、他方、B接骨院に通院中もA病院に通院して診察を受けていたが、同病院でリハビリテーションを受けていなかったことなどの事実を認めることができる。上記の認定事実によれば、原告は、A病院の医師と話し合った上、A病院でリハビリテーションを含む治療を受ける代わりにB接骨院でリハビリテーションを含む治療を受けていたと認められるから、B接骨院での治療も上記の傷害の治療として必要かつ相当なものと認めるべきである。したがって、B接骨院の治療費を本件事故によって原告に生じた損害と認めるのが相当である。
②東京地裁平成25年8月29日
①原告は,診療時間が限られているA整形外科医院には,ほとんど週末しか受診することができなかったことから,早期治癒のため,勤務終了後に通院することができる整骨院等に通院することとし,A整形外科医院の担当医師もこれを承知していたこと,②原告が整骨院等で受けていた施術の内容は,A整形外科医院で受けていた消炎鎮痛等処置と概ね同じであり,症状改善に効果的であったことが認められる。以上によれば,B整骨院及びC接骨院における施術は,本件事故後の原告の症状を改善するために必要かつ相当であったということができ,本件事故と相当因果関係があると認められる。
③横浜地裁平成29年5月15日判決
整骨院での施術についても,上記事故態様に照らし,全身を打撲した可能性を否定できず,受傷直後は医師の診断を受けていた頚部及び腰部以外の部位に痛み等の症状があったとしても不自然ではなく,これに対する施術が必要であったと推認されること,A病院及びB整形では整骨院に通院中であることを前提として治療が行われていること,症状の改善に従って施術対象が限定され,通院頻度も減少しており(甲13),施術の有効性が推認されることからすれば,治療の必要性・相当性を否定すべきではない。
④東京地裁平成29年7月18日判決
原告は本件事故による非器質性精神障害を負い,その治療を受けたものである上,原告がA鍼灸治療室において針治療を受けたのは昭島病院の医師の勧めに基づくものであるから,かかる治療費等も損害として認めるのが相当である。
⑤東京地裁平成30年11月30日判決
本件整骨院での施術は,主治医による同意があったとは認められないものの,前記(1)エの施術箇所は,本件整形外科で症状が認められていた部位と矛盾はないこと,原告Eの出張状況(前記(1)オ)から多忙であったと窺われ,勤務先近くの本件整骨院で施術を受けることが便宜であるという事情は首肯できること,施術回数内容が過剰であるとは認められないことから,平成27年8月末までの施術について必要性相当性を認める。
※整骨院への約1年6か月の通院期間のうち、約1年間の施術については必要性・相当性を認めました。
⑥東京地裁令和元年8月27日判決
各整骨院の施術費については,施術を受けることについては,Aクリニックの医師も把握していたものの(乙2),医師の指示があったとまでは認められないこと,通院頻度も高いことから,医師が診断した負傷名で施術が行われており,施術に一定程度の効果が認められることを考慮しても,その施術の全てについて相当因果関係を認めることはできず,その75%について相当因果関係を認めるのが相当である。
3.施術費が認められなかったケース
①東京地裁平成16年2月27日判決
原告は、整体院における整体料を請求するので、検討するに、対象疾患に対する治療と疲労回復等のための整体術との境界は明確ではないこと、患者の受傷の内容と程度に関し医学的見地から行う総合的判断は医師しかできないところ、整体術は整形外科の治療法と比較したときに限界があり、整体によりかえって筋組織の硬結を招く問題点もあること、整体においても、整骨院における施術と同様に、施術の手段・方式や成績判定基準が明確ではないため施術の客観的な治療効果の判定が困難であることや施術費算定についても診療報酬算定基準のような明確な基準がないという事情があることを考慮すると、施術の必要性・有効性、施術内容の合理性、施術期間の相当性及び施術費用の相当性の各要件を満たす証拠が認められない本件において、整体料を整形外科病院の治療費と同様に、加害者の負担すべき損害とするのは相当ではない。したがって、原告の請求は認め難い。
②大阪高裁平成22年4月27日判決
Bは、本件事故当日、Aとともにb病院を受診し、左肘打撲と診断され、治療としては対症療法をする程度とされ、その翌日にAとともに同病院を受診していないから、Bの上記受傷の程度は軽微なものであったというべきである。したがって、被控訴人が、同月四日にAとともに被控訴人を受診したBについて、左肘関節打撲及び上背部打撲と診断し、同年六月三〇日までに六二日間施術をしたのは、Bの上記受傷の程度に照らし相当な範囲を著しく超える過剰な施術であったといわざるを得ず、これについての施術料が、本件事故と相当因果関係があったと認めることはできない。
③神戸地裁平成28年8月24日判決
原告は,知り合いからカイロプラクティックAを紹介され,手で身体全部をほぐし,タオルで頚部を引っ張る治療を受け,徐々に良くなっていく実感があり,1年位で元に戻ってきた感じになった旨供述し,これと同趣旨の陳述書(甲17)がある。しかし,B市民病院及びC整形外科病院の診療録(乙3,4)には,原告が医師に対して整体治療や鍼治療等を受けていたなどと報告した記載はあるものの,これに対する医師の指示や同意があった形跡はない。また,カイロプラクティックAの施術録等はなく,原告がカイロプラクティックAでどのような治療を受け,どのような効果があったかを裏付ける証拠はない。そして,カイロプラクティックAが柔道整復師等の国家資格を有していたことは窺われず,カイロプラクティックAにおける治療は鍼灸院や整骨院における施術であると認めることはできない。以上に照らすと,原告のカイロプラクティックAにおける治療の有効性・相当性を認めることはできず,原告のカイロプラクティックAへの通院と本件事故との相当因果関係を認めることはできない。
④金沢地裁平成28年9月15日判決
原告は,上記の期間も腰痛が生じており,平成23年9月4日に健康サロン教室で整体,マッサージ,低周波指導を受け,同年11月7日にサポーターやホッカイロを購入したこと(前記1(5)イ)は,いずれも腰痛のためであると主張・供述する(原告〔3,4頁〕)。しかし,本件事故の翌日にA医療センターを受診した後も腰痛が継続していたのであれば,同センターへの通院を継続していたものと考えられるところ,原告は同日以降,同センターへの通院をしていないのであり(同(5)ア,イ),腰痛が継続していたとは認められない。仮に,いったん腰痛が治まった後に新たに腰痛が生じたのだとしても,医療機関への通院をしていないことからすると深刻な症状であったとは考えにくいし,そのような場合にはそもそも本件事故によって生じた腰痛であるともいい難く,20歳ころに交通事故によって負ったという腰椎圧迫骨折等の後遺症である可能性が否定できない。(中略)健康サロン教室(f),B病院(g)及びC整骨院(h)に関する治療費については,本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。
⑤東京地裁平成29年3月29日判決
原告は,平成27年5月1日及び同月12日のマッサージはり灸Aの治療費合計6000円,同年7月14日のB鍼灸接骨院の治療費1210円を請求する。しかし,原告自身の判断で,マッサージ治療に切り替えたもので(原告本人),医師の指示等を認めるに足りる証拠はないし,最初の治療も,本件事故から2か月余り経過し,C整形外科への最後の通院からも1か月半余りが経過しており,本件事故から2か月余り経過して施術の必要性がにわかに発生したとは通常考え難い。したがって,原告の前記請求は理由がない。
⑥東京地裁平成29年11月14日判決
スポーツ整体診療所における治療費 0円
本件事故による傷害の治療行為としての必要性・相当性を認めるに足りない。
4.まとめ
以上は多数ある裁判例のうちの一例にすぎませんが、これらを見ると医師の指示や同意があったかどうかが重要なポイントになっていることが分かります。
この点、裁判官の講演録においても「医師が患者に対して整骨院での施術を受けるように指示をしている場合には、資格を有する医師が患者の治療方法の一つとして柔道整復師による施術を積極的に選択したことを意味していますから、特段の事情がない限りは、①施術の必要性、②施術の有効性があることを強くうかがわせる事情になります。」との指摘がなされているところです(吉岡透「整骨院における施術費について」赤い本2018年版下巻27頁以下)。
もっとも、医師の指示がない場合でも、施術費が認められたケース⑤⑥の裁判例で紹介したように施術費の一部が認められる場合もあります。
反対に、医師の指示があるからといって、無制限にどのような施術でも損害として認められるというわけではありません。
交通事故による怪我の治療のために整骨院等での施術を考えておられる場合には、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【交通事故】接骨院、整骨院、鍼灸、マッサージ等の施術費が問題となる事案
1.はじめに
以前にも簡単に説明したことがありますが、実務において整骨院などの施術費が交通事故による損害として認められるかが問題となることが少なくありません。
交通事故の場合、事故直後の初診には医療機関において一定の外科的治療が施され、その後は整骨院などに通院するというケースがよくあります。
治療を受ける側としても、整骨院などが自宅や職場の近くあったり、医療機関に比べて営業時間が長かったりすることから、できれば整骨院などで治療を進めたいという気持ちになられるのだと思います。
しかしながら、整骨院などで受けた施術費の全額が必ずしも加害者の賠償すべき治療費として認められるとは限りませんので注意が必要です。
2.どのような場合に認められるのか?
一般に、接骨院などの施術費については、症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などは認められる傾向にあるとされています。
これは交通事故事件において一般に利用されている「赤い本」という文献の記載内容です。
ちなみに自賠責保険の支払基準においては「必要かつ妥当な実費」を認めると規定されています。
では、どういった場合に、「有効かつ相当」とか「必要かつ妥当」といえるのでしょうか。
一つ重要な裁判例を見てみましょう。
※下線は当事務所によるもの
【東京地裁平成14年2月22日判決】
事案の概要
自動車と衝突した自転車の運転者の男性が接骨院における施術費として175万2500円を請求しました。
判旨
(1) A整骨院での施術費を損害として計上することができるか
ア 鍼灸マッサージ等の施術の必要性、合理性
負傷した被害者が病院又は診療所において受けた医師又は歯科医師(以下、歯科医師と併せて「医師」と総称する。)による治療は、特段の事情のない限り、その治療の必要があり、かつ、その治療内容が合理的で相当なものであると推定され、それゆえ、それに要した治療費は、加害者が当然に賠償すべき損害となるから、加害者がこれを争う場合には、加害者が積極的に個別具体的な主張立証をしなければならない、と解すべきである。
これに対し、被害者が自らの治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師(以下「あん摩マッサージ師等」という。)による施術を選択した場合には、その施術を行うことについて医師の具体的な指示があり、かつ、その施術対象となった負傷部位について医師による症状管理がなされている場合、すなわち、医師による治療の一環として行われた場合でない限り、当然には、その施術による費用を加害者の負担すべき損害と解することはできないのであって、施術費を損害として認めるためには、被害者は、①そのような施術を行うことが必要な身体状態であったのかどうか(施術の必要性)、②施術の内容が合理的であるといえるかどうか(施術内容の合理性)、③医師による治療ではなく施術を選択することが相当かどうか(施術の相当性。医師による治療を受けた場合と比較して、費用、期間、身体への負担等の観点で均衡を失していないかどうか)、④施術の具体的な効果が見られたかどうか(施術の有効性)、等について、個別具体的に積極的な主張、立証を行わなければならない、と解すべきである。なぜなら、あん摩マッサージ師等は、医師と異なり、その施術は限られた範囲内でしか行うことができない(外科手術、薬品投与等の禁止、脱臼又は骨折の患者に対する施術の制限等。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律四条、五条、柔道整復師法一六条、一七条)上、その施術内容の客観性、合理性を担保し、適切な医療行為を継続するために必要な診療録の記載、保存義務が課せられていないこと(医師法二四条一項、二項、歯科医師法二三条一項、二項の診療録の記載及び保存義務に関する規定が、前記各法律にはない。)、外傷による身体内部の損傷状況等を的確に把握するために重要な放射線による撮影、磁気共鳴画像診断装置を用いた検査をなし得ないこと(医師の指示の下に医師又は診療放対線技師が機械操作することとなる。診療放射線技師法二三条、二条二項。)、それゆえ外傷による症状の見方、評価、更には施術方法等にも大きな個人差が生じる可能性があること、施術者によって施術の技術が異なり、施術方法、程度が多様であること、自由診療で報酬規程がないため施術費が施術者の技術の有無、施術方法等によってまちまちであり、客観的で合理的な施術費を算定するための目安がないこと、といった点が指摘され、これらの事情を考慮すると、あん摩マッサージ師等による施術については、医師の治療のような必要性、合理性、相当性の推定をすべきではなく、それゆえ、施術費を、医師の治療費と同様に、加害者の負担すべき損害とするのは相当ではないからである。
イ A整骨院における施術について
(ア) 施術が医師の治療の一環として行われたかどうかについて
前示認定事実によれば、原告は、A整骨院での施術治療期間中、B病院にも通院しているが、整形外科での受診は平成一一年一月一二日と同月二〇日のわずか二日間にとどまっており、B病院整形外科のb医師(以下「b医師」という。)は、同年一月二〇日に針治療を含めた加療を要する旨の診断をしたものの、それ以降、原告の治療に携わった形跡はなく、原告の身体状態について詳細不明としていることからすると、b医師は前記施術期間中に原告の身体の症状管理をしていなかったことが認められるから、A整骨院での施術が医師による治療の一環としてなされたものとはいい難い。
(イ) 施術の必要性、合理性、相当性、有効性等について
a 施術の必要性、相当性
b医師は、原告の身体状態が針治療等の施術も含めた治療を行うことについて必要性を肯定する。しかし、b医師は、原告の症状につき通院治療を続けながら経過観察を行うことを基本としていたと考えられ(一月一二日の記載)、診療録上施術に関する具体的な指示事項の記載や施術内容に関する聴取事項の記載が全くないこと、をも併せると、同医師は、原告の身体状態が鍼灸マッサージ等の施術を必要とする、との認識していたというよりは、むしろ、施術が原告に対する治療にとって特段障害ではなく、有用性は否定しない、という消極的な認識を有していたにすぎないと解されるのであって、結局、原告に対する施術の必要性を裏付けるに足りる具体的で合理的な証拠はないといわざるを得ない。
そして、後述するとおり、施術は原告の身体症状にとって有効なものであったとは認められるものの、施術を行うことが、医師による治療を受け続けた場合と比較して、費用、期間、原告の身体への負担等の観点から相当であることを裏付けるに足りる証拠もない。
b 施術内容の合理性、有効性
しかし、A整骨院での施術期間中、原告の症状(左上腕から左第四、第五指への疼痛、しびれ感、右半身の脱力感、右上腕部の疼痛等)がしだいに緩解、軽快していった状況と、原告が現に快復している状態であったこと、に照らすと、施術内容が合理性を有し、かつ、原告にとって有効なものであったと推認することはできる。
(ウ) まとめ
A整骨院における施術は、医師の治療の一環として行われたものとは認められず、また、原告の症状に対して施術を選択することが必要で、合理的かつ相当であったとは認められない。
しかし、施術そのものは、原告の症状を緩解させ、原告の快復に有効であったことは認められる。
ウ 結論
前示のとおり、A整骨院での施術が有効であったことは認められるが、その施術を行うことの必要性、合理性、相当性が認められない以上、同施術に要した費用を損害として加害者に負担させるのは相当ではない。
もっとも、前示のとおり、施術が原告の症状に有効であったこと、この施術期間中整形外科の治療費の支出がなかったこと(原告が医師による治療を選択せず、これを受ける機会が少なかったため、算定されるべき治療費に係る損害額も少なくなる。)を考慮すると、施術費を損害として計上せずに被害者たる原告の自己負担としてしまうことは、必ずしも、公平の観点から見て相当とはいい難い。
当裁判所は、原告が、施術費を自己負担をしてでも施術を受けて軽快させたいと思う程度の症状に苛まれていた、との観点から、これを、後述する慰謝料の加算事情として積極的に評価するのが相当であると考える。これに対し、施術費中の幾らかを損害額として割合的に認定する考え方もあり得るが、そのような算定をするための合理的な基礎資料を収集、整理し、提出することは一般に容易ではなく、本件でもそれは十分でないため、割合数値を設定することは困難である。そこで、本件では、民事訴訟法二四八条によって、あえて施術費の費目で損害額を認定するよりは、むしろ、算定困難な損害額の算定として有用な慰謝料の費目で計上するのが合理的かつ相当であると判断した。
3.解説
この裁判例では、「医師による治療の一環として行われた場合でない限り、当然には、その施術による費用を加害者の負担すべき損害と解することはできない」としたうえで、以下の4つの要素を挙げています。
①そのような施術を行うことが必要な身体状態であったのかどうか(施術の必要性)
②施術の内容が合理的であるといえるかどうか(施術内容の合理性)
③医師による治療ではなく施術を選択することが相当かどうか(施術の相当性。医師による治療を受けた場合と比較して、費用、期間、身体への負担等の観点で均衡を失していないかどうか)
④施術の具体的な効果が見られたかどうか(施術の有効性)
これは、医師の治療については原則その必要性、合理性、相当性が推定されるのに対し、整骨院等での施術については医師の指示がない限りその必要性、合理性、相当性の推定を行うべきではないという理屈によるものであると考えられています。
そして、このケースでは、整骨院における施術は、医師の治療の一環として行われたものとは認められないとしたうえで、施術の有効性は認められるものの(④充足)、施術の必要性、施術内容の合理性、施術の相当性が認められないこと(①~③充足せず)を理由に、整骨院での施術費は損害として認定されませんでした。
もっとも、慰謝料の加算要素として考慮を行うという結論をとって一定の調整を図っています。
このように、整骨院等での施術が事故による損害として認められないケースもありますので、整骨院等で施術を受けるか否かにあたっては慎重な判断が必要となります。
次回以降では、施術費が損害として認められたケースを紹介したいと思います。
続きを読む
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【交通事故】治療関係費はどこまで認められるか?~過剰診療・高額診療~
1.治療費が認められる要件
交通事故が起きてけがをした場合、当該交通事故から発生した怪我の治療に必要かつ相当な範囲であれば実費全額が損害として認められます。
ただし、過剰診療や高額診療の場合には必要性・相当性が否定される場合があるので注意が必要です。
過剰診療とは、必要もないのに長期間入院したり、通院を続けたりするなど、事故から発生した傷害に対する治療行為として医学的必要性ないしは合理性がないもののことを指します。
高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に照らして著しく高額な場合を指します。
2.過剰診療が問題となるケース
患者から痛み等の訴えがある場合には、医師が入院や治療の打ち切りをしないことがあり、こういう場合に後々になって過剰診療として損害が否定されることがあります。
実際に過剰診療にあたるかどうかは、カルテ、レントゲン、CT、MRI、看護記録などを精査したうえで、現在の客観的症状を確認し、通常の症例と比較して治療内容が適正か、処方されている薬の内容はどうかなどといった点から判断されることになります。
ここで一つ裁判例を見てみましょう。
頸椎捻挫等による16か月間の通院をしたというケースで、被告からは「原告は長期治療の必要を主張するが、整形外科医学界では、他覚的所見のない頸椎捻挫は通常三か月程度で治癒ないし症状固定になるというのが支配的見解であるところから、原告の負つた頸椎捻挫は、本件事故日から三か月を経過した昭和六三年五月末日までには治癒ないし症状固定になつたものと判断され、それ以降の治療と本件事故との間に相当因果関係はないと考えられる。」との主張がなされました。
この点について、横浜地裁平成5年8月26日判決は次のように判示し、原告の治療費を認めました。
※下線は当事務所によるものです。
本件事故を起因とする原告の治療費は原告主張の三一七万八九七〇円を下らないところ、その大部分を占める三宅整形外科における診療は、期間的・内容的に、必ずしも真摯な医療行為ばかりではなかつたとの疑いを払拭することはできず、この点からすると、右治療費の全部を本件事故と相当因果関係のある損害として被告の負担とすることには些か躊躇を覚えないではない。しかし、原告がその客観的原因はともかく、本件事故を契機とする各種の自覚症状のゆえに通院を続けたことは事実というべきであり、この点について原告に詐病による利得を図る意図があつたなどとは到底考えることができないから、少なくとも右治療費を本件事故による損害として請求し得ることの可否を論ずる場面においては、右の継続的通院をもつて原告を責めるのは酷である。また、三宅医師においても、なお自覚症状が続いているとして原告から治療を求められた以上、それに対応した何らかの診療行為を行つたのもやむを得ない面がないではなく、あえて不必要な治療に及んだとまでみることもできにくい。一方、いわゆる一括支払の合意のもとに毎月「自賠責診療報酬明細書」を送付されながら、事実上中途で支払を止めただけで、その後の診療に何らの異議も伝えなかつた保険会社はその本来あるべき責務を十分に果たしたとはいい難い。被告主張のように三宅整形外科における治療が必要性・合理性の範囲を超えた期間に及んでいると考えるのであれば、直ちにその旨を伝えるなどして爾後の治療費の支払を拒むことを明らかにすべきであつた。
以上のような事情を総合すると、原告主張の治療費については、損害の公平な分担についての信義則上、その全額である三一七万八九七〇円を本件事故と相当因果関係があるものとして被告の負担とするのが相当である。
3.高額診療が問題となるケース
交通事故による治療行為は、自由診療で行われることが少なくありません。
そのため、同一の治療内容であっても、健康保険を利用した場合の治療費と比較して数倍になるということもあります。
これは診療単価が健康保険を利用した場合1点=10円とされているのに対し、自由診療においてはそのような制限がないことによるものです。
ここでも一つ裁判例を見てみましょう。
診療報酬単価が争点となったケースで、東京地裁平成25年8月6日判決は次のように判示しました。
※下線は当事務所によるものです。
(1) 治療費等について 84万8500円
ア 前記前提となる事実(6),前記1の認定事実(6)に証拠(甲5,乙4,6)及び弁論の全趣旨を総合すると,①原告は,本件クリニックにおいて,いわゆる自由診療の方法により本件事故による傷害についての診療を受けたこと,②その診療の開始に際し,原告と原告補助参加人との間で,個別の治療費について具体的な合意はされなかったこと,③一方で,本件組合は,本件クリニックにおける原告の治療費について,いわゆる一括払の手続を手配したこと,④その結果,原告補助参加人は,健康保険法に基づく診療報酬体系とは異なる算定方式により,総治療点数4万0176点,1点単価25円とするなどして治療費を算定し,被告又は本件組合に対し,本件組合が立替払をした平成22年8月31日までのものを含め,合計208万8860円の治療費等(文書料を含む。)を請求したこと,⑤原告は,本件訴訟において,本件事故と相当因果関係のある治療費として同額を請求していることがそれぞれ認められる。
これに対し,被告は,本件クリニックにおける原告に対する治療内容が過剰・濃厚なものであり,治療の必要性及び相当性があるとはいえず,また,健康保険法に基づく診療報酬体系と異なる算定方法により算定された治療費は相当性を欠くと主張するので,以下検討する。
イ(ア) まず,治療内容の必要性及び相当性について検討すると,臨床現場における医師による診療行為は,専門的な知識と経験に基づき,患者の個体差を考慮しつつ,刻々と変化する症状に応じて実施されるものであるから,患者に対する個々の治療内容の選択と実施については,当該医師の個別の判断を尊重し,医師に対して一定の裁量を認めることが相当である。したがって,医師による治療内容の選択と実施については,それが明らかに不合理なものであって,医師の有する裁量の範囲を超えたものと認められる場合でない限り,その必要性と相当性を欠く過剰診療又は濃厚診療であるとすることはできず,実施された治療と交通事故との間に相当因果関係を認めるべきである。
(イ) これに対し,実施された治療内容について,交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づいて賠償すべき治療費の額は,当該事故と相当因果関係があると認められる範囲に限られるのであって,治療費の算定については,治療内容の選択と実施と同様に医師又は病院の裁量に委ねられるものとすることはできない。交通事故の被害者が病院との間で一定の算定方法により算定された額の治療費を支払う旨の合意をしたとしても,被害者が当該合意に基づいて病院に対して治療費を支払うべき義務を負うのは格別,加害者は,当該合意に拘束されるものではないから,相当な範囲を超える治療費については賠償責任を負わない。
そして,前記1で認定した原告の症状の推移及び本件クリニックにおける治療の経過によれば,原告が本件事故により負った頚椎捻挫の傷害は,何ら重篤なものではなく,また,その治療の経過をみても,高度の救急措置,麻酔管理,専門医療従事者の参加等を必要とするものではなく,さらに,その治療内容についてみても,自由診療であるといっても,特に高い専門的知識や技術を要する治療がされたわけではないから,結局,頚椎捻挫に対する一般的な治療の域を出るものではなかったといわざるを得ない。したがって,原告の傷害に対する治療は,健康保険に基づく治療の範囲により実施することも十分可能なものであったということができる。
ところで,健康保険法においては,保険医療機関は,療養の給付に関し,療養の給付に関する費用の額から一部負担金(健康保険法74条)に相当する額を控除した額を保険者に請求することができ(同法76条1項),療養の給付に要する費用の額は,厚生労働大臣の定めるところにより算定する旨が定められており(同条2項),この厚生労働大臣の定めである「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)によれば,療養に要する費用の額は,1点の単価を10円とし,同告示の別表(医科診療報酬点数表)において定められた点数を乗じて算定すべきものとされている。そして,厚生労働大臣が療養の給付に要する費用の額を定めるときは,中央社会保険医療協議会に諮問するものとされており(同法82条1項),同協議会は,診療報酬につき直接利害関係を有する各界を代表する委員と公益を代表する委員によって構成されており(社会保険医療協議会法3条1項),その審議の結果出される答申の内容は,各界の利害を調和させ,かつ,公益を反映させたものとして,その内容には公正妥当性が認められる。したがって,交通事故の被害者が自由診療契約に基づく治療を受けた場合であっても,本件のように,健康保険に基づく治療の範囲により治療を実施することも十分可能であったと認められるときには,実施された治療について交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づいて賠償すべき相当な治療費の額を判断する上で,健康保険法に基づく診療報酬体系による算定方法が一応の基準になるということができる。
ウ 以上を踏まえて,原告の傷害に対する本件クリニックにおける治療内容と,当該治療について原告補助参加人によって算定された治療費等の額について,本件事故と相当因果関係が認められるものであるか否かについて検討する。
(ア) まず,証拠(乙6)によれば,原告の治療に係る本件クリニックの各診療報酬明細書においては,平成22年5月の1回を除く全ての通院治療日について,「外来管理加算」として52点が加算されていることが認められ,同点数に基づき算定された治療費が損害として請求されている。
しかし,証拠(乙2,12)及び弁論の全趣旨によれば,健康保険法に基づく診療報酬体系においては,「外来管理加算」は,処置,リハビリテーション等を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定することができ,かつ,医師による丁寧な問診と詳細な身体診察を行い,それらの結果を踏まえて,患者に対して病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに,患者の療養上の疑問や不安を解消するために一定の取組みを行った場合に算定することができるものであると認められる。
この点,証拠(乙6)によれば,本件クリニックにおいては,すべての通院治療日において理学療法が行われている上,また,原告又は原告補助参加人は,「外来管理加算」を算定する前提として,原告に対して具体的にいかなる診療行為を行ったのかを主張しておらず,上記各通院治療日に「外来管理加算」として52点を加算すべき診療が行われたと認めるに足りる証拠もない。したがって,「外来管理加算」の点数については,これを本件事故と相当因果関係のある治療費の算定の基礎とすることはできない。
そうすると,被告が賠償すべき本件事故と相当因果関係のある治療費を算定するに当たっては,本件クリニックの診療報酬明細書に記載された総治療点数4万0176点から,1回当たり52点に加算回数である122回(通院回数123回から1を減じたもの)を乗じた6344点を減算すべきである。
(イ) 次に,証拠(乙6)によれば,原告の治療に係る本件クリニックの各診療報酬明細書においては,①全ての通院治療日について,「理学療法(Ⅳ)複雑」として115点が加算されていること,②全ての通院治療日について,「マッサージ療法」として2100円が加算されていること,③平成22年5月及び9月の各1回を除く全ての通院治療日について,「鍼灸治療」として4200円が加算されていることがそれぞれ認められ,同点数等に基づき算定された治療費が損害として請求されている。
a ところで,前記1の認定事実(2)のとおり,原告は,全ての通院治療日にマッサージ療法を受けるとともに,平成22年5月22日と同年9月7日の2回を除き,鍼療法を受けていることが認められるが,マッサージ療法と鍼療法の併用は,C医師の判断に基づくものであり,また,同(3)から(5)までのとおり,当該治療により原告の疼痛症状について一定の低減効果があったことが認められる。
そうすると,原告に対してマッサージ療法と鍼療法を併用して実施したことは,原告の通院が極めて高頻度といえる時期があることを考慮しても,C医師が有する治療内容の選択と実施に係る裁量を逸脱したものとまでは認められない。
b もっとも,証拠(乙2,12)及び弁論の全趣旨によれば,健康保険法に基づく診療報酬体系においては,鍼療法と併用することができる理学療法は,消炎鎮痛措置の35点に限られ,この場合にマッサージ療法について同35点と別に請求することができないことが認められるところ,本件においては,原告に対して電気マッサージが実施されたことがうかがわれるものの,原告又は原告補助参加人において,115点の算定に相応する理学療法を実施した,あるいは,原告に対して健康保険法に基づく診療報酬体系において想定されているものとは異なる特段のマッサージ療法が実施されたとの具体的な主張をしておらず,それを認めるに足りる的確な証拠もない。したがって,35点を超える理学療法の点数部分及びマッサージ療法の実施に係る治療費部分については,これを本件事故と相当因果関係のある治療費の算定の基礎とすることはできない。
そうすると,被告が賠償すべき本件事故と相当因果関係のある治療費を算定するに当たっては,本件クリニックの診療報酬明細書に記載された総治療点数4万0176点から,1回当たり80点に加算回数である123回(通院回数と同じ。)を乗じた9840点を減算し,また,原告又は原告補助参加人の請求に係る総治療費等から,1回当たり2100円に加算回数である123回を乗じた25万8300円を減じたものとすべきである。
(ウ) 次に,証拠(乙6)によれば,原告の治療に係る本件クリニックの各診療報酬明細書においては,平成22年5月21日に「初診料」として274点が,同月30日から同年7月31日までの全ての通院治療日について,「再診料」として73点が,同年8月1日以降の全ての通院治療日について,「再診料」として74点(ただし,同年9月のうちの11回は73点と推認される。)がそれぞれ加算されていることが認められ,同点数に基づき算定された治療費が損害として請求されている。
しかし,証拠(乙2,12)及び弁論の全趣旨によれば,平成22年当時の健康保険に基づく診療報酬体系においては,初診料が270点,再診料が69点であったことが認められるところ,原告又は原告補助参加人において,これを超える初診料又は再診料を算定すべき理由について具体的な主張をしておらず,その必要性を認めるに足りる的確な証拠もない。したがって,健康保険法に基づく診療報酬体系の各点数を超える部分については,これを本件事故と相当因果関係のある治療費を算定する基礎とすることはできない。
そうすると,被告が賠償すべき本件事故と相当因果関係のある治療費を算定するに当たっては,本件クリニックの診療報酬明細書に記載された総治療点数4万0176点から,初診料に係る4点並びに再診料に係る平成22年7月31日までの84点(1回当たり4点に通院回数である22回から1を減じた21回を乗じたもの)及び同年8月以降の494点(1回当たり4点に通院回数11回を乗じた数と1回当たり5点に通院回数90回を乗じた数との和)の合計582点を減算すべきである。
(エ) 次に,証拠(乙6)によれば,原告の治療に係る本件クリニックの各診療報酬明細書においては,平成22年5月の1回を除く全ての通院治療日について,「再診時療養指導管理料」として1080円が加算されていることが認められ,これに基づき算定された治療費が損害として請求されている。
しかし,証拠(乙2,12)及び弁論の全趣旨によれば,「再診時療養指導管理料」は,労働者災害補償保険に基づく診療においては加算することができるが,健康保険に基づく診療においては加算することができない項目であることが認められるところ,原告に対する治療は労働者災害補償保険に基づく診療ではない。また,原告又は原告補助参加人において,同加算をすべき理由について具体的な主張をしておらず,その必要性を認めるに足りる的確な証拠もない。したがって,「再診療養指導管理料」については,これを本件事故と相当因果関係のある治療費を算定する基礎とすることはできない。
そうすると,被告が賠償すべき本件事故と相当因果関係のある治療費を算定するに当たっては,原告又は原告補助参加人の請求に係る総治療費等から,1080円に加算回数122回(通院回数123回から1を減じたもの)を乗じた13万1760円を減算すべきである。
(オ) さらに,証拠(乙6)によれば,原告の治療に係る本件クリニックの各診療報酬明細書においては,1点単価25円で治療費が算定されていることが認められ,このように算定された治療費が損害として請求されている。
しかし,上記イ(イ)のとおり,健康保険法に基づく診療報酬体系においては,1点単価10円で治療費が算定されているところ,原告又は原告補助参加人において,これを超える単価により治療費を算定すべき理由について具体的な主張立証をしていない。また,原告の受傷に対する治療が健康保険法に基づく治療の範囲を超えるものであったと認めることができないことは,上記イ(イ)のとおりであり,上記単価を修正すべき事情もうかがわれない。
そうすると,被告が賠償すべき本件事故と相当因果関係のある治療費を算定するに当たっては,1点単価を10円とすべきである。
このようにして、上記裁判例においては、健康保険の基準(1点単価=10円)で治療費を算定しました。
これは「一点単価10円判決」として実務に与えるインパクトは大きなものでしたが、現在においてはおおむね健康保険の基準の1.5倍から2倍程度については認める事例が多いとされており、最近では高額の診療報酬の相当性が争われるケースは少なくなってきているといわれています。
☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所まで。
☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。
【交通事故】素因減額とは何か?
素因というのは、損害の発生や拡大に影響を及ぼす被害者側の事情のことです。
この素因が原因となって損害が拡大した場合には、加害者に損害全部を負担させるのは公平ではないとして、損害賠償額を一定の割合減額するという考え方を素因減額といいます。
たとえば、事故前から椎間板ヘルニアなどの既往症があり、それが事故と相まって症状が発生したとか、症状が特に重くなったというような場合、素因減額が認められるというのが実務上の扱いです。
一方で、疾患に該当しない身体的特徴については特段の事情がない限り素因減額の対象としないとされています。
たとえば、普通の人より首が長いので症状が重くなったというような場合でも素因減額はされないということになります。
このような疾患や身体的特徴のほかに、心因的素因というものもあります。
心因的素因というのは、被害者の精神的傾向が、被害者の被害の拡大に寄与していると思われる場合のことをいいます。
被害者に特異な性格があった、回復に対する自発的意欲がなかった、賠償性神経症(相手方に対する賠償を増額させたいという願望から発症する神経症で、本人に自覚はないものの、過度に痛みなどを感じたり、訴えたりするようになること)、うつ病の既往症などが心因的素因の例といえます。
このような心因的素因がある場合、事故のみによって通常発生する程度範囲を超えていて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的素因が寄与している場合には、素因減額を認めるというのが実務の考え方です(最高裁平成4年6月25日判決)。
以上のとおり、素因には複数の種類がありますが、減額割合について明確な基準や類型があるわけではありません。
素因減額が問題となるようなケースでは、ご自身で悩まず、また安易に保険会社の提案を受け入れるのではなく、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
【交通事故】交通事故証明書の取り寄せ方法
交通事故に遭った場合、事故の存在を証明するうえで、「交通事故証明書」が必要となります。
これは、訴訟になったときだけでなく、自賠責保険の請求の際にも必要です。
では、この交通事故証明書はどのようにして取り寄せの方法について説明させていただきます。
交通事故証明書を取得するためには、自動車安全運転センターに対して、交通事故証明書の交付申請をしなければなりません。
でも、方法はとても簡単です。
自動車安全運転センターの窓口で申請する方法でもいいですし、
交番で申請書をもらって、必要事項を記載して手数料を添えて、自動車安全運転センターの事務所に郵送するという方法でも大丈夫です。
また、インターネットからも申請できるので、手軽に取得することができます。
交通事故に遭われた場合は、交通事故証明を取得したうえで、弁護士に相談に行かれることをおすすめします。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【交通事故】事故件数の推移
1年間にどのくらいの交通事故が起きているかご存知でしょうか?
交通事故件数が最多になったのは2004年で、この年の事故件数は95万2720件でした。
その後、事故件数は少しずつ減っていき、2017年は47万2069件にまで減少しました。
10年強で約半数にまで事故数が減少したということですね。
大幅に事故数は減っているといえるでしょう。
この背景には車の安全性能が格段に向上したということがあると考えられます。
最近の車は、自動ブレーキなどの先進運転支援システムが導入されているものもあり、これらの効果が事故数の減少に繋がっているのかもしれませんね。
事故数が減少したとはいえ、1日あたり約1300件もの事故が起きています。
もしも交通事故に遭われた場合は、初期対応が非常に重要です。
よくわからないまま示談するのではなく、ひとまず弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【交通事故】休業損害-専業主婦(主夫)の場合
これまで有職者の休業損害について説明してきましたが、専業主婦の場合であっても、休業損害は認められています。
主婦の休業損害の「損害額」をどのように決めるのかということを疑問に思われるかもしれません。
この点については、賃金センサスの女子平均賃金(産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均)を基礎として休業損害の額を決めることになります。
賃金センサスというのは、賃金に関する統計資料のことです。
ちなみに平成28年の賃金センサスの女子平均賃金は一日あたり約1万0300円です。
たとえば、家事労働できなかった日(休業日数)が50日であれば、
1万0300円×50日=51万5000円が休業損害ということになります。
仕事をしながら主婦をしているという方も多いですが、このような方の場合は、実際の収入が賃金センサスの平均賃金以下のときは、平均賃金を基礎として休業損害を算定することになります。
先ほどの平成28年の賃金センサスの例でいうと、実際の収入が一日当たりに換算して1万0300円を超える場合は実際の収入額を休業損害算定の基礎とし、下回る場合は1万0300円を基礎として算定するということになります。
いつの年度の賃金センサスを使うのかについては、事故の時点の賃金センサスを使うことになります。
平成27年の事故であれば、平成27年の賃金センサスを使うということです。
以上のとおり、専業主婦であっても休業損害は認められます。
主婦だから休業損害は出ないのではないか・・・
出たとしても小額だろう・・・
と思っている方もおられるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。
【交通事故】休業損害-事業所得者の場合
今回は、事業所得者の休業損害がどうなるのかということを説明したいと思います。
事業所得者とは、個人事業主や自営業者などのことを意味します。
事業所得者の場合も、給与所得者の場合と同じように事故前の収入額を基準に休業損害を算出することになります。
事業所得者の場合、基本的には、得られたはずの売上額から休業によって支出を免れる経費を控除して、収入額を計算することになります。
この売上額や経費は休業前の実績の平均的数値に基づいて判断します。
そして、事業所得者の事故前の収入額は、原則として、事故前年の確定申告所得によって認定することになります。
ちなみに、事業所得に、事業者本人自身の稼動による利益だけでなく、本人以外の第三者の労働による利益などが含まれる場合については、休業補償の対象となるのは、本人自身の稼動による利益分だけとなります。
たとえば、家族が事業を補助していたり、従業員を雇っている場合は、これらの者による利益分は休業補償の対象とはなりません。
本人自身の稼動による利益分がどの程度かは、ケースバイケースではありますが、事故前後の収支状況、業種・業態、本人の稼働状況、家族や従業員の関与の程度・給与額などを考慮することになります。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。